2007年11月18日(日)嬬恋村シンポジウム、第1回実行委員会
嬬恋村プロジェクト最初のプログラムとして シンポジウムが開催されました。
又、シンポジウム開始前に 第1回実行委員会も行われました。
[実行委員会参加者]
| 実行委員 |
|
| 委員長 水野 勝之 |
明治大学商学部教授・地域経営論 |
| 武藤 洋一 |
上毛新聞社取締役編集局長 |
| 熊川 栄 |
嬬恋村長 |
| 黒岩 鹿二郎 |
嬬恋村議会議長 |
| 松本 義正 |
嬬恋村農業共同組合代表理事組合長 |
| 戸部 一男 |
嬬恋村商工会長 |
| 市川 保 |
嬬恋村観光協会長 |
| 霜田 都次 |
嬬恋村農業委員会長 |
| 中丸 眞治 |
株式会社桔梗屋代表取締役社長 |
| 﨑 章浩 |
明治大学経営学部教授・管理会計 |
| 大友 純 |
明治大学商学部教授・ブランドマーケティング |
| 竹本 田持 |
明治大学農学部教授・農業マネジメント論 |
| 早田 保義 |
明治大学農学部教授・野菜園芸学 |
| 池田 敬 |
明治大学農学部准教授・生産システム学 |
| オブザーバー・事務局補助 |
|
| 久保 八百子(パネリスト) |
嬬恋村農業委員会委員 |
| 稲井 里香(パネリスト) |
明治大学商学部水野ゼミOG |
| 手塚 愼(パネリスト) |
嬬恋村在住者 |
| 熊野 正也(評価委員) |
大妻女子大学等非常勤講師 |
| 大川 和夫(評価委員) |
LA会員[リバティアカデミー・マスター☆☆ダブル(リベラルアーツ)] |
| 山本 幸一(評価委員) |
明治大学教学企画部教学企画グループ |
| 事務局 |
|
| 滝沢 英幸 |
嬬恋村役場政策推進課長 |
| 佐藤 重雄 |
嬬恋村役場政策推進課長補佐 |
| 宮崎 孝 |
嬬恋村役場政策推進課政策推進係長 |
| 橋詰 元良 |
嬬恋村役場政策推進課企画係長 |
| 山崎 一也 |
嬬恋村役場政策推進課政策推進係主査 |
| 久保 宗之 |
嬬恋村役場政策推進課企画係主査 |
| 浮塚 利夫 |
明治大学社会連携事務長 |
| 杉浦 哲也 |
明治大学社会連携事務室エクステンショングループ |
| 岡部 理恵 |
明治大学社会連携事務室エクステンショングループ |
| 瀬川 仁美 |
明治大学社会連携事務室エクステンショングループ |
実行委員会 会議風景
嬬恋村シンポジウム
午後から雪の予報の中、大勢の方にお集まりいただき、シンポジウムを開催いたしました。
コーディネータである水野先生の挨拶とプログラム説明のあと 熊川村長よりご挨拶をいただきました。
講演1 「観光とは何か -嬬恋農業と観光に必要な視点」 大友 純 明治大学商学部教授
講演2 「観光推進のために嬬恋農業と食を結びつけよう!」竹本 田持 明治大学農学部教授
工夫を凝らしたパワーポイントを使って、会場内の方一人一人に話しかけるような大友先生の熱く楽しい講義、時折冗句も交えながらご自分の体験談などを織り込んだ、納得感のある親しみやすい竹本先生の講義に皆さん聞き入っていらっしゃいました。
事例発表 地産地消のマーケティング -地方から発信する“全国ブランド”
中丸 眞治 株式会社桔梗屋代表取締役社長
中丸社長のお話からは 自らが作るものに対しての自信と責任を強く感じ、地域ブランドとして信玄餅が根付いた理由を納得させていただける内容でした。
会場でも 社長のお話に大きく頷かれている方が たくさんいらっしゃいました。
パネルディスカッション テーマ「こんなに素敵な嬬恋村」
 |
 |
 |
パネリスト
コーディネータ 水野勝之 明治大学商学部教授
司会進行 武藤 洋一 上毛新聞社取締役編集局長
熊川 栄 嬬恋村長
久保 八百子 農業委員会委員
手塚 愼 嬬恋村定住者
稲井 里香 明治大学商学部水野ゼミOG
中丸 眞治 株式会社桔梗屋代表取締役社長
大友 純 明治大学商学部教授
竹本 田持 明治大学農学部教授
池田 敬 明治大学農学部教授 |
武藤氏の的確な司会進行の中、それぞれの立場から嬬恋の良さを発見させる色々なお話が伺えました。
質疑応答では 来場者の方からの質問をいただき、それぞれの立場からパネリストが回答しました。 会場内が一体となる素晴らしいパネルディスカッションになったと思います。
シンポジウム閉会後は、受講者のグループ分けを行い、各グループで話し合いを行いました。
 |
[テーマ]グループの目標を理解し、地域の良さを見つける
(1)展示会・店舗経営企画グループ
(2)嬬恋アグリカレッジ企画グループ
(3)H20年度農業体験企画実行グループ
(4)新ブランド構想グループ(まちおこしのためのグルメブランド作り) |
みなさん、とても熱心に意見を出し合っていて 今後のプログラムへの意気込みが感じられました。
次は12月10日のテレビ会議で 各グループからの報告を行うことになっております。
いよいよ始動した嬬恋村プロジェクト、これからのプログラムが楽しみです。
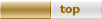
|














