座談会
入学して新しい価値観に気づく。それが国際日本学部の魅力
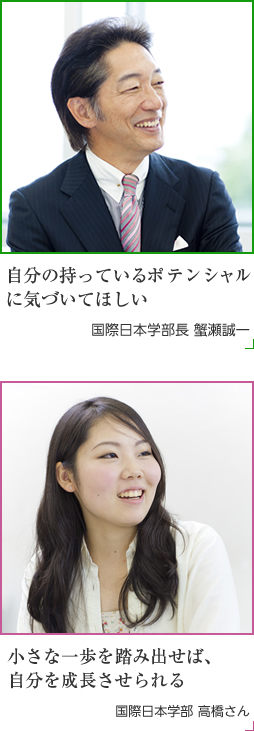
蟹瀬 誠一学部長(以下、蟹瀬) 今日は国際日本学部の魅力について語っていただきます。まず、みなさんがこの学部を選んだ理由は?
若林 リュボーフュさん(以下、若林) 来日前から日本の古い文化に興味があり国際日本学部の伝統文化が学べる授業に関心がありました。また、マンガやアニメに象徴されるサブカルチャーなどの新しい文化についても勉強できるカリキュラムに魅力を感じて国際日本学部に編入しました。初めは日本文化以外の国際科目を学ぶことが負担だったのですが、日本文化をより深く理解するためには、外国と比較することが大切だとわかりました。おかげで来年は科目選びがより楽しくなると期待しています。
蟹瀬 自分が勉強したいことが見つかり、それに集中するのもいいけど、同時にこれまで全然興味がなかったことに目を開かされ、新しいことについて興味を持って調べてみるというのも、時間が自由になる大学生ならではの特権だからね。また、サブカルチャーは今や日本を象徴する文化として世界から注目されていますが、明治大学ではサブカルチャーを専門とした「東京国際マンガ図書館」を2014年に開館を予定しています。 続いて岡部くんはどうですか?
岡部 輝さん(以下、岡部) 実家が和菓子屋を営んでいるため、日本の季節感とか素朴さなどに触れながら育ってきました。それで、もっと日本の文化について知りたいと思い国際日本学部を志望しました。文化を学ぶ際、外国と日本という視点でとらえがちだったんですが、実際に入学して、もっと身近な世代間とか男女間でも文化が生まれるということに気づきました。だから今では、文化をもっと広い視点でとらえられるようになりました。同時に、多くの国の留学生と一緒に学ぶことで、日本人としての視点だけではなく、アジアからの視点、ヨーロッパからの視点と、幅広い視点から改めて日本をとらえることができ、今では毎日新しい日本が見えてくる感じで楽しいです。
蟹瀬 世界には200近い国があるから、200近い視点がある。どの国も地球上でみんな平和に暮らしたいという思いがあって、それを実現するためにどうやって合意していくべきか、というのが世界共通の課題。国際関係、国際交流で大切なのは、こうした視点の違いをどう認め合うべきかを考えることだということを覚えておいてほしいね。 高橋さんも日本文化への興味から?
高橋 美佳子さん(以下、高橋) 私は、コミュニケーションの手段としての英語をしっかり勉強したいという気持ちがありました。また、海外を訪れた際、その国の人は自分の国に誇りを持っていて、自分の国の文化や制度について明らかに日本人の学生より通じていると気付き、今後は、自分たちの国のことをきちんと学ばないと世界に出ていけないと感じたためです。だから、その二つがしっかり学べる国際日本学部のカリキュラムに惹かれて入学しました。
蟹瀬 英語の授業は通常の4倍くらいあるから鍛えられるようだね。僕自信、ジャーナリストとして様々な国を取材してきたけれど、そこで気づいたのは、外国において日本人としてのアイデンティティを確立すること、例えば、自分の国をどれくらい愛しているかを示せるかが思った以上に大切だということ。それによって相手から信頼されたり、尊敬されたりすることが多い。だから、国際日本学部ではそうした「日本を愛して、日本を語れる」人材育成を行うことを目標の一つにしているんだ。
学生生活を通して自分の持つポテンシャルに気づいてほしい
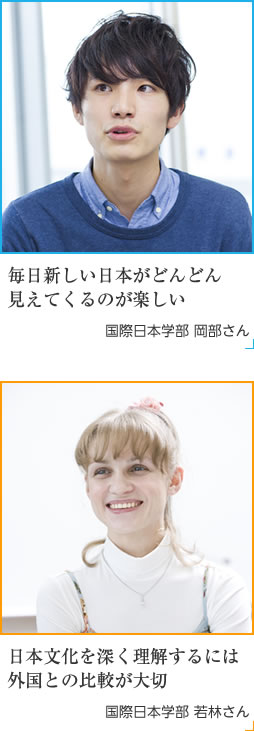
蟹瀬 続いて具体的に国際日本学部で学んだことや、経験したことを聞かせてください。まず若林さんは、この夏、学部内のスピーチコンテストで活躍してくれたね。
若林 はい。「いただく命」というタイトルでスピーチしました。私も含めてですが、ずっと食べ物を無駄にしてしまっている人が多いと思いと感じていました。例えばハンバーガーを食べる時なども、それが作られる過程を見てないので、もともとは生き物だったという自覚がないから粗末にしてしまう。命を「いただいて」自分の命を維持しているという自覚を持つことで、少しでも食べ物を大切にするようになればという思いを込めました。
蟹瀬
今、グローバライゼーションが叫ばれ、企業からも日本だけではなく世界のどこでも働ける人材、つまり、自分の考えていることをきちんと表現できる人、自分で問題を探せる人、与えられた問題を解くんじゃなくて問題を自分で探していける人が求められているから、いい訓練になったんじゃないかな。
高橋さんはやっぱりフロリダのディズニーワールドへのセメスター留学が一番の思い出かな?
高橋 はい。ディズニーワールドでのインターンシップに参加したのですが、7か月間の滞在で英語が上達したのはもちろんですが、ディズニー流のホスピタリティ精神とか、リアルなアメリカの生活を体験できたことが一番の収穫です。もちろん当初は苦労した場面も多くありました。私の職場は南米からの移民の方が多く、独特の発音がうまく聞き取れませんでした。最初は自分から話しかけられず、つらい思いをしましたが、除々にスタッフやゲストとの会話を楽しむことができました。だから、これから留学を考えているみなさんにも、自分から積極的に行動してほしいと思います。自分から話しかけるという、小さな一歩を踏み出しさえすれば、どんどん自分自身を成長させることができるという実感がありましたから。
蟹瀬 明治大学の学生はいろいろなポテンシャルをもっているから、自分が思っている以上のことが、実はできるということを知ってもらいたいね。どういう機会をつかんで花咲かせるかということは、みなさんの努力もありますが、大学が、留学制度やスピーチコンテストなどの機会をもっと充実させることで後押しできたらいいと考えています。 最後に、岡部くんの大学生活はどんな感じですか?
岡部 僕はゼミの活動に力を入れており、現在、偏見を持たれる方の立場について考えるというテーマに取り組んでいます。例えば性同一性障害の方や、障がいを持っている方と一対一で話し合うことで新たな価値観を共有させて頂いています。他にも、アルコール依存症から回復された方、ギャンブル依存症から回復された方、上肢、下肢の切断障がいを持った方が行うアンプティサッカーの日本代表の方のお話を伺う機会を得て、貴重な経験ができました。
蟹瀬 国際日本学部では、教員はもちろんですが、なるべく外部の方、つまりいろいろな企業や自治体や団体などとうまく連携して、みなさんが様々な価値観に出会えることをサポートできるよう努めていこうと考えているから、積極的に参加してほしいね。
コミュニケーション能力を武器に世界と日本の橋渡しを

蟹瀬 最後に、卒業後みなさんはどういう方向に進んでいきたいですか?
若林 私は旅行業界に興味があります。例えば通訳ガイド。観光客はもちろんビジネスで日本を訪れた方に、正確な日本の情報を伝えることが大切だと思っています。旅行をするだけでも視野が広がったり、何より楽しいですから、ぜひたくさんの方に旅行の楽しさを経験して欲しいと思っています。
蟹瀬
「百聞は一見に如かず」で、本で読んだりテレビで見ていても、実際にその場所に行ってみると全く違うということがよくあるね。ジャーナリストは、現場に行くことが一番大事で、自分の目で見て、耳で聞いて、それこそにおいまで嗅いで事実を伝える。それがジャーナリストの仕事ですからね。
岡部くんは実家の和菓子屋さんを継ぐの?
岡部 いいえ。異文化教育学の授業で留学生について学んでいて、文部科学省が推進する「留学生30万人計画」に興味を持ちました。ですから、今後留学生が海外からたくさん日本へ訪れてくれるよう、橋渡しができる仕事に就きたいと考えています。今学んでいる英語も活かせると思いますし、何より日本文化や魅力をアピールして多くの学生が日本に集まってくれたらいいと思います。
蟹瀬 留学をコーディネートする仕事だね。今すでにいくつか会社があるけど、そういうところで数年務めてノウハウを学んだら、ぜひ自分で会社を作るくらいの気持ちで頑張ってほしいね。明治大学は海外留学の拠点校として「グローバル30」に選ばれたわけですが、いよいよ2011年4月から全ての単位を英語による授業で取得できる「English Track」がスタートするんだ。それにより、英語圏をはじめますます多くの留学生がこの学部に集まってくれることを期待しています。

高橋 私は留学したことで改めて日本の素晴らしさに気づくことができました。特に日本のサービスやおもてなしは素晴らしいものだと思っていますので、ホテルや旅館に勤めて、世界に通用する、日本らしい「おもてなし」を伝えていきたいと考えています。
蟹瀬
これからは日本をもっと楽しい国にしなければいけないと思う。実はもっと楽しいところがたくさんあるのに、それを僕ら日本人自身もうまく見つけられていないんじゃないかな。そのあたりは海外の人の方が見つけるのが上手ですね。「クールジャパン」という言葉は、そもそもアメリカ人が言い出したわけだから。外から見てもらったおかげで日本の良さを発見するってこともあるよね。
みなさんには、ぜひこれからもここ国際日本学部で他では味わえない貴重な時間を過ごしていただき、日本と世界を結ぶ橋渡しをしていただくよう期待しています。
