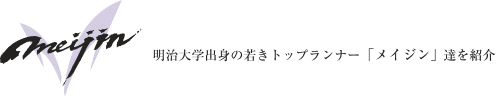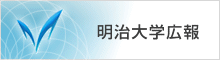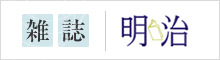関心というのは愛だから。
愛のない人は関心を持てないんです
おなじみの居食屋「和民」を中心とした外食事業をはじめ、教育や介護、農業と多岐に渡る事業を展開する渡邉美樹さん。生まれ持った類い稀なリーダーシップを発揮し、周囲の人たちをぐいぐいと引っ張っていく。そのバイタリティーと人を惹き付けてやまない魅力は、大学時代から遺憾なく発揮されていた。
明確な2つの目標を掲げた大学時代
もともと大学に行く気はなかった。社長になるから大学は必要ないと思って。でも何の社長になるかは決めてなく、高校3年時の担任の先生に「それを決めるためにお前、大学に行ってもいいんじゃないか」とアドバイスを受け、大学への進学を決心した。
あまり大きな声では言えないけど、明治大学に入学してもほとんど学校に行かなかった。でも、私は大学に行くということに対して2つ目標を立てた。一つは将来、何の社長をやるか見つけること、つまり事業探しのため。もう一つは、社長の模擬体験というか、組織というものを自分で動かそうと思ったんです。
海外で見つけた幸せを運ぶ食の魅力

大学2年の時は漠然と人がびっくりするようなビジネスをやりたいとだけ思っていた。その頃に読んだ国学者の安岡正篤さんの本に、「新」という字は立つ木に斧を入れるとあった。もともとあるものに工夫をすることで新しいものができる、というわけ。
その時、ビッグビジネスというのは意外と身近なところに転がっているんだと思った。それなら日本人の生活からビジネスを探してみようと、日本一周の旅に出たのです。でも、この旅では答えを見つけることはできませんでした。
大学4年生になると、事業は人・物・金・情報から成り立つと知った。しかし、当時の自分に物・金はない。人という要素だけで勝てるビジネスとは何だろうかと考えた結果、コンピュータのソフト開発と外食事業ならできると思った。この2つを念頭に入れながら、今度は北半球一周を目指して世界に飛び出した。
旅をして感じたのは、世界は差別と偏見の固まりだということ。主義主張が違うとか、お金があるとかないとか、男とか女とか、宗教が違うとか、肌の色が違うとか、そんな些細なことでいがみ合っている。人間というのはつまらないことでいがみ合っているんだと半ば失望していた。そんな矢先、ニューヨークのグリニッジ・ビレッジのライブハウスで、世界中の人たちが一体になっているのを目にした。みなが歌い、踊り、お酒を飲んで、世界が一つになっていたんです。私の目から見ると、そこは一つの地球だったんです。人間というのは美味しいものがあって、いい雰囲気といいサービスがあって、好きな人と一緒にいる時は、本当に素敵な顔をするんだ。自分もこんな場面を提供したい。それならば、外食をやってみようと決心したのです。
あるべき組織、あるべき経営の姿

旅に夢中になる一方、「横浜会」という横浜から明治に通う人間が集まるサークルで59代目の幹事長も務めていた。そこで私は、サークルの歴史に残ることをしようとビジョンを掲げ、横浜文化体育館で1万2000人を集める大コンサートを開いた。明治大学マンドリンクラブを呼んで、それだけでは1万人も集まらないから大物演歌歌手も手配して。1枚1000円のチケットを売って、一晩で1200万円の売上を出した。経費はその歌手の出演料とあとはマンドリンクラブのバス代と弁当代だけ。残り全部が利益なんです。コンサートでの収益は「目の不自由な子どもたちに読書を」というのがテーマでしたから、目の不自由な子どもたちを応援することもできました。
なぜそんな大それたイベントができたかというと、そこにいる百何十人の仲間みんながボランティアで働いてくれたからなんです。誰から頼まれるわけではなく、その仲間と一緒にいることが嬉しくて、その事業をみんなで立ち上げるのが嬉しかった。つまり、みんながわくわくするような大きな目標を仲間と共有しながら、好きな仲間と一緒に仕事をするということは、みんなただでも行動するわけです。
その時、私が作りたい組織というのはこういう組織なんだと思った。私はこの経験であるべき組織の姿、あるべき経営の姿を見つけた。だから大学の4年間というのは、何ものにも代え難い大切な時期だと思っているんです。
社会への関心、それは愛でもある

私は人間は好きなことをやって生きていいと思っている。好きなことなら頑張れるし、頑張れるから上手になる。上手になるからもっと好きになる。そういう循環があるんです。好きなことはビジネスにならないとか、好きなことだけ求めていいのか、といったことを言う人もいますが、人生というのは苦しむものではなくて楽しむものですから。ただし、明治大学を目指す学生や明治大学を卒業しようとしている学生には、社会に対して関心を持って欲しいと思う。何をやっていいか分からないとか、好きなことが見つからない若者は今いっぱいいる。そんな彼らは社会に対して関心を持っていないんです。今ここで日本人として生活していることに対する責任を感じ、そこから好きなもの探しを始めたらいいのではないかなと思います。でも、これは厄介なんです。関心というのは愛だから。愛のない人は関心を持てないんです。
私は今、カンボジアで農業を始めることにもの凄く燃えている。カンボジアで数ヘクタールという面積から農場をはじめるんです。なぜそんなことをしようとしているかと言うと、200ヘクタールあれば、1万人の孤児がご飯を食べられるようになるから。カンボジアには10万人の孤児がいる。その10人に一人を食べさせられるわけ。それを考えるとわくわくしてくるんです。
もし私が彼らのことを好きでなければ、カンボジアの孤児のことなんて知ったことではないわけです。でも私は彼らを好きなんです。好きだから彼らがご飯を食べられていない現状を知ったし、また彼らの生活も知った。抽象的かもしれないけど、まず、みんなの中に本来ある愛を掘り起こして欲しい。そこで必ず関心が生まれてくるから。関心をもとにいろいろな情報を集め、そこから自分の好きなことを探していけばいいと思います。
バイタリティーの源は人一倍強い「欲」
私はいろいろなことを手がけて、バイタリティーに溢れていると言われる。その源は何かと言うと、「欲」なんです。私の欲は生まれてきたからには人と係わりたい、人の幸せに係わりたいという欲。10歳の時に母親の死に直面し、人間というのは必ず死ぬことを知った。時間は有限なんです。このことを嫌というほど知っているから、時間をとても大切にする。だからいっそう生きている間に何かをしたいという欲が生まれてくるんです。
私は自分の会社の社員が増えることが一番嬉しい。なぜならば社員4000人の人生と係わっていけるから。カンボジアで孤児院もやっていますが、同じように孤児院が増えていくのも嬉しい。私の孤児院には今、74人の子どもたちがいるけど、彼ら を自分の子どもとして育てている。そうやって彼らの人生に係わっていくのが嬉しいんです。それが自分の存在対効果。対効果というのは人の幸せや喜びなんだけども、存在対効果を高めていくことの欲が自分の中でとても強いんです。さらに、私は好きなことや楽しいことしかやらない。だから、いつも元気でいられるんです。
- ワタミ株式会社
- 居食屋「和民」などの外食を中心に、介護、高齢者向け宅配、農業、環境事業を展開。「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」をスローガンに、「地球人類の人間性の向上のためのよりよい環境をつくり、よりよいきっかけを提供すること」というミッションの達成のために事業活動を展開する。
-
〒144−0043 東京都大田区羽田1−1−3 TEL 03−5737−2288 FAX 03−5737−2700
ワタミ株式会社
History of Miki Watanabe
- 1959年
- 神奈川県横浜市に生まれる。
- 1970年
- 最愛の母親の死、父親の会社清算を経験し、将来は社長になることを決意。
- 1978年
- 明治大学商学部に入学。在学中、日本一周、北半球一周の旅に出る。
- 1982年
- 大学卒業後、会計システム会社に半年勤務。会社経営に必要な経理を修得する。
その後、起業資金を貯めるために運送会社に転職。 - 1984年
- 現ワタミの前身となる有限会社渡美商事を設立。
「つぼ八」FC店のオーナーになり、飛躍的に売上を伸ばす。 - 1992年
- つぼ八とのFC契約を解約する約束をし、居食屋「和民」を展開。
- 1999年
- 外食産業で世界初となるIS014001を取得。
- 2000年
- 会社を東証一部市場に公開(96年店頭公開、98年東証二部市場に公開)。
- 2001年
- 特定非営利活動法人 スクール・エイド・ジャパンの理事長に就任(現在は公益財団法人として活動中)。
- 2002年
- 有限会社ワタミファームを設立。千葉県で農場運営を始める。
- 2003年
- 学校法人 郁文館夢学園理事長に就任。
- 2004年
- 医療法人盈進会 岸和田盈進会病院 理事に就任(07年より理事長)。日本経団連理事に就任。
- 2006年
- 持ち株会社体制に組織を改め、「人」が差別化となり、コツコツと売上・利益を積上げる事業のみを展開する。
- 2008年
- 高齢者向け宅配事業へ参入する。
- 2009年
- ワタミ株式会社代表取締役会長・CEOに就任する。