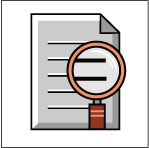| 明治大学現代GPニュース第10号 平成18年12月22日発行 |
 |
|
|
| 現代GP 地域連携プログラム 成果報告発表会 〜地域に生きる学生力!〜 |
|
12月2日に行われた発表会では、以下(発表順に掲載)のプロジェクトが報告を行いました。各プログラム(proj.4〜7、9)の詳細は現代GPニュースNo.8号にも掲載しています。 【各発表のタイトルと質疑応答・コメントを一部掲載】 |
|
■proj.3 中林ゼミ 大地震における千代田区内の帰宅困難者支援〜大学の立場として出来ること〜 もし突然千代田区で大規模災害が起きたとき、大学側が出来ることを提案。 Q;学生自身が帰宅困難者になった場合、学生ボランティアを投入できないがどうしますか? A;現在研究中ですが,学生の中でも自宅から近距離、遠距離とに分けて優先順位をつけるのがよいかと思っています。 ■proj.10 山下ゼミ 採用・就職目的のインターンシップにおける「負の側面」 インターンシップの社会的関心が高まる現在、インターンシップの正の側面だけでなく負の側面から考察。 Q;大学生側から見た負の側面ではなく、企業側からみた負の側面はどのようなものがあるでしょうか? A;企業側からの視点からみたデメリットにも気付いたので今後の研究としていきたいです。 ■proj.4 大友ゼミ 老舗企業のマーケティング特質に関する基本的考察 次々に流行に合わせた新しいお店が現れてくる中、伝統を武器に生き続ける老舗の経営戦略を分析していく。 Q;老舗というものになじみのない若者に対して、老舗は企業努力をしているのでしょうか? A;とらやでは表参道にカフェを出すなどし、若者向けに新しい時代に合わせて事業展開をしています。 ■proj.5 大友・戸崎ゼミ カレープロジェクト結果報告 多くのカレー店が集積する神保町。横須賀の海軍カレーと定義を比較した上で街の活性化を目指した神保町カレーマップを作成、その過程を報告。 コメント(山下教授);横須賀と神保町の比較では、神保町のカレー提供店は多様性や個性があるというポジティブな表現がよいのでは。今度マップを作成する際は明治大学がもっと目立つようにしてもらえるといいです。 ■proj.7 富野ゼミ 金銭教育成果報告 カレー販売という実践を通して、小学生への金銭教育の過程を報告。 Q;この活動をどうゼミの活動に結びつけますか? A;ゼミ員の意見のまとめ方、企画・デザインの構成などこれからの卒論作成にあたりそれらが生きてくると思います。 ■proj.9 水野ゼミ 観光事業を通じた嬬恋村の地域活性化 嬬恋村の3回の農業体験ツアーを開催、グリーンツーリズムを通した村活性化の報告。 Q;季節や時期によって何か工夫しましたか? A;農業の出来ない冬の時期にダイレクトメールを送るなど情報発信に重点をおき活動しました。 ■proj.6 熊澤ゼミ 空き店舗事業「なごみま鮮果」報告 東京三浦市店として三浦市の物産を販売し、情報を提供する店を神田の空き店舗を使い運営。店づくりの過程、現状を報告。 Q;次のイベントはどのようなことをやるのですか? A;12月に三浦市ご招待ツアーを企画しています。それによって、三浦のよさを知ってもらおうと思っています。 |
| 【意見交換会】 ■横井先生
■山下先生 今までの学生の活動の成果を論文としてペーパーにし、商学論叢という商学部のジャーナルにGPの特別号として発行したい。各担当の先生にプロジェクト紹介を書いてもらい、学生はゼミの専門分野に絡めながら共著で執筆をお願いしたい。 ■事務室(田子、藤田、菊池) 学生の柔軟な発想で目標が決まったらまず提案してみてほしい。役所、教育機関、地域住民など様々な人と接するので困難もあるが多く学ぶチャンスであると思う。プロジェクトとして提案を実行できるかどうかを判断し、事務的にサポートして行く。全学的にも、いろんな人を巻き込んでいってほしい。 ■富野先生 今回、専門領域以外でこの現代GPのプロジェクトに取り組んだが、教員・学生側としても物理的にも、モチベーションを高めるにも大変であった。ゼミで取り組むことについては、統率力がとれやすい、動員をしやすいといったメリットはあるが、その分デメリットも大きいと思う。今度、取り組み体制整え、全学的へ募集をおこなったり、活動を単位化するなど検討してみてもよいのでは。 |
| 【参加者の感想】 どのプロジェクトの参加者も、「学んできたことをいかに目前の課題に適応させるか?」といった壁にぶち当たったのではないでしょうか。普段の授業やテストでは理解したつもりでも、いざ地域社会で使ってみて、と言われると何もできないものです。でも色々な人とのコミュニケーションによってその壁を乗り越え、良いものを創り出せることもわかったでしょう。社会と関わり合い、社会人の予行演習ができる。現代GPはそんなお得なプログラムだと思いました。(大友ゼミ 3年 村上裕美) |
| 老舗プロジェクト インタビュー |
Q.「老舗」研究を通して理解したことは? A. 老舗というのは、意識せずとも世間から信用される「仕組み」が備わっており、それが長寿の秘訣になっている。お客さんのためを思い、当たり前のことを当たり前にすれば(これは簡単なことではありません)商売は長続きするのではという結論に至りました。(長谷川) Q.どれぐらいのペースに論文作成にとりくんだのか?振り返ってみて大変だったことは? A. 構成を組み立て始めたのが7月で、夏休み中も毎週2回グループで集まり、朝から晩まで取り組んだり、締め切り前は徹夜で仕上げました。大変だったことは、みんなのベクトルを一つの方向にまとめることでしたが、包み隠さず意見を出し合い、お互いに理解しあうことで乗り越えることができました。また、論文の決まった形式に慣れておらず戸惑いましたが、先生や大学院生の添削があってやっと完成させることができました。(長谷川・関) Q.一番心に残っていることは? A. 3ヶ月から4ヶ月かかって作り上げた論文をみんなで無事提出できた瞬間は、今までの学生生活の中でも一番感動したことと言えるかもしれません。実は、少し泣きそうでした。(長谷川) Q.最後に一言 A. アンケートやヒアリングを通して多くの地域の方々の協力を頂き、また、有名な老舗の社長さんや老舗研 究の権威のお話を聞けたことは貴重な体験となりました。今は老舗に関して語らせたら長いですよ。今後 のゼミ活動でもこの経験を発展させていきたいです。論文応募の注意点として、今回は締め切り1週間前に大きな修正ポイントに気づき、仕上がりまで焦ったので、出来る限り早めに先生方や院生にお願いして内容を見てもらうことは大切だと思います。(関・長谷川) |
| 12月のイベント |
◆年末三浦市お買物ツアー |
| 編集後記 今回の現代GPニュースでは現代GP「広域連携支援プログラム」成果報告発表会を取り上げました。現代GP活動報告会では、通常各プロジェクトごとに行われている活動のいわば全像が見える形となりました。そのような意味で、自分達のプロジェクトがどのような活動をしているのかを他のプロジェクトの皆さんにも知って頂くすばらしい機会となりました。プレゼンターの皆さん。お疲れさまでした。また節目節目にこのような機会があるといいですね。また、老舗プロジェクトについては、夏休み等を通じて皆さんが努力されたことが実を結んだことに、大変うれしく思います。本当におめでとうございました!今回賞を受賞されなかった他のプロジェクトの皆さんも、情熱を注いで取り組んだことは、学生生活の財産です。大きな蓄積として今後に生かしてください。(河内) |
| 現代GPニュース編集協力 商学部3年 野本なつみ 長谷川豊康 村上裕美 山本和輝、 商学研究科 河内俊樹 |
| │ チェーンプロジェクト概要 │ GPニュース │ トップページ │ |