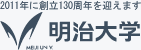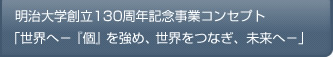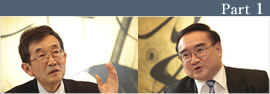深刻化する世界の食糧問題。国内でも食料自給率、産地や賞味期限の偽装問題など、様々な 問題を抱えている。このような社会的状況に対し、大学の研究が果たす役割は大きい。これ からの食糧問題への取り組みについて、商学部長と農学部長が対談した。
- どちらの学部もフィールドワークを重視していますね。最後に、世界に羽ばたく人材の育成についてお聞かせください。
横井 国境を越え、外に発信できる学生を育てる目的もあり、カリキュラムの世界標準化を進めています。具体的には、授業の英語化です。英語科目の授業だけではなく、一部の専門科目についても英語の授業を取り入れています。英語のみで授業を行っているゼミもあります。
人材育成については、一言でいうのは難しいのですが、ここ数年、学生の姿勢が大きく変わってきました。教室で授業を受けて、試験を受けて、単位を取るだけではなく、それを踏まえて社会に出て様々な取り組みを行い、その成果を社会に向けて発信していく学生が増えています。
今年はホンダがハイブリッドカー「インサイト」の企画・設計から製造・販売までの全体像について半年かけて学生に講義してくれました。最後は関係者の前で学生たちが彼らなりの提言を行い、高い評価をもらっています。授業でフランス語の単語集を自分たちで編集し、出版社を通して出版にこぎつけるなど、レベルの高いことをやり遂げる学生が増えています。最近では、学生が商学部の広報活動にも取り組みました。OBの指導も受け、『商学部の現場』という冊子を刊行するという成果を出しています。
商学部のコミュニティーの一員として、大学の教育研究の成果を社会に発信できる学生、自立した学生を育てていきたいと思います。
田畑 農学部でも、現場で問題を発見し、それを解決できる能力を養うことを重視しています。国際機関で働くことを希望している学生が多いのも特徴です。グローバルな視点と、ローカルな視点の両方をしっかり合わせ持って、物事を考えることも重要です。国内外問わず、どの分野でも活躍できる人材を目指しています。新時代を担いうる広い視野と専門知識、技術、豊かな人間性を備えた人材として育ってほしいと思っています。
また、農学部の特徴として大学院に進学する学生の割合が非常に多いこともあげられます。専門知識をしっかり身に付けることで、大学院、さらに就職しても活用できる人材を育てたいと思います。
- 農学部は他の理系と比べても女性の割合が多いですね。
田畑 多い学科で半数、少ない所でも3割程度が女性です。このことは、食や生命などに対する女性の関心が高まっていることの反映ではないかと考えています。
- 商学部
- 新たな時代の要請に柔軟に対応できる1学科7コース制のもと、幅広い領域を学び、特定の分野で市場のスペシャリストを養成するための教育カリキュラムを実践している。徹底した少人数ゼミナール教育のもと、商学専門演習と総合学際演習を同時に履修することで、ビジネスパーソンとして必要な深い専門性と広い教養の修得を可能にしている。
現在、学部創設105年目を迎え、「Project105商学のフロンティアを拓く」という教育改革プロジェクトを新たに掲げ、(1)「先端的な学術研究・地域活性化研究の推進(研究の見える化)」(2)「学生主導の社会連携活動の展開」(3)「カリキュラムの世界標準化」(4)「体系的な初年次導入教育の実践」という4つの視点から、わが国の大学における商学教育をリードし、教員と学生が一体となってその成果を国際社会に発信していくことを目指している。
- 農学部
- 1946(昭和21)年に設立された農学部は、現在農学科、食料環境政策学科、農芸化学科、生命科学科の4学科を擁している。川崎市多摩区に位置する生田キャンパスで学部・大学院生約2500名が一緒に学んでいる。
「食料」・「環境」・「生命」という21世紀を象徴するキーワードを軸にして、生物の生命現象の解明、生命機能を有効活用した食料や食品の生産、およびそれらの効率的流通による安定供給、さらには、緑豊かな生活環境や自然環境の維持・創生などを全地球的・全生物的視野に立って把握し、対処できる人材を養成することを目的に総合的な教育を実施している。
2012年には、川崎市麻生区の黒川地区に新たな農場を開設、都市型農業としてのハイテク技術やエコ技術を駆使した植物生産システムや地域社会との農業交流を行なう。21世紀型の都市型農学部を体現する新しいシンボルとして期待が集まっている。