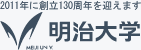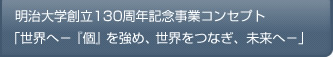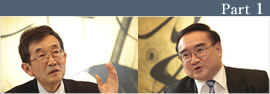深刻化する世界の食糧問題。国内でも食料自給率、産地や賞味期限の偽装問題など、様々な 問題を抱えている。このような社会的状況に対し、大学の研究が果たす役割は大きい。これ からの食糧問題への取り組みについて、商学部長と農学部長が対談した。
- 世界的な「食」の問題に対するアプローチとして、どのような取り組みを行っているのでしょうか。

横井 関連する専門科目としては、貿易論や流通システム論などがあります。それらを踏まえて、実践的なフィールドワークを行っています。
今日、大量生産、遠距離輸送やそれを支える都市交通システムなどが高度に発展した結果、大量消費社会が誕生しました。そのなかで、農産物の流通システムにもかなり問題が生じてきています。そして、そのため生産者と消費者が疎遠になり、さらに、昨今の食糧問題や偽装などの事件が起き、ますます消費者の食品や農産物への不安が高まってきています。
そういったことを背景として、最近では「地産地消」や「食の安全」が注目されてきておりますが、「社会連携」や「地域貢献」に積極的に取り組んできている商学部では、学生たちが群馬県嬬恋村などで企業や自治体と連携してフィールドワークを行っています。
長野県飯田市でも、市や地元のNPO法人とともに、現地の魅力や問題点についての分析を行いました。このプロジェクトでは、飯田市長に「飯田市における農業ビジネス」と題した、様々な企画を提案し、実現に向けて動き出しています。
また、神田を拠点に神奈川県三浦市の海産物を販売する実践店舗「なごみま鮮果」を学生のみで運営するプロジェクトもあります。仕入から販売まで、すべての店舗経営を通し、商学の実践と社会連携や地域貢献を体験しています。
このような取り組みを通し、日本の食料自給率や、農業、漁業の現状を初めて認識する学生は多く、食料問題に対しての意識を高めています。さらに、新しい農業ビジネスの提言やプロデュースなど、社会貢献や地域活性化の研究・報告も行っています。

田畑 農学部では、一年生全員を対象とした農場実習をはじめ、農家に一週間ほど寝泊まりして農作業を手伝う「ファームステイ研修」やゼミ毎のフィールド調査実習、あるいは様々な生物や生態系の野外での観察、緑化・景観の研究、圃場での作物栽培実験など、学生が「農」の実態にふれ、農学を学ぶインセンティブを養う機会としても、実験室での研究と並ぶもう一つの研究方法としてもフィールドワークが重視されています。
昨年、世界的に食料価格が高騰して食糧問題がクローズアップされ、食品偽装などで食の安全・安心にも国民の関心が高まっています。世界的な食料需給の見通しなどについては様々な見方がありますが、いずれにせよ、食料を安定して持続可能な形で供給する体制、環境を整備していくこと、そのための技術開発が今後ますます重要になっています。
そのために農学部では例えば低炭素・窒素排出を目指した食料生産技術の開発や農薬に頼らない病害抵抗性植物の開発など、食料の持続的供給に向けた基礎研究と応用研究の両面に力を注いでいます。さらに2009年度には経済産業省の補助事業の採択を受け、土地や気象の制約をあまり受けずに食料の安定的供給を図ることや農業の産業化に貢献することが期待される「植物工場」の基盤技術の研究センターを立ち上げることになりました。
- 日本の農業技術は世界最先端といわれていますが、技術移転についてはどうでしょうか。
田畑 日本の進んだ農業技術を海外に移転し、食料生産力を上げることに貢献することは、非常に素晴らしいことです。
今後もそれが一層進むことが期待されます。同時に貿易商社が介在してそれが逆輸入され、国内農業を圧迫することにならないよう貿易のあり方を考えていくことも大事だと考えています。
横井 途上国の支援や環境保護の観点からは、途上国の原料や食品を適正な価格で継続的に輸入するフェアトレードについても、本来の意義が問い直されはじめています。
- バイオエタノールが注目されて、原料のとうもろこしなどの買い占めなどで相場や金融にも大きな影響を与えていますね。
田畑 化石燃料に代わるエネルギーとして非常に注目されていますし、重要な問題だと思います。同時に、食料を転用することで、価格の高騰を招き、批判的な意見も高まりました。
そこで、今注目されているのは、第二世代のバイオエタノールと言われている、穀物や糖分ではなく、セルロースを使用する技術の研究開発です。日本も大いに貢献しうる余地があると思います。食料とエネルギーの対立ではなく、もっと広汎に存在する資源をエネルギーにする技術開発に期待したいと思っています。