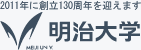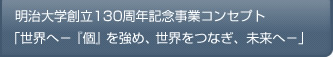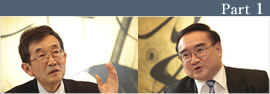地球温暖化やエネルギー問題など、環境を取り巻くテーマが国際会議でしばしば取り上げられる ようになってきた。さらに、その対策として、技術開発や法整備も急速に進んでいる。地球規模 での持続可能な社会の構築に向け、法学部長と理工学部長が対談した。
- 地球温暖化問題に取り組むうえで、法学的・理工学的な視点からどのようにアプローチされているのでしょうか。

高地 環境基本法が平成5年に制定され、そのほかにも各種のリサイクル法、資源有効利用促進法、古いところでは、廃棄物処理法などが作られています。これらの法律のように、廃棄物を出す側に対する規制という観点から法整備がなされています。
また、これからは風力や太陽光による発電といった、エネルギー開発の観点からの法整備も必要になってくると思います。具体的には、余剰電力の継続的な買い上げや、新しい技術開発への助成といった取り組みになると思います。
法律的なアプローチは、主に行政がリードしていくという側面が非常に強いと思います。政府の取り組みが非常に重要になります。というのも、法律というのは、あくまでも手段で、実施するのは政治の役割となるからです。
現在の日本の環境に関する法整備は、ヨーロッパと比較すると、それほど進んでいません。ヨーロッパでは、風車などによる風力発電や、太陽光発電の施設をいたるところで見ることができます。太陽光発電のパネルも、かつては日本のものが先進的でしたが、今ではドイツのほうが世界的に大きなシェアを占めています。日本の場合、一時的に力を入れますが、継続して政策を実行できていない場合が多く、そういうところが問題なのではないかと思います。

三木 日本のエネルギー自給率というのは、2005年の統計では原子力を除くとたった4%で、原子力を含めても19%です。先進国の中で非常に低くなっています。
また、エネルギーも全体を見て、8割以上が石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料が中心です。特に石油は、新しい油田が発見されない限り、このままでは、40数年で枯渇するといわれています。
ですから、何か他のエネルギー源でカバーすることが必要です。高地先生の言われる、風力や太陽光発電のほか、地熱、バイオマスなど、分散してエネルギーを取り込むことを考えないといけません。日本の太陽光発電技術は、国際的に非常に進んでいます。今は発電設備容量においてドイツに抜かれていますが、追い抜く努力をしています。
エネルギーの使用は、民生、産業、運輸に分けられます。ただ、産業界は、世の中の動きに非常に敏感なので、いろいろな対策を講じて、それほどエネルギー消費量は増加していません。
それに対し、運輸や民生の分野では、どんどん消費が増えています。消費の面でいうと、一番多いのは民生部門です。理工学部では、自動車関連、特に電気自動車の研究も行っています。環境破壊を食い止める技術として、自動車がガソリンから電気に移行していくのは必然的な流れです。
また、民生分野では、家庭の電化製品で省エネなどの技術開発を進めていくことが、持続可能な社会構造につながると思います。
地球の温暖化は、数年前の予測よりも急激に進んでいます。技術者も、地球規模で技術開発に取り組まなければ、自分たちの首を絞めることになります。人間に便利なものは、多くが環境に影響を及ぼします。それを技術でカバーしていかなければならない。そういう時代になってきているのではないでしょうか。
- 環境を守る技術については、技術移転と特許の問題もあると思います。
高地 環境技術と特許の問題は、逆の対応が必要になると考えます。環境に役立つ技術は開放しなければいけません。それを囲い込むと、地球全体を考えるとマイナスになってしまいます。
また、技術の中身を見ますと、環境そのものに直結する技術と、そうではない技術があります。家庭用の機器についての省エネ技術と、地球全体の環境に関する技術は分けて考える必要があります。生活を便利にする種類の特許は保護していく必要があります。
三木 医学の分野も同様ですが、技術開発には投資も必要ですし、企業の命運もかかっています。特許を取るのも仕方がない側面もあります。しかし、最終的には環境に関する技術は開放するべきでしょう。
高地 技術開発にかかるコストは無視できません。それは回収できるようにしたいですね。
- 持続可能な社会の構築に向けて、どのように取り組むべきでしょうか。
高地 市民レベルの問題と、国全体で取り組む世界的な問題があります。
身近なところでは、廃棄物のリサイクルに代表されるように、国民の意識改革が必要になります。限られた資源を活用するための法整備が必要になるでしょう。さらに、製品づくりの段階で、リサイクルを念頭に入れた開発を奨励しなければいけないと思います。
一方で地球レベルのことを考えた場合、電力の買い取りなど、エネルギーの活用についての整備もしていく必要があります。
三木 法律という点では、今まで以上に技術者倫理が重要になっています。現代社会は、企業の動向にとても敏感です。講義科目として技術者倫理を取り入れている大学が増えています。技術的には、以前にもまして、資源を循環させるシステムが出来上がってきています。水力発電なども見直されてきています。そういう点で、国民の意識も環境に向いてきていると思います。