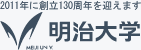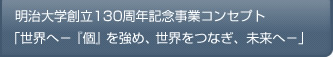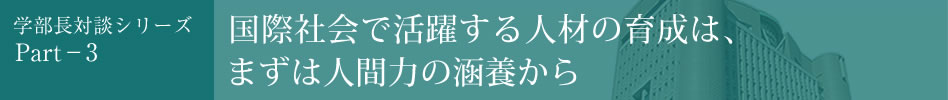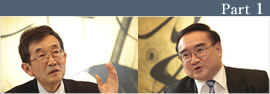社会のグローバル化が進み、国境なき時代が到来している。国際舞台で活躍する人材を育成する機関として、大学に求められる期待は大きい。グローバル社会に求められる人間力とは何か?文学部、経営学部、情報コミュニケーション学部の学部長が鼎談した。
- 国際社会で活躍する人材育成に向け、各学部ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。

小笠原 経営学部は、IBPと呼ばれる学部独自の短期留学プログラムを実施しています。これは、単に語学研修というだけではなく、現地の企業を訪問してインタビューするなど、日本と現地の経営の違いを学ぶ、実地研修の側面もあります。
この研修には、ある程度の英語力が求められますので、経営学部では、能力別に英語のクラス分けを行っています。とにかく、英語を使って議論や話し合いができる土壌を作りたいと思っています。
細野 情報コミュニケーション学部では、来年度からの新しい取り組みとして、タイとの学生交流プログラムを開始します。短期でタイの留学生を受け入れ、こちらからも留学生を送り出していきます。語学ではなく、人との出会いを通して、異文化の理解と体験ができることに重点を置いています。
林 世界の共通語として英語は必須です。まずは、全員同じ教材で大人数教室で授業を行います。さらに、学生の興味に従って、少人数のクラスで学びます。また、TOEIC(R)をはじめとする諸外国語の検定試験に補助金を出して積極的にチャレンジする機会を設けています。また、春、夏の大学主催の語学合宿やカナダなどでの外国語研修への参加を奨励しています。
小笠原 英語を話すだけで、国際人になれたと思うのは大間違いです。真の国際教育は、幅広い角度から行わなければなりません。経営学部では、各国の文化論と、専門の地域別国別の経営論をリンクさせ、全体としての国際教育を行っています。

- 語学を修得すること以外で、国際人にとって必要な能力についてはどのようにお考えでしょうか。
小笠原 まず第一に異文化理解が挙げられます。さらに、自分たちを知るということです。実は、留学して一番困るのは、日本についての質問です。古典芸能や日本料理などについて質問されます。
林 まず、相手のことを知ろうとする好奇心だと思います。相手の懐に飛び込んでいくある種の勇気も必要ではないでしょうか。その大前提として、日本のことを知っていることが大切です。
細野 すべての学生が留学できるわけではないのですが、日本に来た留学生と出会うことも、経験になると思います。
林 明治大学は「個を強くする大学」です。外国で「個」とは、自分の意見を持って、主張することです。語学の能力が足らずに発言できない場合でも、外国では意見なしと判断されます。自分の意見をはっきりと言う姿勢を身につけていくことが、特に日本人の場合は、国際社会で生活や仕事をしていく上では大事だと思います。
小笠原 その通りですね。同時に、寛容心も必要だと思います。日本人には、遠慮、思いやり、譲るといった心があります。国際的な社会で日本人が活躍する場合、異文化に対する寛容が求められると思います。

細野 男女や同郷など、同質な者同士で集まる傾向がありますね。その決まったグループの中で、言わなくても分かり合ってしまうといった、「言わない文化」のようなものが、日本的なコミュニケーションの根っこにあります。これからは、違ったタイプの人たちと話をしてコミュニケーションをとることが必要になると思います。
小笠原 多様性の時代ですから、これから必要なコミュニケーションの心とツールについては、日本全体で考える課題になると思います。
細野 明治初期の文献に「安心」という単語が見られます。最近話題の安心安全ではなく、ものを言うことについての安心という意味です。つまり、今までは意見を言うことを警戒して、言ってはいけないといわれてきたけれど、これからは安心して言っていいんだという意味で使っている。当時から、コミュニケーションそのものが馴染む文化ではないということですね。
小笠原 最近は「以心伝心」と言わなくなりましたが、代わりに若者は「空気を読む」という言葉を使っています。「空気を読むな、言葉を出して自分の意見を言え」と私は言いたいですね。
林 例えば、アメリカは移民から始まった国です。そこでのコミュニケーションはやはり言葉なんですよね。日本人という、同一性が高い国民と違い、言葉を通してのコミュニケーションが非常に大事です。