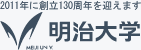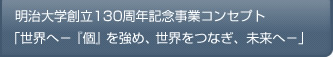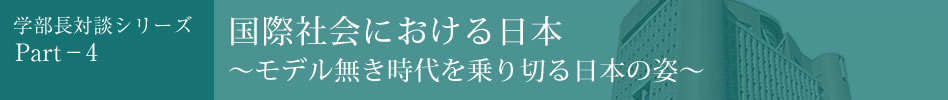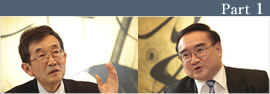社会のグローバル化が進み、世界はいまだかつて経験したことのないボーダレス社会へと変貌した。今は世界に向けた日本の在り方が大きく問われている。その社会を生き抜き、国際社会を先導するために、日本と日本人に求められていることは何なのか。政治経済学部と国際日本学部の学部長が対談した。
- 国際化時代となり、現在はモデル無き時代と言われています。この時代を乗り切るために、今求められていることは何でしょうか。

蟹瀬 国際化というのは、世界が一つの均質的な社会になることではありません。多様なものが共存できる社会、それが国際化の本来あるべき姿だと思います。今はその過渡期です。これから、企業やビジネスの在り方、働く人の考え方も変わります。それによって、我々の生活も変わってくるでしょう。
大六野 その過渡期であることが、モデル無き時代といわれる理由ですね。社会は、はるか昔の物々交換の時代から徐々に発展して、政治と経済の枠組みがほぼ国民国家という単位の中に収まる状況になりました。
その後、二度の世界大戦を通し、自国の国益を求めると国家間の戦争になることを経験しました。そこで、国際連盟や国際連合、IMFやWTOといった国際機関を設立して、国の枠組みで収まりきれない問題に対処する構造を作りました。
以前は、これを国際化と呼んでいた訳です。それが今ではボーダレス化が進み、お金、物、サービス、情報が国境を越えて動くようになっています。しかし、政治の決定権は未だに国家にある。そこに矛盾が生じています。これまでの国際化と異なるのは、自分の国に起こっていることなのに、国内で解決できなくなっているところです。しかも国際機関でもコントロールできない。

蟹瀬 個人の力が大切になってきている時代とも言えます。輝ける人材をどれだけ輩出できるかが、今の国際社会では求められています。かつてニューヨークの作家に「日本の商品は輝いているが、輝く日本人にあったことがない」と言われ、ショックを受けたことがあります。そんなことはないのですが、日本人の発信力の弱さを痛感しました。日本の顔となる、輝ける人材を輩出していくことが、日本の競争力を高めることにもつながるのだと思います。
- 人材育成についてですが、最近の若者は、政治や経済をよく知らないという話も聞きます。
大六野 彼らは日本がある程度経済的な発展を遂げた後で生まれた世代です。また、最近の不景気の時代に成長していることもあり、特にほしいものもなく、何をしても無駄だという意識の若者は多いかもしれません。
ちょっと前までは、裸電球が蛍光灯に変わり、テレビが家に来るなど、経済発展と日常生活の経験が実感として一致している面がありました。今は政治や経済のような難しいことではなく、自分の関心がある身近なことに集中するようになってきていると思います。
蟹瀬 情報化社会の到来で、日本だけではなく、世界的に若者の関心の幅が狭くなる傾向があります。今はインターネットもあり、一人ひとりが百科事典あるいは図書館を手のひらに持ち、キーワード一つで知識は手に入る時代になりました。その中で、教育も時代とともに変わっています。かつては、読み(Read)、書き(Write)、計算(Arithmetic)という、3つのRが非常に重視されていました。記憶や知識の蓄積に重点がおかれていたわけです。しかし、これからの教育は、問題を探求する力(Explore)、それを表現する力(Express)、そして得た知識を共有する力(Exchange)の3つのXだといわれています。日本の教育は、まだどちらかと言えば3R型の教育です。これは若者にとっては大変不幸なことだと思います。さらに、日本の先行きを考えたとき、時代が要求している人材が育たないという問題を引き起こしているわけです。
- 両学部とも英語の教育には力を入れていますね。
蟹瀬 世界で何か表現するには、やはり英語が必要です。英語ができないために、国際舞台で活躍できない悔しい思いをしている人はたくさんいます。
大六野 学部の成り立ちは違いますが、政治経済学部でも同じように、世界に出るための道具としての英語の能力を重視しています。そのため、留学にも力を入れています。教育の一つの方法として、海外に出て外から自分の国を見ることも必要だと思います。