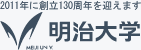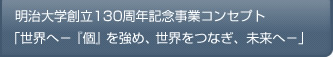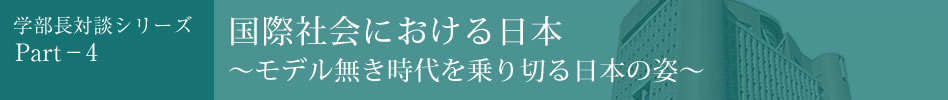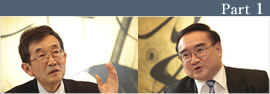社会のグローバル化が進み、世界はいまだかつて経験したことのないボーダレス社会へと変貌した。今は世界に向けた日本の在り方が大きく問われている。その社会を生き抜き、国際社会を先導するために、日本と日本人に求められていることは何なのか。政治経済学部と国際日本学部の学部長が対談した。
- 海外留学に関しては、最近は尻込みする学生も多いと聞きます。
大六野 日本の中で生きていると、留学の必要性を感じないかもしれません。しかし、必要性を感じないことと、本人が伸びるために行動することは別です。海外で学ぶこともあるし、実は逆に日本を学ぶこともあります。
これからの社会では、活躍する舞台が日本である必要はありません。チャンスがあれば、世界のどこにでも行くという気になるかどうかです。
蟹瀬 日本の学生は、欧米と比較すると、海外志向が弱いですね。しかし、日本の学生も潜在的に海外に対する好奇心は持っています。これをどうやって引き出すかが、教育機関だけではなく、日本社会全体の責務だと思います。
大六野 そうですね。我々の仕事は、もちろん知識を与えることです。しかし、新しい世界への視野を開き、気づかせることも大切だと思います。
蟹瀬 学生が世界の知識を共有するグローバルな教育環境も、これから生まれてくると思います。
- グローバル化で教育に関しても垣根がなくなると言うことですね。
大六野 実際に今の学生は、学内ではあらゆる学部で講義を受けることができます。学問の領域も、それぞれの特色は当然残りますが、周辺部分の垣根はなくなるでしょう。
蟹瀬 学際的という言葉が生まれて、数十年が経ちました。それが大学で具体化し、学生が学びたいものを学べる機会を提供しています。
- その一方で、日本語のコミュニケーション能力が低下している学生たちも増えてきていますね。
大六野 確かに、言いたいことを言わないし、言う努力や工夫をしない学生は増えています。
蟹瀬 逆に、その能力をつける場が必要ということです。テクノロジーの発達とともに、目と目を合わせて会話する機会が少なくなっています。
大六野 個人を独立した存在とみなし、それを契約で結びつける西洋式の社会観に限界が出ているのかもしれません。理想化してはいけませんが、今の日本人が忘れかけている家族や村落といった中での共生感覚の中に、これからのコミュニケーションのヒントがあるのかもしれません。
- 世界に通用する人材を輩出するための、それぞれの学部の人材育成についてお聞かせください。
大六野 政治というのは、多くの大学では法学部の中で学びます。しかし、政治と経済は密接に絡んでいます。この2つを現実的に考えていくのが政治経済学部の特徴です。
政治や経済の歴史は、グローバル化の歴史でもあります。異なる文化やその立場に立った考え方を、相手の立場に立って理解することが必要です。日本が生き残るために、そういう能力を持った人材を育成しています。
蟹瀬 国際日本学部は、明治大学で9番目にできた、一番新しいユニークなコンセプトの学部です。世界で尊敬される人に共通するのは、自国の悪口を言わないことです。自国の文化を大切にする人は、国際社会では高く評価されます。若者に日本の文化・社会システムなど多様な価値を知ってもらい、海外に発信できる人材を輩出していきたいと考えています。
- 政治経済学部
- 1904(明治37)年に設立された政治経済学部は、政治学科、経済学科、地域行政学科の3学科を擁する、100年以上の歴史ある学部だ。
現在そして未来を読み解く上で、人間社会の基礎となっている政治と経済は切り離すことはできない。 「政治を解せずして経済を分からず、経済を分からずして政治を解せず」を設立当初からの理念とし、4,000名以上の学生が現代社会の問題に正面から取り組んでいる。
国際化が進む現代の政治経済を分析する上で、英語の能力は欠かすことができない。通常の英語授業とは別に学部独自の「英語実践力特別強化プログラム」(ACE)を通して、資格や就職、留学に通用する実践的な英語のコミュニケーション能力を身につけるカリキュラムも実施している。留学にも力を入れており、学部独自の留学促進プログラムで、国際的な視野を持った人材の育成を目指している。
- 国際日本学部
- 国際教養を身につけ、積極的に世界に向けて情報発信できる能力を持った人材の育成を目指して、2008(平成20)年に設立された、明治大学でもっとも新しい学部だ。かつてオランダ人画家のゴッホは「日本の芸術を研究すれば、誰でももっと陽気にもっと幸福にならずにはいられないはずだ」と日本文化に驚嘆した。近年、世界の注目を再び集めている日本の文化や社会、その背景となる伝統や思想の教育研究を行っているのが国際日本学部だ。
日本を知り、世界を知る真に国際社会で活躍できる人材の育成を目指している。2年次前期まで集中的に英語教育を行い、コミュニケーション手段としての英語能力を徹底的に鍛えている。3年次からはコース制を取り、さまざまな角度から日本を研究する。
まだ、卒業生は出ていないが、将来は、コンテンツ産業、マスコミ、旅行・交通業、外資系企業、国際機関などの業種での活躍を想定している。