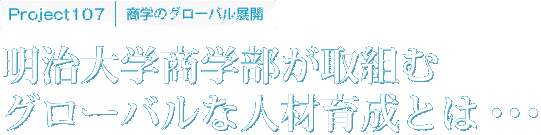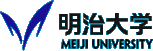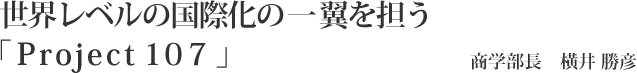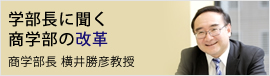商学部長 横井 勝彦
ひと昔前は、大学に求められる国際化といえば「語学力を高める」「留学支援をする」といったことが一般的でした。しかし現在、世界が求める“大学の国際化”は、もはやそんなレベルではなくなってきており、「国境を越えて自由に学ぶ」という状況になりつつあります。たとえばヨーロッパではEU内における学生の流動化を促進する「エラスムス計画」が以前より始まっていて、EU経済圏の中であれば、どこの大学でも自由に授業を受けることができます。もちろん一定のレベルの大学に限られてはいますが、1年生はパリで、2年生はベルリンで、3年生ではウィーンでといったように自由に勉強ができる、こういう世界がすでにヨーロッパにはあるのです。
こうした背景もあり、現在はアジア圏でも「キャンパス・アジア構想」がスタートしています。これは日本と中国、韓国の間で学生が大学間を自由に行き来できる仕組みになっているのですが、残念ながら中国や韓国から10人の学生が日本に来るとすると、日本から中国や韓国に行く学生は1人だけ。ちなみに中国と韓国では10対10で学生が交流しています。理由のひとつとして語学力の差が挙げられるでしょう。中国や韓国はいま、すごい勢いで英語での授業が増えていますから。しかし、こうした状況を大学側がただ見ているわけにはいきません。このままでは日本は完全に乗り遅れてしまうことに、もっと危機感を持つ必要があります。
こうした世界全体の流れを踏まえたうえで、世界レベルの国際化の一翼を担うべく、私たち明治大学商学部がグローバル展開のひとつとして、このたび形にしたのが「Project107商学のグローバル展開」です。2005年の101から一貫してグローバル展開は意識していたのですが、今回の107はとくにそこに焦点をあてたものとなっています。
これから大学は、学生はもちろん、教員も、国境を越えて自由に行き来する時代に突入していきます。ぜひこの時代に乗り遅れず、むしろこの流れを自分のモノにして、社会で生きていく力をしっかり養ってもらいたい。そう強く願っています。