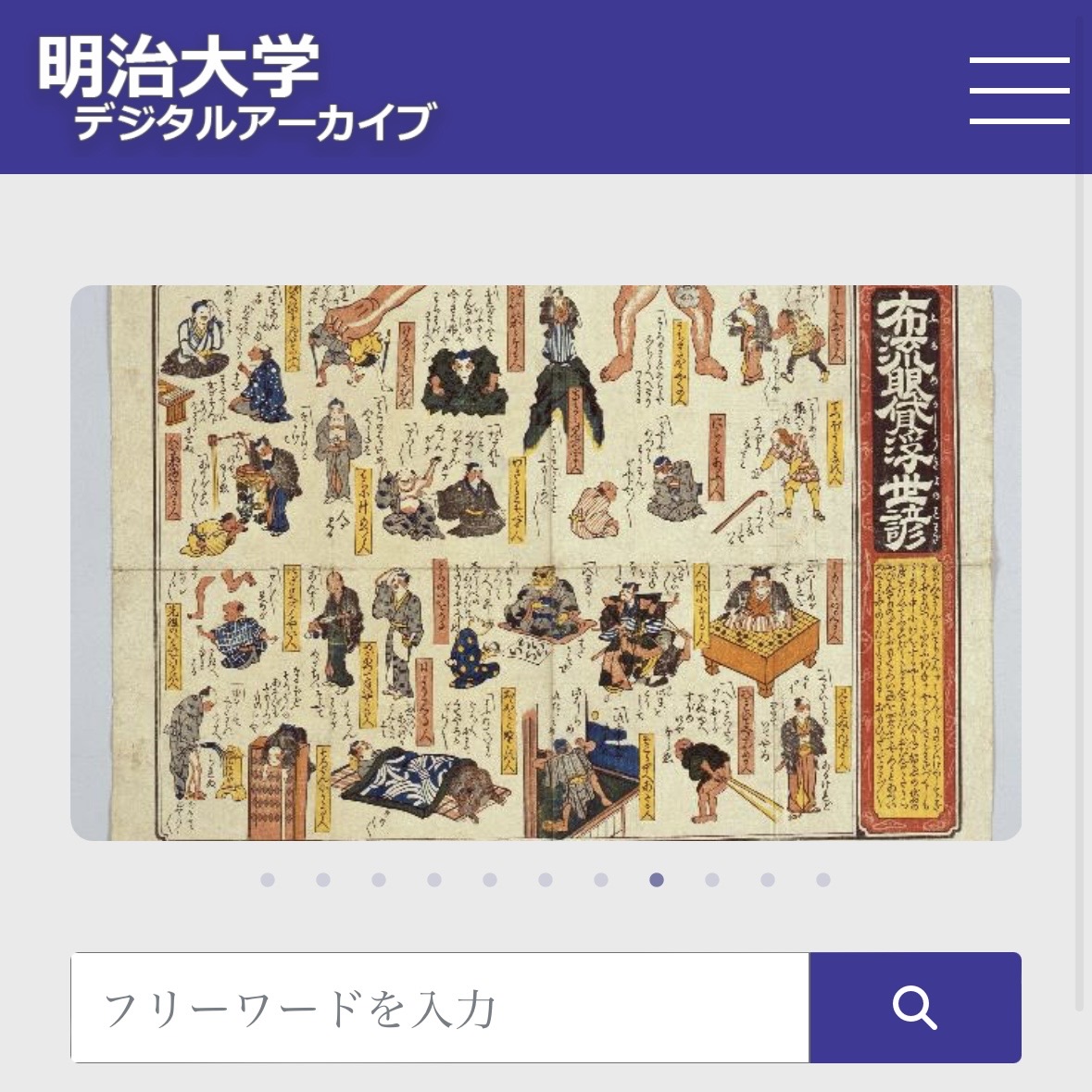2026年02月03日
分科会 古文書の基礎を学ぶ会
当会は、明治大学リバティアカデミー講座「今日から始める古文書講座」の終了者が中心となり発足しました。その時の学習方法を踏襲し、事前に配布されたテキストを各自が読み解き、月1回の例会では、順番に2~3行ずつ発表して、出席者全員で検討して確認しています。発表の際は、勿論判らない字がありますので、それは判らないということで、皆さんと検討していきます。
検討の際は、その古文書が書かれた時の、時代背景や書かれた環境などを含めて話し合い、理解を深めております。進行はかなりゆっくりと進めております。
途中新規に加入された方は、辞書の引き方など、先輩会員の助言を受けながら学習を進めています。新しく入った人は発表を免除され、ある程度判るようになった時点で、本人の申告制で発表に加わります。
現在当会は、「壱」(毎月第一月曜日)、「弐」(毎月第三火曜日)の二部制で活動をしています。
参加は「壱」または「弐」及び「壱」、「弐」両方の参加ができます。新規入会は常時受け付けております。
【最近のテキスト】
「壱」:「瀧脇信敏家記」(駿州小嶋藩藩主⇒上総桜井藩藩主)
「弐」:「紀伊国屋長三郎」道中記(神田塗師町の豪商)
例会
古文書の基礎を学ぶ会「壱」:毎月第一月曜日 13時30分~15時30分
古文書の基礎を学ぶ会「弐」:毎月第三火曜日 13時30分~15時30分
場所
博物館教室 (年会費:1,200円)
顧問
日比 佳代子 明治大学博物館学芸員
- お問い合わせ先
-
明治大学博物館友の会
分科会へ入会希望の方、見学を希望される方は、希望される分科会名と入会希望または見学希望とご記入のうえ、下記へはがきまたはメールでご連絡下さい。
ご希望された方には各分科会よりご案内します。
(現在、募集を行っていない分科会もあります。)
※分科会に正式に入会された方は、明治大学博物館友の会に入会していただきます。(必須条件)
【はがき】
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
明治大学博物館友の会
【メール】
meihakutomonokaig★gmail.com
(上記アドレス中、★を@に置き換えてご利用ください。)