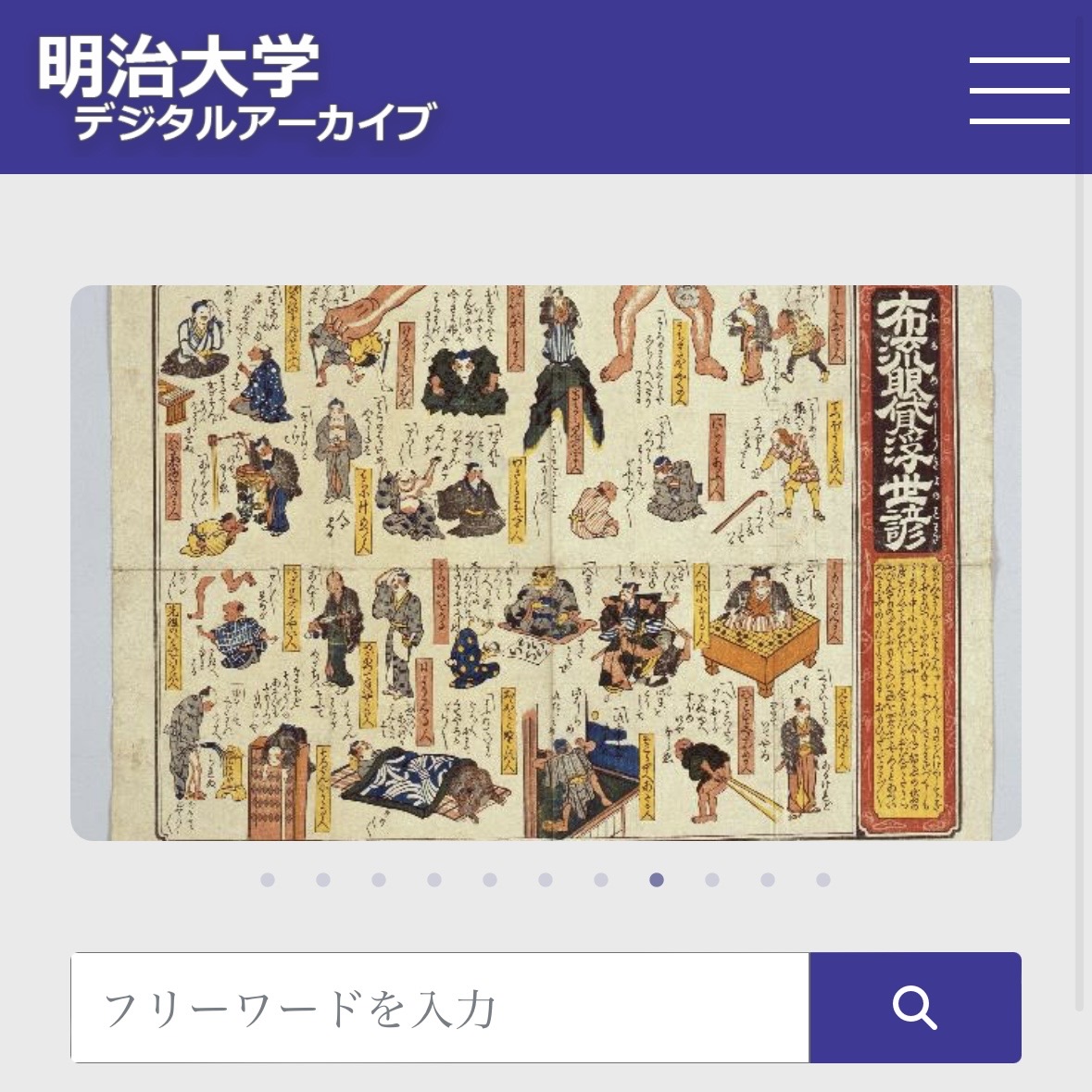明治大学博物館 公式Facebook
科学研究費補助金基盤研究(C)
「黒耀石利用のパイオニア期と日本列島人類文化の起源に関する研究」
研究期間2008年度~2010年度
研究代表者:島田和高
「黒耀石利用のパイオニア期と日本列島人類文化の起源に関する研究」
研究期間2008年度~2010年度
所属機関・職:明治大学 文学部 講師
研究計画の概要
本研究テーマは,日本列島において考古学的に確認できる,旧石器時代最古の黒耀石利用の実態を明らかにすることをとおして,日本列島人類文化の成立過程に関する,考古学的調査の進展に応じて検証可能なモデルの構築を目的としている。
研究プログラムではまず,中部日本で最古段階(南関東立川ロームⅩ層段階)の石器文化に認められる黒耀石利用の初源的な様相から,これに続く(同Ⅸ層段階)黒耀石管理体制が確立した様相への変化を,日本列島における黒耀石利用のパイオニア期と位置づけたい。そしてこの時期,山岳部と外洋部で行われた黒耀石原産地探索のプロセスを,原産地と消費地である平野部の間に広がっていたと考えられる,異なる環境にまたがって実施された網羅的な生存環境の探索行動と関連付けてモデル化する。その上で,黒耀石利用のはじまりは,移住により新天地を開発する現代型新人に特有の行動様式の一環としてあらわれた,その結果であるとする仮説を提示したい。
なお,「黒耀石利用のパイオニア期」とは,現状で,当該時期を遡り,かつ考古学的に繰り返される黒耀石利用の物的証拠が存在しないことを指す,申請者の造語である。
研究プログラムではまず,中部日本で最古段階(南関東立川ロームⅩ層段階)の石器文化に認められる黒耀石利用の初源的な様相から,これに続く(同Ⅸ層段階)黒耀石管理体制が確立した様相への変化を,日本列島における黒耀石利用のパイオニア期と位置づけたい。そしてこの時期,山岳部と外洋部で行われた黒耀石原産地探索のプロセスを,原産地と消費地である平野部の間に広がっていたと考えられる,異なる環境にまたがって実施された網羅的な生存環境の探索行動と関連付けてモデル化する。その上で,黒耀石利用のはじまりは,移住により新天地を開発する現代型新人に特有の行動様式の一環としてあらわれた,その結果であるとする仮説を提示したい。
なお,「黒耀石利用のパイオニア期」とは,現状で,当該時期を遡り,かつ考古学的に繰り返される黒耀石利用の物的証拠が存在しないことを指す,申請者の造語である。
学術的背景と本研究の目的
日本列島最古の人類文化すなわち旧石器時代の成立には,大きく二つの説がある。一つは,「中期/後期旧石器時代移行説」であり,一方は,「南方渡来起源説」ということができる。いずれも,南関東地方においては,立川ローム最下底部(Ⅹ層段階)から出土する石器群が,当該地における最古の人類痕跡であることでは,認識が共通している。
前者は,立川ローム最下底部の石器文化を移行期と理解し,これを年代的に遡ると考えられている列島各地の石器文化との技術的な系統関係を認め,「中期旧石器時代」を設定することに特色がある。ただし,「中期旧石器時代」相当の石器文化のすべてについて,その年代あるいは石器認定などの点で学界全体が合意に達しているわけではない。 また後者は,形質人類学の「スンダランド起源仮説」に依拠している。同説の特色は,現代型新人が南方的な形質をもちながら日本列島に伝播してきた可能性を下敷きに,東南アジアの「不定形剥片石器」文化が日本列島でどう分布するかを追跡するところにある。
これらの二説は,現状の考古資料からはいずれも成立し,今後の検証を要する仮説として並立する性格のものである。ただ,大きく異なるのは,前者が最後の間氷期に遡るヒトの渡来と後期旧石器時代への連続を唱えるのに対し,後者は後期旧石器時代こそが現代型新人の渡来時期であり,列島人類文化の初源であるとすることである。 しかしながらいずれの仮説でも,①現代型新人に特有とされる行動が,考古資料の中にいつどの時点でどのように認められるのか,また②後期旧石器時代の定義はなにかということが問題となる。ところが現状の「後期旧石器時代」は,2000年に発覚した「前期・中期旧石器時代遺跡捏造事件」以降,そのはじまりと時代の性格にかかわる定義が曖昧なままである。
酸素同位体ステージ3の半ばに位置する当該時期は,現代型新人が旧世界各地に拡散した時代として,そのプロセスが議論されている現在(例えばP.J.Brantinghan他編2004),考古資料をもとに,対立しながらも並立しうる複数の仮説を構築し,かつ海外へ発信することは,日本旧石器学界の急務である。本研究からは,上記①と②の問題にもアプローチすることが可能である。
前者は,立川ローム最下底部の石器文化を移行期と理解し,これを年代的に遡ると考えられている列島各地の石器文化との技術的な系統関係を認め,「中期旧石器時代」を設定することに特色がある。ただし,「中期旧石器時代」相当の石器文化のすべてについて,その年代あるいは石器認定などの点で学界全体が合意に達しているわけではない。 また後者は,形質人類学の「スンダランド起源仮説」に依拠している。同説の特色は,現代型新人が南方的な形質をもちながら日本列島に伝播してきた可能性を下敷きに,東南アジアの「不定形剥片石器」文化が日本列島でどう分布するかを追跡するところにある。
これらの二説は,現状の考古資料からはいずれも成立し,今後の検証を要する仮説として並立する性格のものである。ただ,大きく異なるのは,前者が最後の間氷期に遡るヒトの渡来と後期旧石器時代への連続を唱えるのに対し,後者は後期旧石器時代こそが現代型新人の渡来時期であり,列島人類文化の初源であるとすることである。 しかしながらいずれの仮説でも,①現代型新人に特有とされる行動が,考古資料の中にいつどの時点でどのように認められるのか,また②後期旧石器時代の定義はなにかということが問題となる。ところが現状の「後期旧石器時代」は,2000年に発覚した「前期・中期旧石器時代遺跡捏造事件」以降,そのはじまりと時代の性格にかかわる定義が曖昧なままである。
酸素同位体ステージ3の半ばに位置する当該時期は,現代型新人が旧世界各地に拡散した時代として,そのプロセスが議論されている現在(例えばP.J.Brantinghan他編2004),考古資料をもとに,対立しながらも並立しうる複数の仮説を構築し,かつ海外へ発信することは,日本旧石器学界の急務である。本研究からは,上記①と②の問題にもアプローチすることが可能である。
研究の焦点
本研究が対象とする地域は,南関東,北関東,東海,中部,上越を含む中部日本一帯である。
(1)研究の第1段階では,①黒耀石利用の段階的変化,②黒耀石利用の地域的格差,③黒耀石原産地の開発痕跡についての観察をとおして,黒耀石利用のパイオニア期の考古学的状況を整理する。また,遠隔地石材である黒耀石に対置される各地域の在地石材の利用状況をあわせて整理する。
(2)研究の第2段階で達成すべき課題は,第1段階で得られた考古学的状況をヒトの動きに置き換えることである。第1段階で分析した石器文化資料の黒耀石産地推定分析をとおして,原産地と消費地間における遺跡の連関と黒耀石の管理方法の分析を行う(文献6等の方法を援用)。
(3)研究の第3段階で達成すべき課題は,黒耀石利用にはじまりがあるとすれば,実証的に構築された黒耀石を巡るヒトの動きから,そのプロセスをモデル化することである。いまのところ,遺跡密集地域を中心に,在地石材から地域縁辺の石材へ,さらに遠隔地石材へという同心円状の石材資源開発の広がりがあること,もし黒耀石利用がはじめてであれば,原産地一帯はそれまで未踏査地域であったこと等を根拠に,黒耀石原産地の発見は決してそれ自体が目的ではなく,より網羅的な生存環境の探索の結果であった,とする着想を得ている。
(1)研究の第1段階では,①黒耀石利用の段階的変化,②黒耀石利用の地域的格差,③黒耀石原産地の開発痕跡についての観察をとおして,黒耀石利用のパイオニア期の考古学的状況を整理する。また,遠隔地石材である黒耀石に対置される各地域の在地石材の利用状況をあわせて整理する。
(2)研究の第2段階で達成すべき課題は,第1段階で得られた考古学的状況をヒトの動きに置き換えることである。第1段階で分析した石器文化資料の黒耀石産地推定分析をとおして,原産地と消費地間における遺跡の連関と黒耀石の管理方法の分析を行う(文献6等の方法を援用)。
(3)研究の第3段階で達成すべき課題は,黒耀石利用にはじまりがあるとすれば,実証的に構築された黒耀石を巡るヒトの動きから,そのプロセスをモデル化することである。いまのところ,遺跡密集地域を中心に,在地石材から地域縁辺の石材へ,さらに遠隔地石材へという同心円状の石材資源開発の広がりがあること,もし黒耀石利用がはじめてであれば,原産地一帯はそれまで未踏査地域であったこと等を根拠に,黒耀石原産地の発見は決してそれ自体が目的ではなく,より網羅的な生存環境の探索の結果であった,とする着想を得ている。
研究の特色
(1) 社会還元:2008(平成20)年には,本研究テーマを中核とした特別展「氷河時代の山をひらき海をわたる(仮題)」を明治大学博物館で開催する。また,これと関連する市民講座などをとおして,研究内容の社会還元を促進する。なお,申請者は明治大学博物館の学芸員である。
(2)学界への貢献:本研究テーマは,日本列島人類文化の起源を黒耀石考古学(安蒜政雄2003)の立場から明らかにしようとする点に独創性がある。また,あくまで理論的な予測が主となっている日本列島への現代型新人の拡散問題について,具体的な仮説を国内外に提示できること,そして,「前期・中期旧石器時代遺跡捏造事件」以降,停滞している日本列島人類文化の起源についての議論を活性化させる役割を果たすことができる。考古学分野から同問題を扱う古人類学分野へ,考え方の枠組みあるいは作業仮説を提示することは,学際研究のうえで重要である。
(2)学界への貢献:本研究テーマは,日本列島人類文化の起源を黒耀石考古学(安蒜政雄2003)の立場から明らかにしようとする点に独創性がある。また,あくまで理論的な予測が主となっている日本列島への現代型新人の拡散問題について,具体的な仮説を国内外に提示できること,そして,「前期・中期旧石器時代遺跡捏造事件」以降,停滞している日本列島人類文化の起源についての議論を活性化させる役割を果たすことができる。考古学分野から同問題を扱う古人類学分野へ,考え方の枠組みあるいは作業仮説を提示することは,学際研究のうえで重要である。
2008年度の成果概要
本年度は、既に先行して実施していた当該研究テーマの成果を6月にロシア・アルタイで開催された国際シンポジウムで発表した。その後、日本列島における黒耀石利用の始まりとヒトの動き(特にその進化上の段階)の復元に係わるモデルを検討した。仮説的モデルの骨子は以下の通り。
中部日本に点在する黒耀石原産地と関東平野の消費地との間に、明確なヒトの移動経路が開かれるのは、中部日本に突発的に遺跡が増加する35,000年前と一致しており、標高1,500m~2,000mの山岳部や太平洋上の神津島にある黒耀石をすでに探索・発見・利用している。約30,000年前には、黒耀石を管理・分配する体制が確立し、詳細は課題であるが複雑な交換ネットワークが形成された公算が高い。黒耀石原産地の発見は、未踏の地における網羅的な生存環境の探索に伴う偶発的な事件だったと考えられ、発見の当初は環境情報の一部として利用は発達しないが、石器原料としての優位性が認められるに従い、管理・分配する体制が発達したものと考えられる。環境探索に必要と想定される技術や装備(ただし考古学的には復元困難:航海技術等)、黒耀石管理・交換に見られる高い社会性の存在は、少なくとも中部日本における現代人的行動(Modern Human Behaviors)の登場を示し、先行する十分な地域的広がりを伴う石器文化を日本列島に見出せない状況から、背景に大陸から日本列島に移住した行動的現代人(ホモ・サピエンス)の定着過程を想定することが出来る。
このように、周辺大陸で議論されている、現代人の登場問題に具体的にリンクしうる日本列島側での仮説のアウトラインを本年度は構築することが出来た。
中部日本に点在する黒耀石原産地と関東平野の消費地との間に、明確なヒトの移動経路が開かれるのは、中部日本に突発的に遺跡が増加する35,000年前と一致しており、標高1,500m~2,000mの山岳部や太平洋上の神津島にある黒耀石をすでに探索・発見・利用している。約30,000年前には、黒耀石を管理・分配する体制が確立し、詳細は課題であるが複雑な交換ネットワークが形成された公算が高い。黒耀石原産地の発見は、未踏の地における網羅的な生存環境の探索に伴う偶発的な事件だったと考えられ、発見の当初は環境情報の一部として利用は発達しないが、石器原料としての優位性が認められるに従い、管理・分配する体制が発達したものと考えられる。環境探索に必要と想定される技術や装備(ただし考古学的には復元困難:航海技術等)、黒耀石管理・交換に見られる高い社会性の存在は、少なくとも中部日本における現代人的行動(Modern Human Behaviors)の登場を示し、先行する十分な地域的広がりを伴う石器文化を日本列島に見出せない状況から、背景に大陸から日本列島に移住した行動的現代人(ホモ・サピエンス)の定着過程を想定することが出来る。
このように、周辺大陸で議論されている、現代人の登場問題に具体的にリンクしうる日本列島側での仮説のアウトラインを本年度は構築することが出来た。
当該研究による業績
[論文]
島田和高 2009 「黒耀石利用のパイオニア期と日本列島人類文化の起源」『駿台史学』135 駿台史学会 pp.51-70.
[学会発表]
島田和高 2009 「黒耀石利用のパイオニア期と環状のムラの消滅」『シンポジウム「東アジアへの新人の拡散とOIS3の日本列島」予稿集』 日本第四紀学会
Kazutaka Shimada 2008 Emergence of Modern Human Behaviors and Obsidian Use in the Paleolithic Period of Japan. in The Current Issues of Paleolithic Studies in Asia and Contiguous Regions. Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
[著書]
島田和高 2008 『2009年度明治大学博物館特別展解説図録「氷河時代の山をひらき、海をわたる-日本列島人類文化のパイオニア期-」』 明治大学博物館