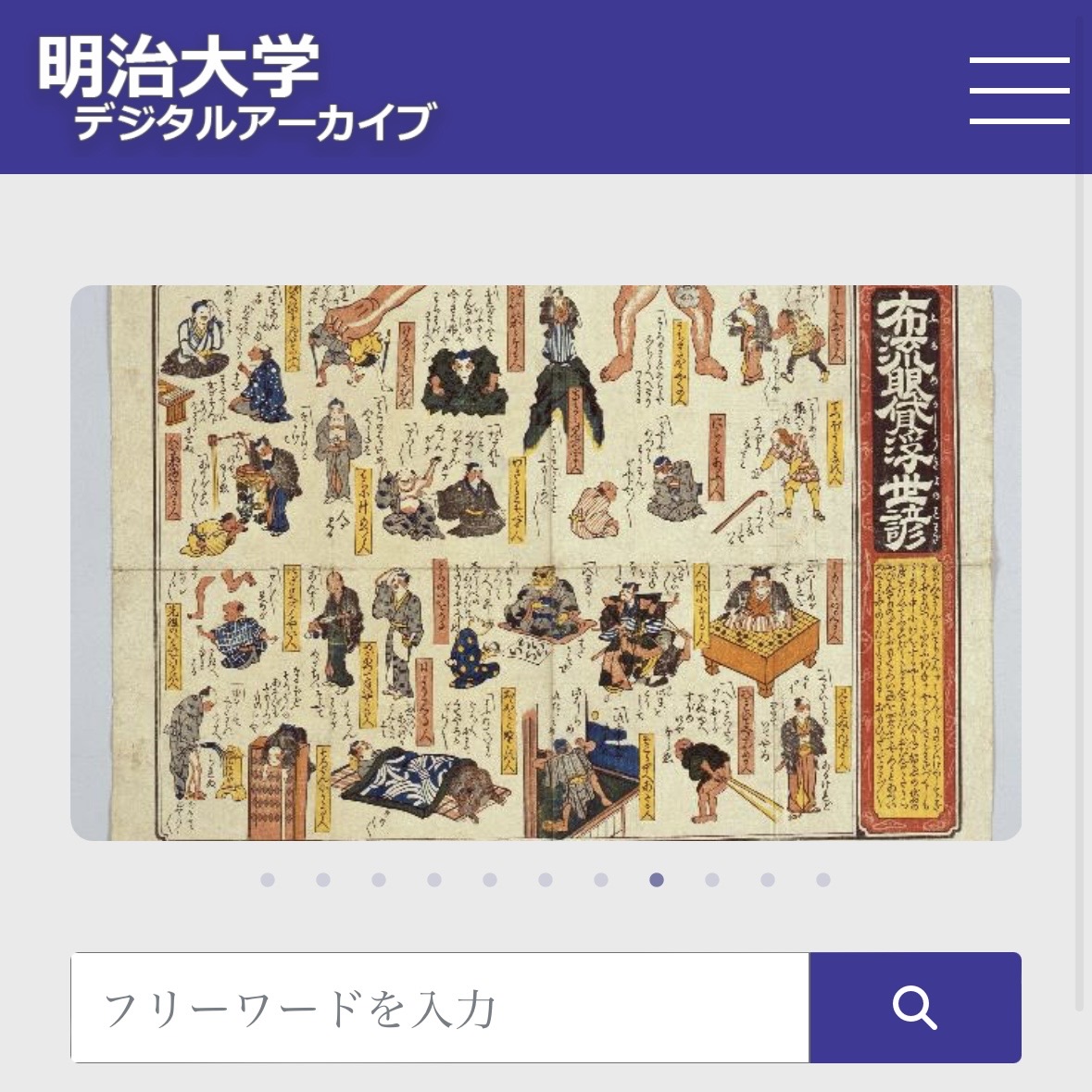2026年02月03日
王の埴輪—玉里舟塚古墳の埴輪群—
|
2010年度明治大学博物館特別展 王の埴輪—玉里舟塚古墳の埴輪群— |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)実施形態
(2)趣旨 茨城県小美玉市に所在する玉里舟塚古墳は、1965年から5次にわたって明治大学考古学専攻の調査団によって発掘調査され、特殊な二重の箱式石棺と大量の埴輪が出土した。埴輪は大型かつ多彩で、関東を代表する埴輪のひとつとして知られている。近年、明治大学博物館が行った再整理の結果、横座り方式の乗馬を示す大型の馬や柱付の家、まわしをしめた力士、特殊な線刻を施した円筒埴輪などの存在が明らかとなり、まさに「王」の埴輪ともいえる豊富な内容をもつことが判ってきた。今回の展示では、明治大学博物館と茨城県立歴史館と小美玉市玉里史料館、古墳の所有者である山内氏宅に分散収蔵されている埴輪群及び伝資料も含めた副葬品等約400点を初めて一堂に集め、霞ヶ浦北岸に君臨した「王」の実像に迫った。 (3)展示構成 (1)玉里舟塚古墳とは 茨城県小美玉市に所在する6世紀前半に位置づけられる玉里舟塚古墳の概要について紹介。1965年から5次にわたった発掘調査の成果とその評価について述べた。 (2)玉里舟塚古墳以前の埴輪 玉里舟塚古墳以前に周辺に築造された大型古墳の埴輪を展示し、玉里舟塚古墳との違いを示した。東日本第2位の規模をもつ巨大前方後円墳の舟塚山古墳の朝顔形円筒埴輪をはじめ、行方市三昧塚古墳、かすみがうら市富士見塚1号墳、小美玉市玉里権現山古墳の円筒埴輪・形象埴輪など比較的小型で稚拙なつくりのものから、玉里舟塚古墳の埴輪が飛躍的に巨大化し技巧的にも高度になることを示した。 (3)玉里舟塚古墳の円筒埴輪 全国的にも珍しい約120~80cmの巨大円筒埴輪24本を中央ステージに配置し、往時の埴輪配列の状況を復元した。墳丘上に見上げるように設置されていた様子を来場者に実感してもらうため、高さ40cm・60cmのステージに2段にわたって並べ、またできるだけ近づいて観察できるよう露出展示とした。玉里舟塚古墳の円筒埴輪の巨大さと高い規格性、そして埴輪を並べることで古墳の外と内を区画する円筒埴輪の性格を実感できるよう工夫した。 (4)玉里舟塚古墳の形象埴輪 武人・女子・家・馬を中心とする大型の形象埴輪群について、茨城県立歴史館他蔵品と、明治大学博物館で今回復元したものをあわせて陳列した。これまで知られていなかった馬形埴輪や力士の埴輪、そして高床式の家形埴輪など、関東でも屈指の規模を持つ形象埴輪群であることが明らかとなった。また、あわせて形象埴輪列の配列復元を行った結果、継体大王の墓と目される大阪府今城塚古墳との共通性がうかがわれ、近畿の中央政権とのつながりをもつことが判明し、埴輪研究のうえで重要な資料を提供することとなった。 (5)埋葬施設と副葬品 1960年代に明治大学が調査した折に出土した資料と、茨城県立歴史館所蔵の伝玉里舟塚古墳出土の資料をあわせて展示し、金銅装の大刀をはじめとした膨大な鉄製武器類、またガラスや青銅製の装飾品類など数々の豪華な副葬品と復元レプリカから被葬者像を推定した。特殊な構造で知られる後円部の埋葬施設をほぼ実物大のタペストリーにしてケース背面に展示し、円筒埴輪列の奥に埋葬施設がある位置関係を想起できるような配置とした。 (6)その他 古墳の地主である山内氏宅に保管されていた調査の様子をまとめたアルバム(大塚初重名誉教授が調査時に作成)の複写のほか、調査時のスナップをまとめたスライドを上映し、当時の調査の雰囲気と出土状況を理解する一助とした。 (4)展示資料数 借用機関・個人;7個所 出展資料;401点(内借用285点、茨城県指定文化財8点、水戸市指定文化財2点) (5)関連事業 1 連続公開講座
2 学芸員によるギャラリートーク (1)10月17日(日)14:00~14:30 (2)11月3日(水・祝)11:00~11:30 (3)12月4日(土)15:00~15:30 3 文化の日子ども講座「はにわって何だろう?」 実際の埴輪の洗浄体験などを通して埴輪とは何かを学ぶ。 日時:2010年11月3日(水・祝)14:00~15:30 参加費:無料 対象:小学校3年生~6年生(原則保護者と児童のペア) 定員:8組 参加者数:3家族8名 

|
||||||||||||||||||||||||||||