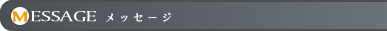 |
|
| 第7回 (2005.8.2) |
| 孫 楊 さん (中国南京財経大学金融学院 副教授) |
1996年 商学部 商学科 卒業
2001年 大学院 商学研究科 博士後期課程修了 |
|
 私は明治大学商学部卒業後、さらに同大学院商学研究科に進学しました。商学博士号取得まで、通算9年間、母校、とりわけ商学部の教職員の方々に大変お世話になりました。
私は明治大学商学部卒業後、さらに同大学院商学研究科に進学しました。商学博士号取得まで、通算9年間、母校、とりわけ商学部の教職員の方々に大変お世話になりました。
実は私の場合、義理の叔父が明大卒業生のため、明治大学のことは日本へ行く前からすでに知っていました。私が入学した1992年当時は、中国大陸からの留学生がまだ少なく、韓国や台湾からの留学生が比較的に多かったので、しばらくの間、寂しい思いをした記憶があります。ただ、生活や勉学の面で大学が色々と相談にのってくれたため、比較的に短い期間で大学生活に慣れることができました。
在学9年間、時代の変化に沿ったカリキュラムの充実や駿河台校舎の整備など、母校の著しい飛躍を体験することができました。去年5月14日、現在勤め先の大学の副学長や金融学部長を含む教授団に伴い、母校明治大学を表敬訪問し、学長の納谷先生をはじめ、諸先生から暖かいもてなしを頂きました。その時は、いわば里帰りのようで感無量でした。
|
 現在、母国の大学で教えている傍ら、時々明大との比較をしています。この比較で、自主性の尊重やゼミ教育への重視など、明大の優れたところを再認識できました。特に、ゼミ教育は日本の大学のなかでも明大商学部がいち早く導入した制度で、中国の大学にないものです。私の場合、ゼミ履修の最大の収穫は、北島忠男先生から学問だけでなく、豊かな人間性も学ぶことができ、一生の糧になったことです。
現在、母国の大学で教えている傍ら、時々明大との比較をしています。この比較で、自主性の尊重やゼミ教育への重視など、明大の優れたところを再認識できました。特に、ゼミ教育は日本の大学のなかでも明大商学部がいち早く導入した制度で、中国の大学にないものです。私の場合、ゼミ履修の最大の収穫は、北島忠男先生から学問だけでなく、豊かな人間性も学ぶことができ、一生の糧になったことです。
現在、中国では、大学進学率が大幅に増加しており、多くの大学が以前の英才教育から大衆教育への転換を余儀なくされています。その過程において問題とされるのは、「規模の経済」の反面、いわゆるマンモス授業の弊害です。多くの学生は一辺倒の授業を聞き流し、自主的に勉強をするというインセンティブに欠けています。それから、以前は教員と親密な関係があったものの、それが段々と希薄になっているほか、同級生同士、また上級生および下級生との繋がりもなくなり、いわば個々の学生はキャンパスのなかで孤独の存在となっています。以上の問題の解決策として、ゼミ教育制度の導入が挙げられます。
|
 昨年から、私はゼミ教育制度を中国の大学にも導入する研究および実験をしております。幸い、地方政府の教育管理官庁および勤務する大学から研究資金などの支援を得たほか、学生達からも好評を受けています。
昨年から、私はゼミ教育制度を中国の大学にも導入する研究および実験をしております。幸い、地方政府の教育管理官庁および勤務する大学から研究資金などの支援を得たほか、学生達からも好評を受けています。
この激動する社会において、後輩の皆さんには、ぜひ「個を強くする」信念を持ち、そして何よりもアンテナを高くし、グローバル社会の多様な価値観を理解・包容できる人間に成長してもらいたいと思います。
|
|