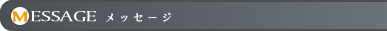 |
|
| ��P�S�� �i2006.3.28�j |
| �ԕ� �� ���� �i������Еx�m�L���������@������j |
| 1975�N ���w�� ���w�� ���� |
|
 �@1971�N4���A���̖�����w�����̓X�^�[�g���܂����B��Ɖ�v���w�т����Ə��w���i�w���܂������A�����ŐV���Ȕ����ɑ������܂��B�u�}�[�P�e�B���O�v�Ƃ��������Ȃ�Ȃ��J�^�J�i�p�ꂪ�u������u�`���ɂ����p����Ă������Ƃł����B
�����̓}�[�P�e�B���O���_���悤�₭���{�ɒ蒅���n�߂������ł�����A�������g�����m�ȈӖ����������o���ʂ܂܁A�����Љ�ۂ�Y�Ƃ�o�ς̎��ۂ��A���̂܂܋��ނɂȂ��Ă��邱�Ƃɕ���̐V�N���ƁA�D��S��傫���h���Ԃ��܂����B
�@1971�N4���A���̖�����w�����̓X�^�[�g���܂����B��Ɖ�v���w�т����Ə��w���i�w���܂������A�����ŐV���Ȕ����ɑ������܂��B�u�}�[�P�e�B���O�v�Ƃ��������Ȃ�Ȃ��J�^�J�i�p�ꂪ�u������u�`���ɂ����p����Ă������Ƃł����B
�����̓}�[�P�e�B���O���_���悤�₭���{�ɒ蒅���n�߂������ł�����A�������g�����m�ȈӖ����������o���ʂ܂܁A�����Љ�ۂ�Y�Ƃ�o�ς̎��ۂ��A���̂܂܋��ނɂȂ��Ă��邱�Ƃɕ���̐V�N���ƁA�D��S��傫���h���Ԃ��܂����B
�@�_�C�G�[vs���F�X�g�A�̏o�X�������A���ʊv����������}�[�P�e�B���O�̎��H��ƂȂ��Ă������Ƃ�A�}�N�h�i���h�̓��{�i�o���t�@�[�X�g�t�[�h�`�F�[���r�W�l�X���t���������Ă��邱�ƁA�Z�u���C���u���̃m�E�n�E�����{�ɂ������ꓱ������Ă��铙�����[�����e�̍u�`�𐔑�����u�ł������Ƃ́A���̌�̎��̎d���ɑ傫���e����^������̂ł����B
�@�܂��A���w�����N��8���ɂ́A�Y������Ȃ��u�j�N�\���V���b�N�v�������܂����B���ƃh��������~�Ȃǂ���e�Ƃ���č��̐V�o�ϐ���ɂ�萢�E�o�ς��[���ȏՌ����������������A���{�ɂ����Ă͂P����360�~�̈בŒ葊�ꐧ���ϓ����ꐧ�ֈڍs���A�~������C�ɉ�����300�~��ɒB����ł����B����̎��Ƃ��n�܂�ƁA�����ǂ̐搶�����ϓ����ꐧ�̌��߂��u�`�ʼn�����Ă�������A���w���̖ڎw�����e���A�@���Ɍo�ώЉ�ɒ������Ă��邩�������F�������o�����ł�����܂����B
�@�������Ȃ���A�݊w4�N�Ԃ̂���2�N�����т�4�N���́A�w��l�グ���Ő�����������w�����b�N�A�E�g�[�u���Ƃ��A���������͂���������|�[�g��o�ɂȂ菭�X�s���S�R�Ă̎v�����c���Ă̑��ƂƂȂ�܂����B
�@���ƌ�͉��̂�����A���݂̋Ζ���ł���s�꒲����ЂɏA�E���܂������A���Ђ͏�����̕��͂Ƃ�������ʒ��������A�R���T���ɋ߂���Ɛ헪�����Ȃǂ̋ƊE���������ӂƂ���������Ђł��������߁A�w������̍u�`���e�̎���ɐ������G��邱�Ƃ��o���A����̎d���ւْ̋����ɑ傫�����т��܂����B
�@���݂́A�C���^�[�l�b�g�𒆐S�Ƃ����ʐM�l�b�g���[�N�֘A����̒�������̐ӔC�҂����Ă���A�h�b�O�C���[�ƌĂ��i���̑����ƊE�̓�����ǂ������Ă��閈���ł����A�ω��̌���������ł����Ă������Ɏ��g�ފ�{�p���͕ς��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���g�ނׂ��ۑ�ɑ��A�����ȁu�z���́v�Ɓu����́v�����g�ɂ��Ă���A���Ƃ͉��p�����ł��B�݊w���ɁA���̗͂���������Ɛg�ɂ��A�Љ�ɑ傫���v���ł���l�ނƂ��Đ�����������p�����厖�ł��B
�@�Ƃ�����A�s���S�R�Ă̑z���̂܂ܑ��Ƃ��Ė�30�]�N���o�߂��܂������A�ߔN�A�V���ȑ�w�Ƃ̐ړ_�������n�߂܂����B����͑��q��3�N�O�ɏ��w���ɓ��w�������Ƃł��B��͂�Ƒ��ɍ݊w�������邱�Ƃő�w����̏��ϑ��������Ă���悤�ɂȂ�܂����B
�@���N����͎��͂̕��X�̋������U��������A�u�����v�̒n����������������Ă��������A��w�����Ƃ����V���ȃR�~���j�P�[�V�����̏��z���܂������A�܂��A�V���ƂȂ����A�J�f�~�[�R�����ɐ݂����Ă���u���o�e�B�E�A�J�f�~�[�v�̃r�W�l�X�v���O���������x����u���A�ŐV�̃}�[�P�e�B���O���_���z������@�����A�V���Ȗ�����w�̊��p���@�����\���Ă��܂��B
|
|