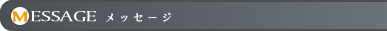 |
|
| ��Q�R�� �i2008.1.12�j |
| ��� �a�v ���� �i������w���o�e�B�E�A�J�f�~�[����j |
| 1964�N ���w�� ���w�� ���� |
|
 �b���
�b���
�@��A �@�w������̎v���o
�@�u�Ό��l��҂����v�Ƃ͂悭���������̂ŁA���吶�������l�N�Ԃ́A�����I�߂����O�̂��ƂɂȂ��Ă��܂����B�R���A���̂��t����̎c���͂܂�ō���̏o�����̂悤�ȑN�����������đh���Ă���B
�@���a�O�\�ܔN�t�̓����Z��w�싅�ŁA����D���I�I�g���߂Ă������͗D���̂����������Ԃ̎��������A���F�B�̗v�]���A��ܒS�������̂��Ƃɕ����A�����̂��߂��ꂩ��_�{����ɂ����������̂ŁA���ЂƂ��x�u�̎��v�����肢�����|�\����A�������B�D�������A��̐V�h�̕��꒬�ł̑�j����A����A�瓔�������Ă̗D���p���[�h�E�E�E
�@���a�O�\�ܔN�́A������Z�\�N���ۂ̎���ł������B���ۓ����́A�����ȍ~�̓��{�̗��j���O�̑�O�^���ƂȂ�A������ӂł͘A���u���۔��I�݂�|���I�v�̃V���v���q�R�[���������܂��A�Z���\�ܓ��ɂ͑S�w�A�嗬�h������\���ɓ˓��A�x�@���@�����ƌ��˂���Ȃ��A���吶�̊��ؒq�q���S�Ɏ������B��ʊw���ł�������������A����̍���\���ɗ������Ă����B�܂�Ŋv���O��̂悤�ȗl����悵�Ă������Ƃ��v���o���B
��A �@�Ǐ��̊���
�@�w���̓Ǐ����ꂪ�i��ł���Ƃ悭�����B
�@���͏��w���Ɋw�сA�T�����[�}���Ƃ��ĘZ�\�̒�N�܂ʼn߂����B����Ύ��w�Ɋւ�鎞�Ԃ�����������ł��邪�A���ۂɂ͖𗧂Ȃ��w�Ƃ��ċ��w�Ə̂���镶�w�A�v�z�E�N�w�A���j���D���ŁA�w�����ォ�炻���Ɋւ���{�������Ȃ�ɑ����Ƃ��ǂ�ł����B���̂��߁A�Z�\���疾�僊�o�e�B�E�A�J�f�~�[�̌��J�u������u���Ă��邪�A�u�w��ɏI��Ȃ��v�Ƃ̎v���������A�Ǐ��ɂ��S�L���Ȏ��Ԃ��߂��������Ɏ����̎��Ɗ����Ă���B
�@�t�H�ɕx�ގႫ�w�����N�ɂ́A���Ћ��Ǐ��̏K����g�ɕt����悤�肤���̂ł���A�Ǐ��̗L�Ӌ`���ɂ��A���|�]�_�Ɖ��쌒�j���̈ꕶ���Q�l�܂łɍ��L���Ă��������B
�@�u�Ǐ��͌����̎����ȊO�̐l���̒Ǒ̌��ł���B�Ǐ��ɂ���Đl�͌���ꂽ�����̐l���̓�{�A�O�{�̉ˋ�̐l�����邱�Ƃ��ł���B�����̐l���ł͒m�肦�Ȃ����̂�m��A�̌��ł���B���̂��Ƃ������Ǐ��̉��l�ł���B����͓Ǐ��̍Œ��ɂ����̌�������B����{��ǂ��Ƃɂ���āA���̐l�̐l��������I�ɕς���Ă��܂����Ƃ�����B�v
|
|