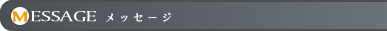 |
|
| 第30回 (2008.10.13) |
| 水澤 一廣 さん(北海道 浦幌町長) |
| 1972年 商学部 商学科 卒業 |
|
 私が明治大学商学部商学科に入学したのは1968年の年でした。
私が明治大学商学部商学科に入学したのは1968年の年でした。
ベトナム戦争の時代であり、国内では東大闘争で安田講堂が占拠される、使途不明金に端を発した日大闘争が燃え上がる、10月には国際反戦デーで新宿騒乱が勃発して騒乱罪が適用されるなど「70年安保粉砕」に向けて学生運動が各大学に飛び火し、全学連闘争が全国の大学で大きな炎となっていた時期で、明治大学も学生闘争の嵐が吹き荒れ、バリケード封鎖、ロックアウトと続き授業を落ち着いて受けるような状況にはありませんでした。
その中で、私は合気道部に入部しましたが、まだ同好会で道場は和泉校舎の体育館にあり、体育会への昇格の為には厳しい稽古が必要不可欠との旗印の下でほかのクラブ以上の厳しい稽古が続けられていましたので、学生集会は遠い世界のことでした。
入部当時は30名近くいた1年生も夏合宿が始まる頃には12名となり、この12名は先輩が恐ろしくて辞めると言えないまま部活動を続けることになります。
学生時代は5分刈りで、学生服に学生帽しか着用は認められず、新入部員には度胸をつける練習だと新宿西口交番前の大勢通行人がいるところで挨拶の練習をさせるのが恒例でしたが、最初は恥ずかしさもあり声が出るものではありませんでした。
もちろんお酒も鍛えられましたが、2年時に体育会に昇格することになります。
勉強を頑張った記憶はあまりありませんが、本だけはよく読みましたし、体力的に鍛えられたとともに人間関係のけじめとか、何事にも動じない、逃げない姿勢を教えられ、それらは社会に出てから、大切なことに気付かされました。
学生の皆さんもいつかは社会へ出ることになりますが、一般社会では自分に都合のよい事、自分の好きな事ばかりをする訳にはいきませんし、何よりも物事に積極的に取り組む姿勢が求められると同時に、雑学的な知識や頭の柔軟性と発想力とが求められます。
そのためには専門書ばかりでなくジャンルに拘わらず多くの本を読破することが大切であり、活字離れといわれる時代ですが、時間のある学生時代だからこそ出来ることですので是非実践してください。
商学部学生諸君の活躍を期待しています。
|
|