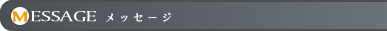 |
|
| 第42回 (2011.12.22) |
| 名雪 等 さん(ヤマサ醤油株式会社 経理・総務本部総務課長) |
| 1982年 商学部 商学科 卒業 |
|
 元々特別な目標があったわけでもなく、東京の大学にいって一人暮らしをしてみたいと思い立って受験勉強を始めたのは高校2年生ごろだったと思います。銚子商業という田舎の商業高校に入学していたので進学希望者も少なく、何冊かの参考書を繰り返し解くだけの受験勉強でした。そんな私にとっての明治大学は本当に夢の存在でした。本学を含めて運よく現役で何校か合格しましたが、迷わず明治大学に決めました。
元々特別な目標があったわけでもなく、東京の大学にいって一人暮らしをしてみたいと思い立って受験勉強を始めたのは高校2年生ごろだったと思います。銚子商業という田舎の商業高校に入学していたので進学希望者も少なく、何冊かの参考書を繰り返し解くだけの受験勉強でした。そんな私にとっての明治大学は本当に夢の存在でした。本学を含めて運よく現役で何校か合格しましたが、迷わず明治大学に決めました。
勉学については率直に言って褒められた学生ではなかったと思います。やはり普通科の進学校出身の同級生に比べて基礎学力が無いことを実感することも多々ありました。高校時代に少し得意だった簿記の勉強を頑張り、大学在学中に日商簿記検定1級を取得したのもそんな劣等感の裏返しでした。
こんなことを言うと暗い学生時代みたいですが、これだけ楽しく自由に生きて、友人に恵まれた時代はありませんでした。楽しそうな名前に惹かれて体育同好会連合所属のある同好会に入部したら、結構、本気な登山の団体でした。当時は全盛期で100名近い部員がいました。活動に於いては、それぞれ自分の本音でぶつかり合うこともあるが、しかし一旦方針が決まったら団結して成し遂げる、こんな濃密な人間関係をもてたことが何よりの経験だったと思います。色々な意味で、この4年間があって今の自分があるとハッキリ言えます。
就職はさほどの企業研究もせずに、馴染んだ地元の会社を受験しました。入ってみたら本学出身者が多いこと。銘遊会(めいゆうかい)なんていう、粋な呼び名の親睦会もあって、新人歓迎会や転勤者の送別会を開いています。
業務は営業職が長かったのですが、やはり基本は、言い古されていますが、人間関係です。食品メーカーの営業は、長年取引のある得意先を先輩から引き継ぎ、継続発展させるのが基本です。江戸時代の初期に創業した醤油屋ですから、100年近く取引している得意先もあります。お得意先とは運命共同体で、しかも何年も担当するので目先の誤魔化しは利きません。正直に熱心に取り組んで、心が通い合えばこんな楽しい仕事は無いと思いました。
しかし、順調なことばかりではなく、40歳を過ぎた頃に大病をしました。会社も配慮して職場を替えてくれましたが、配属先がなぜか本社研究所です。何をするのか?もしかしてリストラ?と不安に思いました。
そこでのメインの業務はお客様のご指摘事項に対する「回答書」の作成でした。風味、色、異物混入、ラベル、容器、物流事故までありとあらゆるご指摘事項に対して回答書を作成する仕事です。ご指摘品を時には顕微鏡や試用して細部まで観察し、検査データや製造現場の調査、外部に依頼した実験データなどをまとめあげて回答書を作成する仕事でした。商学部出身で営業一筋の私でしたから、毎日が勉強です。最初は新人社員にも及ばない知識だったと思います。研究者・技術者・製造現場の責任者に教えを受け、現場に入って自分で製造工程のフォローを図にまとめたりしました。少しだけ微生物の勉強も、聞きかじりました。それらの情報を自分の中で一旦理解しから、一般消費者の方にも分りやすい文章にするものです。
取り組むうちに、なぜこれを営業出身の自分に任されたのか分ってきました。誤解を恐れずに言えば、技術者の論文だけではお客様は納得しないのです。調査の結果自社に落ち度が無い場合がほとんどですが、お客様の気持ちを考えた回答書を書く。これが私に期待されているのだと気がつきました。色々とご指摘をいただく方は当社のファンなのです。顧客満足度を上げるのが最終の仕事だと考えました。この業務に就けた3年間が私にとってはターニングポイントでした。知識も社内の人脈も大いに増えて、自分の考え方も変わりました。
そして8年前から東京支店で総務課の仕事をしています。守備範囲は広く、トイレ掃除や排水管のつまりの心配から、建物管理、不動産関係、新卒及び中途採用まで本当に多方面にわたり飽きません。
特に社員の採用は営業出身者こそ得意とするところではないかと感じています。会社説明会は自社のプレゼンです。簡潔にしかも印象に残ることを心がけています。面接は学生さんを理解し、自社の良さを伝える大切な商談です。
また、商品・サービスを選ぶ側になると、営業職時代の自分の至らなかったところばかりが分ってきます。詳しくは書ききれませんが、拙い文章を読んでくださっている学生さんが営業職に就くことがあったら、成功のカギはどれだけ得意先の立場・方針を理解しているかに尽きると思います。自社の都合を押し付ける営業が一番駄目です。
最後に一つ、同じ程度の商品・サービスならば信頼できそうな担当者から購入します。それには普段から訪問して、親しくなっておくことです。商談のネタが無くて悩んだ時も、御用聞きだって顔を出さないよりはずっとまし、そんな開き直りも必要ではないでしょうか。(毎回では呆れられますが)
以上、思ったよりも長い文書になってしまいましたが、本学の発展と皆様のご活躍を記念して終わりとします。最後までお付き合いいただき有難うございました。
|
|