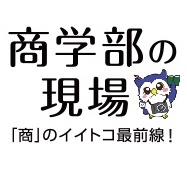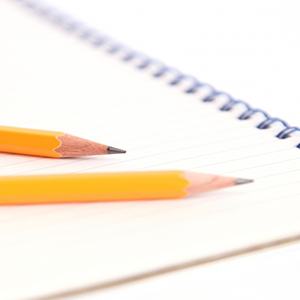2026年02月03日
1.実施日
2018年11月14日(水)13:30~15:10
2.実施場所
駿河台キャンパス リバティタワー 1165教室
3.科目名
総合学際演習
4.テーマ
日本とフランスの架け橋として
5.ゲストスピーカー
フロランス・メルメ・小川 氏(元明治大学商学部教授)
6.実施内容
タイトル:Pont entre le Japon et la France
(日本とフランスの架け橋として)
日本とフランスが「互いの相違」を意識し、その違いを相互に「尊重しあう」形で、過去160年にわたる日仏交流がなされてきたとOgawa元商学部教授は語り出す。そして、建造物・庭園・食事・ファッションなど学生に関心のあるであろう例を順次あげながら、両国の文化・社会の差異=特性をピックアップしていく。たとえば、建造物を「保存する」préserverという考えが18世紀に生まれ、それを法制化し、数世紀前の建物を守りぬくフランス。対して、明治維新以降の西洋化というスローガンのもと、景観が日々変わることに抵抗の少ない日本。シンメトリーを旨とする人工的な構造美を具現する欧州の庭園に対して、竜安寺に見てとれるような余計な装飾を退け、岩や小石を配するだけでわびさびを形にしたZenの世界。あるいはまた、宙に向かって大きく伸び「荘厳」という名の様式美を鼓舞するキリスト教教会に対し、杜の中にひっそり潜み静謐に徹する我が国の神社等々。
そうした例証から、「画一性」uniformitéに支えられた縦社会日本の精神性と「多様性」diversitéをよしとするフランスのそれとの違いへと話を転じ、畢竟、日常の暮らしのなかに見るべきもの、考えるべきものが隠れ、そこに気づきの原点があるのだとスピーカーは演繹法で話を収斂してゆく。日仏文化などというと壮大なテーマだと身構えがちだが、実は、日々の暮らしのなかにこそその原点が隠れていると。たとえば、ゴミをなくし、家屋が整然と立ち並び、木々を人工的に剪定した一見西洋風の近代都市がはたして人が暮らす理想空間なのか。あるいはまた、障子を張り替えるという日本のかつての風物詩がどのような意味を持っていたか。ゲストは学生に問いを投げかける。然り、等身大の暮らしを見つめ、そこから俯瞰的な広い視野へと通じる複眼を養うようにと簡明な比較対照を通じて語りかけたのだ。
授業後「井の中の蛙」ではなく、「既存の情報に振り回されない海外の生の文化社会に自身の目と足とで触れたくなった」とする声が複数聞こえてきた。30名ほどの学生は口々に「充実した時間だった」と言い残し、教室をあとにした。
久松 健一 (科目担当教員)