終氷期末、およそ17,000~15,000年前に展開し、大形石斧と尖頭器で構成される神子柴系石器群について、性格解明のアプローチと新たな研究の方向性を模索するシンポジウム“神子柴系石器群の生成とその性格をめぐって”が、2023年1月14日(土)、明治大学リバティタワーにおいて開催された。
科研費「神子柴系石器群の生成とその性格をめぐる研究」の研究代表者堤隆が主催し、明治大学黒耀石研究センター(COLS)が共催となって開催された。コロナ禍ではあったが60名ほどの参加者を得て、以下のプログラムにおいて実施した。
・ 総括報告 10:00~10:30 堤 隆 (明治大学黒耀石研究センター)
科研費「神子柴系石器群の生成とその性格をめぐる研究」実施報告
・ 講演1 10:30~11:30 堤 隆 (明治大学黒耀石研究センター)
「黒曜石熱破砕にみる神子柴の行為論」
昼食休憩
・ 講演2 13:00~14:20 田村 隆(元 千葉県立中央博物館 上席研究員)
「神子柴 do ut des」
・ 講演3 14:30~15:50 安斎正人 (元 東北芸術工科大学 教授)
「神子柴遺跡をめぐる象徴性」
・ パネルディスカッション 16:00~16:40 パネリスト 堤 隆・田村 隆・安斎正人
シンポジウムの射程は、神子柴遺跡の性格をいかに明らかにしていくかということであったが、田村隆氏は人類学的交換理論をもとに神子柴遺跡の成立に関して言明、安斎正人氏は象徴性をキーワードに神子柴遺跡を読み解いた。また、堤も神子柴遺跡の黒曜石熱破砕にみる行為の意味を象徴的観点から探った。
とくに両氏は、日本の旧石器考古学の理論の開拓者であり、理論基盤を構築した上で、神子柴遺跡の性格をどう解明するか、といった視座の重要性が再認識されたシンポジウムであった。
(明治大学黒耀石研究センター 堤 隆)
※ 本事業は、日本学術振興会科学研究費基盤(C)研究代表者 堤 隆 「神子柴系石器群の生成とその性格をめぐる研究」(17K03216)の一環です。
※ シンポジウムの発表要旨は、こちらからダウンロードできます。
https://sitereports.nabunken.go.jp/130439
 シンポジウムでの講演の様子
シンポジウムでの講演の様子
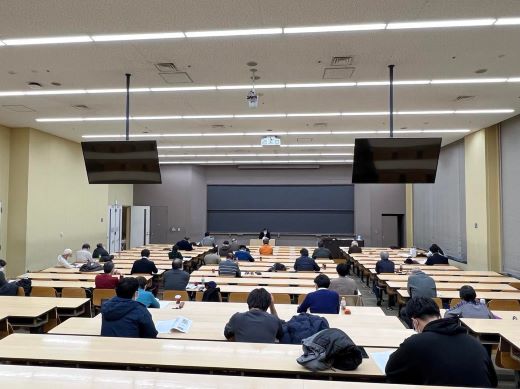 シンポジウムでの講演の様子
シンポジウムでの講演の様子

