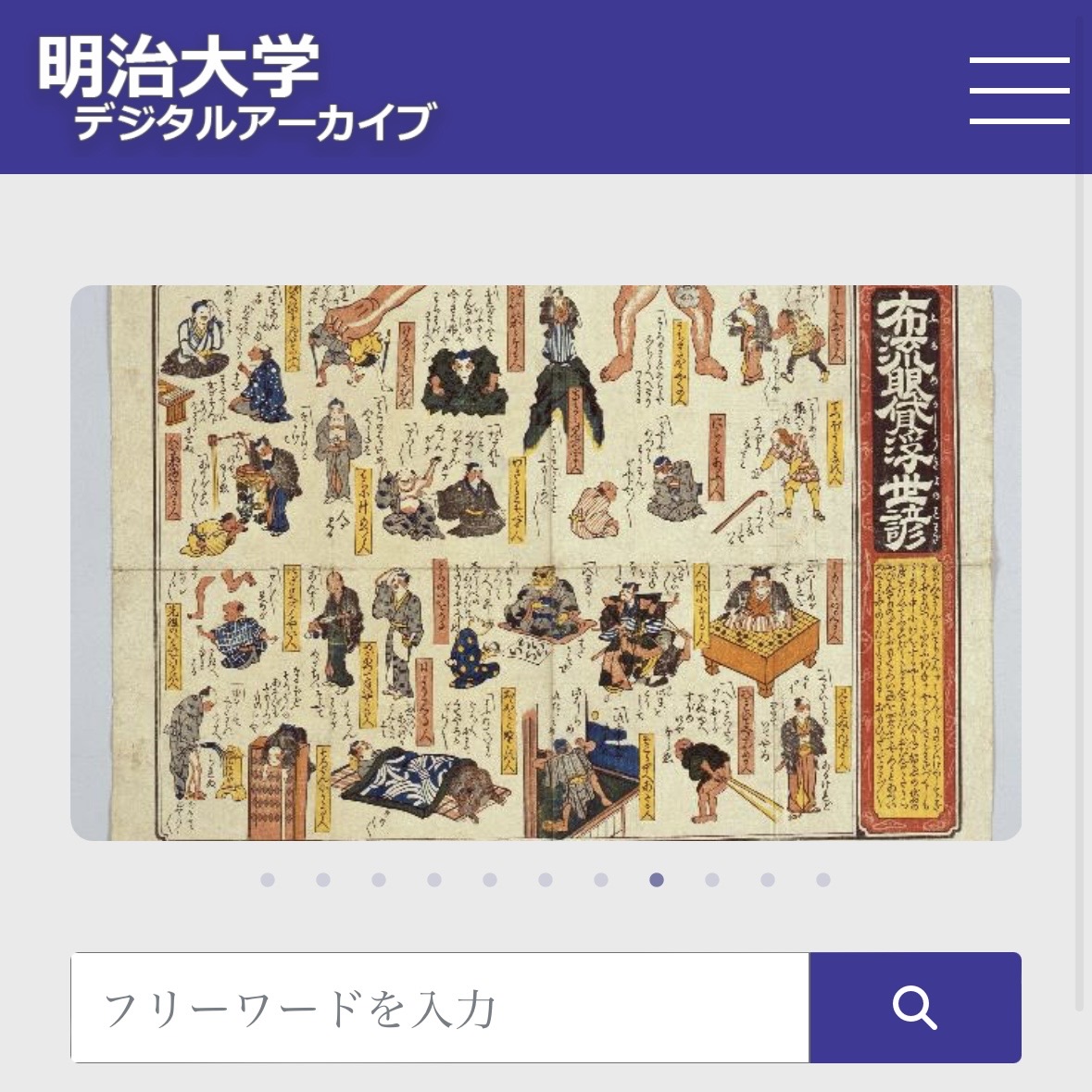明治大学博物館 公式Facebook
商品部門
商品陳列館の開設
伝統的工芸品の収集・展示
1970年前後の大学紛争時に閉鎖を余儀なくされた陳列館は1973年に再興されます。当時、花形商品であった自動車や新型家電の実物を多数収集するのは現実的ではなく、それらについては映画フィルムやカタログなど2次資料を収集・活用することとし、実物は伝統的工芸品を収集・展示する方針が採用されました。
同じ頃、通商産業省(現経済産業省)が「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」を制定(1974年)し、先端産業ではない地方の中小企業支援という政策転換として注目を集めましたが、高度経済成長の結果生じた都市一極集中や環境破壊を契機に地域色、伝統文化、自然保護への関心が高まりを見せた時代でした。
高度成長後の時代相について、刀根武晴第三代館長は「不確実性の時代,不透明の時代」「選択の時代など色々な形容詞を冠して呼ばれる1980年代」(『明大商品陳列館報』5号)と評し、混迷を打破する「現代文明の原動力」として「手づくりの文化」に言及し、「伝統的な社会において」「単に商品生産のための技術ではなく、生活のための技術が文化として存在」「人間がどのように才覚を発揮して商品形態を作りあげ、生活文化を形成させてきたかを今こそ見直すことが必要」と述べています(同誌6号、1982年)。
運営に関わる教員個々の研究テーマは現代産業に関わるものでしたが、異なる視点からインスピレーションを得る意図で、伝統的工芸品の調査・収集・展示が陳列館の事業として継承され、今日の商品部門に至っています。