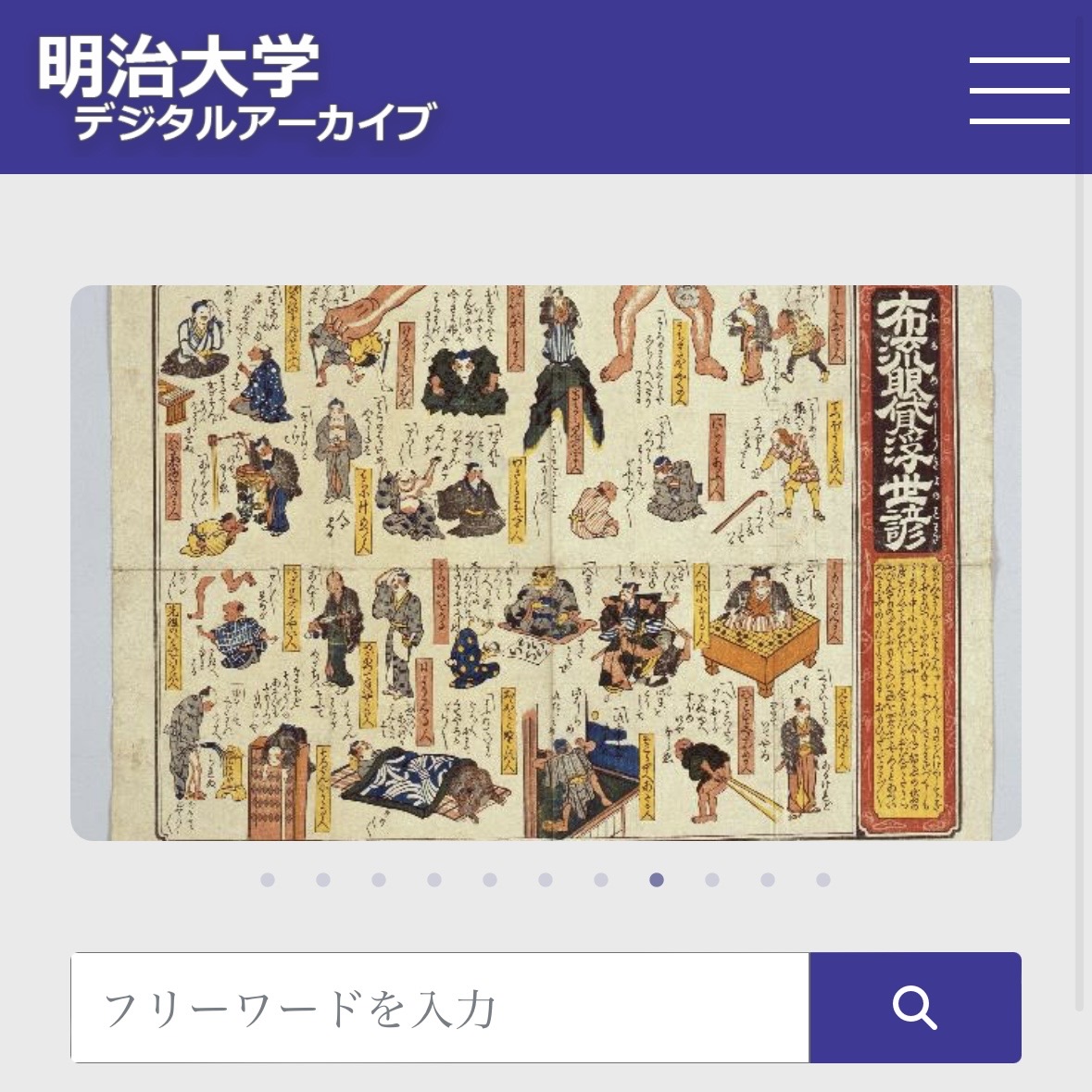明治大学博物館 公式Facebook
明治大学博物館友の会 行事予定
<世界史講演会>「シルクロードのソグド都市と文化交流—拝火寺院の調査成果を中心に—」
講師:村上 智見(むらかみ ともみ)氏(東北芸術工科大学 芸術学部 文化財保存修復学科 准教授)
ソグド人と言われても、なかなかイメージが持ち難いと思いますが、唐を通じて西域の品々を持ち込んだり、奈良の都に鑑真とともに訪れたり、日本とも浅からぬ関係があると言われています。是非この機会にソグドの民のことに触れてみてはいかがですか。お誘いあわせの上、お申し込みください。
| 日 時 |
10月31日(金)14:00~15:30(受付開始13:45)
|
|---|---|
| 会 場 |
明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン8階 308E 教室
|
| 定 員 |
90名(教室での聴講のみです。)
|
| 参加費 | 無料(友の会会員限定。但し、この機会に入会される方は参加できます。) |
| 申込方法 | 事前申し込み 電子メール、はがきによる申し込みのみ。Faxは不可です。
会員:氏名、電話番号、会員番号、「世界史講演会」参加を明記、
一般入会希望者:上記4点に加え、住所も記載
メールアドレス:meihakutomonokaig★gmail.com(★を@に置き換えてご利用ください。)
はがき宛先:〒101-8301東京千代田区神田駿河台1-1 明治大学博物館友の会
|
| 締切日 | 10月24日(金) ※定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。 |
| 共同主催 |
明治大学博物館、明治大学博物館友の会
|
【講演要旨】
ソグド人は中央アジアのソグディアナを本拠地とし、シルクロード交易を担ったイラン系の民族です。東西文化交流を促した立役者でもあったと言っても過言ではなく、唐代にはソグド人がもたらした美術、音楽、服飾などの西域文化が大流行し、日本にも少なからぬ影響を与えました。しかし、8世紀初頭にイスラーム勢力がソグディアナに侵攻したことを契機に、彼ら独自の文化は徐々に衰退し、やがて歴史の表舞台から姿を消していきました。
これまでソグド都市と文化の実態を明らかにするべく、ウズベキスタン共和国において発掘調査に携わってきましたが、2022年度からは、新たにクルゴン・テパ遺跡およびクルドル・テパ遺跡での調査を主導しています。これらの遺跡では、壁画や祭壇、人物彫像などを伴った、寺院とみられる極めて貴重な遺構が発見され、当時のソグド人の文化、信仰、美術の広がりがより鮮明に見えてきました。あわせて、日本を含む東アジアへと広がった文化との接点を物語る貴重な出土資料も得られています。
本講演では、こうした現地における発掘の最新成果を紹介いたします。ソグド人を通して見えるシルクロード文化の広がりと、日本に伝わった西域文化の源流について、思いをはせる機会になれば幸いです。
(講師より)
【講師プロフィール】
北海道出身。奈良大学文学研究科文化財史料学博士後期課程修了、博士号取得。
日本学術振興会特別研究員PD(帝塚山大学)、日本学術振興会海外特別研究員(All-Russian Art Research and Restoration Center named after Academician I.E. Grabar)、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター非常勤研究員、北海道大学アイヌ・先住民研究センター博士研究員、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター特任助教を歴任。2024年より現職。
<博物館企画展関連見学会>「信楽焼の里と琵琶湖東岸の遺跡を巡る」
3月から5月にかけて、「進化する信楽焼の「伝統」」と題した博物館の展示をご覧になった方も多いと存じます。その信楽焼の里を外山学芸員のご案内でたどりながら、周辺にある選りすぐりの遺跡を見て回り、近江牛にも舌鼓を打ってもらいます。奮ってご参加ください。
【 実 施 要 領 】
| 実施日 | 2025年12月4日(木)~5日(金) |
|---|---|
| 集合 |
東海道新幹線米原駅 新幹線改札口
午前10時30分
(参考アクセス 8:00東京(のぞみ61号)→9:39名古屋9:43(こだま703号)→10:10米原)
|
| 宿泊 |
ビジネスホテルタカラ(野洲市内)
tel 077-587-0391 *シングルルーム
|
| 見学予定コース |
※天候等で変更の場合があります。
(1日目)10:30米原駅バス出発~近江商人博物館~昼食~安土城考古博物館~雪野山歴史公園~野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)~17:10ホテル着
(2日目)8:30ホテルバス出発~伊勢遺跡史跡公園~信楽焼ミュージアム(伝統産業会館)~信楽窯元散策~昼食~紫香楽宮~東海道新幹線米原駅16:30頃解散
|
| 参加費 |
34,000円(予定額)
(貸切バス、宿泊費、食事代:朝食1、昼食2、夕食1、保険料など)
※参加人数により参加費が変動する場合があります。
|
| 定員 |
30名(先着順、会員限定)
|
| 申込方法 |
メールまたは往復はがきにて(FAX不可)。
郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・携帯番号・会員番号・「宿泊見学会」係と明記の上、お申込みください。
|
| 締切日 | 11月5日(木) |
| 事前学習会 | 外山学芸員による学習会を開催する予定にしております。 |
【 主な見学場所 】
(1)信楽焼ミュージアム(伝統産業会館)
常設展示室があり鎌倉時代から現在までの信楽焼の紹介している。企画展「信楽焼指定無形文化財展」が開催されており観覧ができる。
(2)信楽窯元散策
信楽駅前から続く古いたたずまいの路で、登り窯や無造作に積まれた古い火鉢、「陶生町」「焼屋町」といった町名が、陶都信楽ならではの風情をかもし出している。窯元のショールームや工場内の見学を予定。
(3)雪野山歴史公園
標高308.8mの山頂にある雪野山古墳は4世紀前半の竪穴式の前方後円墳。出土した銅鏡、漆製品、石製品、ガラス小玉等218点は重文。麓にある八幡社古墳群は前方後円墳を含む17基の後期古墳群である。
(4)野洲市歴史民俗博物館
銅鐸博物館と言う愛称で親しまれ、大岩山から出土した銅鐸24個を中心に展示されている。隣接する弥生の森歴史公園では復元住居があり、弥生時代の人々の生活や文化を実物大で体験できる。
(5)伊勢遺跡
弥生時代後期、多数の大型建物が整然と建ち並ぶ巨大な祭祀空間で、中国伝来の最新建築技術が使われた建物もあった。史跡公園として整備され遺構が保存展示され、ジオラマ展示なども楽しめる。近江南部の「クニ」の中枢だったのか。

抹茶碗(自然釉を模した商品)1992年収集
「企画展 進化する信楽焼の「伝統」」より
<博物館館長 講演会>「人工知能は人間に迫れているのか~生成AIの急速な発展に寄せて」 ※教室での対面のみ
講師:石川 幹人(いしかわ まさと)氏(明治大学博物館館長 情報コミュニケーション学部教授)
昨年に引き続き、明治大学博物館館長の石川先生をお招きし講演会を開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。
| 日 時 | 2025年12月20日(土)14:00~15:30(受付開始13:45) |
|---|---|
| 会 場 |
明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント2階4021教室
|
| 定 員 | 90名 (Zoomによるオンライン配信はありませんので、ご注意ください。) |
| 参加費 | 無料(友の会会員限定。但し、この機会に入会される方は参加できます。) |
| 申込方法 |
事前申し込み 電子メール、はがきによる申し込みのみ。Faxは不可です。
会員:氏名、電話番号、会員番号、「館長講演会」参加を明記
一般入会希望者:上記4点に加え、住所も記載
メールアドレス:meihakutomonokaig★gmail.com(★を@に置き換えてご利用ください。)
|
| 締切日 | 12月6日(土) ※定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。 |
| 共同主催 | 明治大学博物館、明治大学博物館友の会 |
【講演要旨】
講演者の基本的な興味は認知科学、つまり、人間の思考(ものの見方や考え方)の原理を究明することにある。昨年の講演では、私たち人間がお人好しで騙されやすいのも、狩猟採集の生活に適応したことに由来すると、人間の思考の特徴を生物進化の歴史を背景に講じた。今年の講演では、昨今飛躍的に性能を上げている生成AIの発展を背景にし、人工知能(AI)によって人間の思考が解明されているのか、あるいは我々の⼼も結局のところ、脳という生物学的な機械の動きに過ぎないのかという根本的な疑問を深堀りする。
講演では第1に、現在「第3次AIブーム」を迎えているAI研究の歴史を概観する。1950年代に始まったAI研究は、当初から論理計算にもとづくアプローチと、脳を模倣したモデルにもとづくアプローチとの対立が続いてきた。第3次AIブームはディープラーニングや生成AIの成果に代表される脳モデルの成功に特徴づけられており、その意味では、過去2回のAIブームが論理計算中心であったのに対して、脳モデル中心のブームに来ていると言える。今後は対立を超えて両者の融合が進む見込みであり、それとともに、人間の仕事が大々的にAIへと置き換わる将来像が描かれる。
第2に、AI技術の発展によって人間の思考原理が解明されたかどうかを検討する。認知科学はAIをひとつの有力な研究手段としており、AIが人間を忠実に模倣している間(強いAI)は良き研究手段と言える。だが一方で、AIモデルには脳にはありそうもない処理も実用性の観点から組み込まれており(弱いAI)、AI技術の発展がつねに人間の究明に迫っているわけではない。とはいえAI技術は、言語学習や身体技能獲得の面で人間研究に新しい地平をもたらし、知能ロボットの実現を予感させる。
第3に、生成AIの成功要因を解説しながら、人間の思考や心の働きが将来解明されるかどうかを吟味する。AIの性能には人間を凌駕する面があるが、AIさえも作れてしまう人間の創造性にはまだ至っていない。とりわけ、創造的な頭脳を生み出した生物進化の過程には依然として大きなミステリーが残されている。むしろAI研究の成功裏にはミステリーが垣間見え、人間の知能が単純な機械に還元されることはなさそうだと指摘する。 (講師より)
【講師プロフィール】
1959年東京生まれ。東京工業大学(現、東京科学大学)理学部で生物物理学を、同大学院物理情報工学専攻で心理物理学を学ぶ。
パナソニック(株)マルチメディアシステム研究所、(財)新世代コンピュータ技術開発機構研究所で、人工知能の研究開発に従事し、人工知能技術を遺伝子情報処理に応用する研究で博士(工学)を取得。
1997年に明治大学文学部に赴任し、文学部心理社会学科や情報コミュニケーション学部の新設に寄与。2002年には米デューク大学に客員研究員として滞在。
2004年に開設された情報コミュニケーション学部へ移籍し、同学部長、明治大学大学院長を歴任。
専門は認知情報論で、情報科学と生物学と心理学の学際領域研究を長年手がけている。
著書に『だからフェイクにだまされる』(ちくま新書)、
『なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの?』(朝日新聞出版)、
『進歩した文明と進化しない心』(KANZEN)など多数がある。
詳しくは、http://www.isc.meiji.ac.jp/~ishikawa/を参照されたい。
<Zoomによる 第29回古代史講演会>「福井洞窟の最新調査報告-洞窟遺跡の保存と活用-」
講師:栁田 裕三(やなぎだ ゆうぞう)氏(佐世保市教育委員会文化財課主査 文化財専門職員)
| 実施日 | 2026年1月28日(水) |
|---|---|
| 会場 | Zoomによる視聴 (対面ではありませんのでご注意ください) |
| 時間 | 14:00~15:30(13:45より入場可能) |
| 定員 | 先着順 90名 (友の会会員限定) |
| 参加費 | 無料 |
| 申込方法 |
メールによる事前申し込みに限定されます。
講演会参加の招待状は開催前日には送信元のアドレスへお送りいたします。
申込みアドレス: meihakutomonokaig★gmail.com(★を@に置き換えてご利用ください。)
件名に「古代史講演会参加」と明記し、本文に氏名、会員番号、電話番号を記載ください。
なお、一般の方は住所ならびに入会希望の旨も記載ください。
|
| 締切日 | 2026年1月21日(水) *定員になり次第締切りますのでお早めにお申し込みください。
一般申込の方へ:年会費のお支払方法等を送信元のアドレスへ返信いたしますので、内容ご確認の上、お手続きをお願いします。
|
【講演要旨】
福井洞窟は、『日本列島における後期旧石器時代から縄文時代への移行を連続的に示す洞窟遺跡』として評価され、令和6年10月11日に特別史跡に指定された。特別史跡は、史跡の中でも『学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの』が選ばれ、福井洞窟は長崎県ので3例目であり、旧石器時代まで遡るものとして国内初の指定である。
福井洞窟は長崎県佐世保市に位置する。昭和30年代と平成20年代に発掘調査が行われた。平成の再発掘調査では、旧石器時代細石刃文化期の炉4基や石敷、骨片集中部などの遺構を重層的に検出したことによって、逆転のない文化層序を確認し、放射性炭素年代とともに細石刃石器群の初現から終末にいたる変遷と土器出現の過程が明らかとなった。また、旧石器時代から縄文時代の環境変動期において、河川の側刻と地滑り等によって洞窟地形が形成された過程を明らかにし、旧石器時代では珍しい炉や石器製作跡を中心とした洞窟利用を明らかにした。
このように半世紀保護され再発掘したことによって、新たな包含層や遺構を確認し、自然科学分析を行うことで今日的な視点から学術的価値を見直すことができた。さらに、遺構を保存しつつ発掘作業を進め、岩盤まで到達したことで、連続的な地層剥ぎ取りを行い、展示資料を多く採取できた。令和3年には福井洞窟ミュージアムが開館した。交通の不便な立地にもかかわらず、年間1.5万人が訪れており、学校教育や他都市博物館との連携企画展なども行われている。今回の特別史跡指定は、平成17年から約20年にわたる調査・整備の成果であり、史跡に関わった多くの人々の努力が実を結んだものといえる。 (講師より)
【講師プロフィール】
1979年、宮崎県生まれ。別府大学文学部文化財学科卒業。宮崎県教育委員会埋蔵文化財センター任期付職員をへて、現在、佐世保市教育委員会文化財課主査。文化財専門職員。これまでに山田遺跡、筆無遺跡、堀川運河などの宮崎県の発掘調査や福井洞窟、直谷岩陰、大古川岩陰など佐世保市内の洞窟遺跡の調査・整備に従事。主な著作・論文 『史跡福井洞窟発掘調査報告書』(編著、佐世保市教育委員会、2016)、『旧石器から縄文のかけ橋!福井洞窟—洞窟を利用しつづけた大昔の人々—』(編著、雄山閣、2022)、「西北九州の洞穴遺跡からみた更新世から完新世移行期の素描」『九州旧石器』21(九州旧石器文化研究会、2018)ほか。
江戸時代を探訪するPart11「旧板橋宿平尾から上板橋宿・板橋区立郷土資料館へ-川越街道を歩く-」
江戸と川越を陸路で結ぶ川越街道は、川越の政治・経済・文化的な重要性から、江戸時代に五街道に準ずる脇往還に位置付けられていました。川越街道の起点は、五街道の一つである中山道の初宿・板橋宿南端の平尾(平尾宿)であり、川越街道の最初の宿場が上板橋宿です。同宿は、上宿・中宿・下宿から構成され、五街道の板橋宿に及びませんが、脇往還の宿場として、重要な役割を果たしていました。今回は脇往還の宿場を探索したいと思います。
併せて、板橋宿・上板橋宿がかつて存在した板橋区の考古・歴史・民俗等を学ぶため、同区郷土資料館を訪れます。
【実施要項】
| 実施日 | 2026年2月25日(水)(小雨実施) |
|---|---|
| 集合 | 10:00 JR埼京線 板橋駅 改札口 |
| 予定コース | 板橋駅東口~近藤勇と新選組隊士の墓~(中山道)~前田加賀藩下屋敷跡(都立北園高校)~板橋宿平尾宿(平尾宿一里塚跡、観明寺:加賀前田家下屋敷ゆかりの寺)~(川越街道・東武東上線大山駅通過)~旧上板橋宿(上板橋宿名主屋敷跡、下頭橋:江戸期に石橋として建設)~東武東上線中板橋駅(昼食解散・同駅改札口にて再集合)~(鉄道)~同線成増駅~(バス)~板橋区立郷土資料館~(バス)~成増駅・16:00解散(予定) |
| 同行講師 | 明治大学農学部兼任講師 森 朋久 氏 |
| 定員 | 30名(先着順) |
| 参加費 |
会員 1,200円 一般 1,500円<予定> (保険料、資料代等含む)
当日集金 *昼食は各自ご持参ください
|
| 申込方法 |
事前申込制(先着順)
メール&往復はがきにて郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・携帯番号・会員番号・「江戸探訪係」と明記の上お申込みください。 |
| 締切日 | 2026年2月11日(水) |
【主な見学場所】
(1)近藤勇と新選組隊士の墓
新選組隊長・近藤勇は、慶応4年(1868)4月に板橋平尾宿の一里塚で斬首、首は京都三条河原にさらされ、胴は滝野川三軒家の無縁塚に埋葬された。墓碑は近藤勇、土方歳三のほか殉死した隊士の供養のために、新選組隊士・永倉新八が発起人となり、旧幕府典医松本順(良順)の協力を得て明治9年(1876)に建てられた。新選組の祭祀を目的の最初期の供養塔として貴重である。
(2)前田加賀藩下屋敷跡
延宝7年(1679)前田家は板橋宿に隣接した平尾に藩邸を拝領した。最初は6万坪であったが、駒込邸の一部や筋違邸等を上地し、最終的には天和3年(1683)に22万7900坪余に拡張される。その大部分は庭園で、邸内を石神井川が流れ、広大な回遊式の大池が存在した。
(3)板橋宿平尾
板橋宿は、中山道の初宿で、下板場宿とも称される。平尾宿・中宿・上宿で構成され、それぞれに名主が置かれた。平尾宿は、中山道と川越街道の分岐点である。平尾宿に一里塚が存在し、その付近で近藤勇が処刑された。平尾宿には料理・茶屋が軒を連ね、宿場というよりは繁華街的な賑わいがあった。
(4)上板橋宿
板橋宿平尾で分岐した川越街道の最初の宿場である。上宿・中宿・下宿で構成され、街並みは6町40間。江戸日本橋へ二里半、下練馬宿へ26町の人馬の継立てを行ったが、助郷はなかった。中宿にあった名主屋敷で宿場業務を行った。宿場西端を石神井川が流れる。
(5)板橋区立郷土資料館
昭和47年(1972)赤塚城址及び赤塚溜池公園に隣接する場所に開館した郷土資料館は、板橋区の歴史や文化・自然に関するさまざまな資料、情報の展示を行い、講習会・講座・体験学習を通して、郷土に関する情報を発信している。
2025年度行事予定表
明治大学博物館友の会(2025年10月現在)
| 2025年 | 見学行事 | 講演会等企画 |
|---|---|---|
| 4月 |
|
|
| 5月 |
17(土)総会特別講演会 寺澤知子氏(神戸女子大学名誉教授)「4世紀の倭国-政権の動向と『記紀』伝承」
|
|
| 6月 | 5(木) 《会員企画による東京近郊の遺跡 探訪》 縄文の漆の里「下宅部遺跡」に行ってみよう! |
24(火)第28回古代史講演会 設楽博己氏(東京大学名誉教授) 「黥面から見えてくる邪馬台国」 (H)
|
| 7月 |
26(土)近世史講演会 桑野梓氏(なら歴史芸術文化村学芸員) 「大阪・茨木のキリシタン遺物発見とかくれキリシタン『発見譚』」 (Z)
|
|
| 8月 | ||
| 9月 |
|
20日(土)日本考古学2025
|
| 10月 |
31日(金)世界史講演会 村上智見氏(東北芸術工科大学 芸術学部 文化財保存修復学科 准教授) 「シルクロードのソグド都市と文化交流—拝火寺院の調査成果を中心に—」
|
|
| 11月 | ||
| 12月 | 4日(木)~5日(金)<博物館企画展関連見学会>「信楽焼の里と琵琶湖東岸の遺跡を巡る」 |
20日(土)博物館館長講演会 石川幹人氏(明治大学博物館館長 情報コミュニケーション学部教授) 「人工知能は人間に迫れているのか~生成AIの急速な発展に寄せて」
|
|
2026年
1月
|
|
28日(水)第29回古代史講演会 栁田裕三氏(佐世保市教育委員会文化財課主査 文化財専門職員) 「福井洞窟の最新調査報告-洞窟遺跡の保存と活用-」(Z) |
| 2月 | 25日(水)江戸時代を探訪するPart11「旧板橋宿平尾から上板橋宿・板橋区立郷土資料館へ-川越街道を歩く-」 | |
| 3月 |
|
|
| 4月 |
(注)講演会の日程・講師は予定のもので変更などもあり得ますので、ご了承願います。
Z:Zoom利用によるリモート講演会をいう。
H:会場とZoom併用による講演会をいう。
H:会場とZoom併用による講演会をいう。
| ハイブリッド講演会(会場参加とオンライン併用)における申込方法および留意事項について |
|---|
| これまで、オンラインでの講演会には参加の叶わなかった会員の方々に、博物館教室での対面講演を実施する運びとなりました。この機会に是非博物館にもお越しくださいますよう心よりお待ち申し上げております。
申込方法:会場参加、オンライン参加のいずれかとし、事前申込みが必要です。
会場参加:普通はがきに限定、Fax不可。
※電子メールをお持ちの方もはがき申し込みとなります。
記載事項:住所、氏名、電話番号、会員番号(会員の方)、入会希望(一般の方)、「○月○日○○○講演会」参加 と明記
※「○○○講演会」には申込みをしようとする該当講演会名を記載願います。
定員に達してご参加できない場合、または開催方法等に変更が生じた場合に限り、はがきまたは電話にてご連絡いたします。 オンライン参加:電子メールに限定。
申込みアドレス: meihakutomonokaig★gmail.com(★を@に置き換えてご利用ください。)
件名に「○月○日○○○講演会」参加と明記し、本文に住所、氏名、電話番号、会員番号(会員の方)、入会希望(一般の方)、を記載ください。講演会参加登録用URLを開催前日には送信元のアドレスにお送りします。
お願い:
・会場参加とオンライン参加とで申込方法に相違がありますが、事務処理上の観点から区分いたしましたのでご理解ご協力をお願いいたします。
・特に会場の定員から、より多くの会員に参加いただきたく、これまでZoom講演会に参加された方には申込み状況によりオンライン参加をお願いすることもありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
・一般の方で今回友の会に入会される場合の年会費は、2023年度会費3000円です。お支払い方法につきましては、次のとおりです。
会場参加:当日会場にて納付していただきます。
オンライン参加:電子メールによる申込みがあった場合、受付状況等を確認のうえ振込み口座等を返信いたします。
【新型コロナウイルス感染対策について】
・マスクの着用をお願いいたします。
・当日、発熱または体調不良の方は、会場でのご参加を遠慮願います。
・ご入場時は、必ず入口での消毒にご協力をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催方法や会場等に変更が生じる場合がありますので予めご了承ください。
|