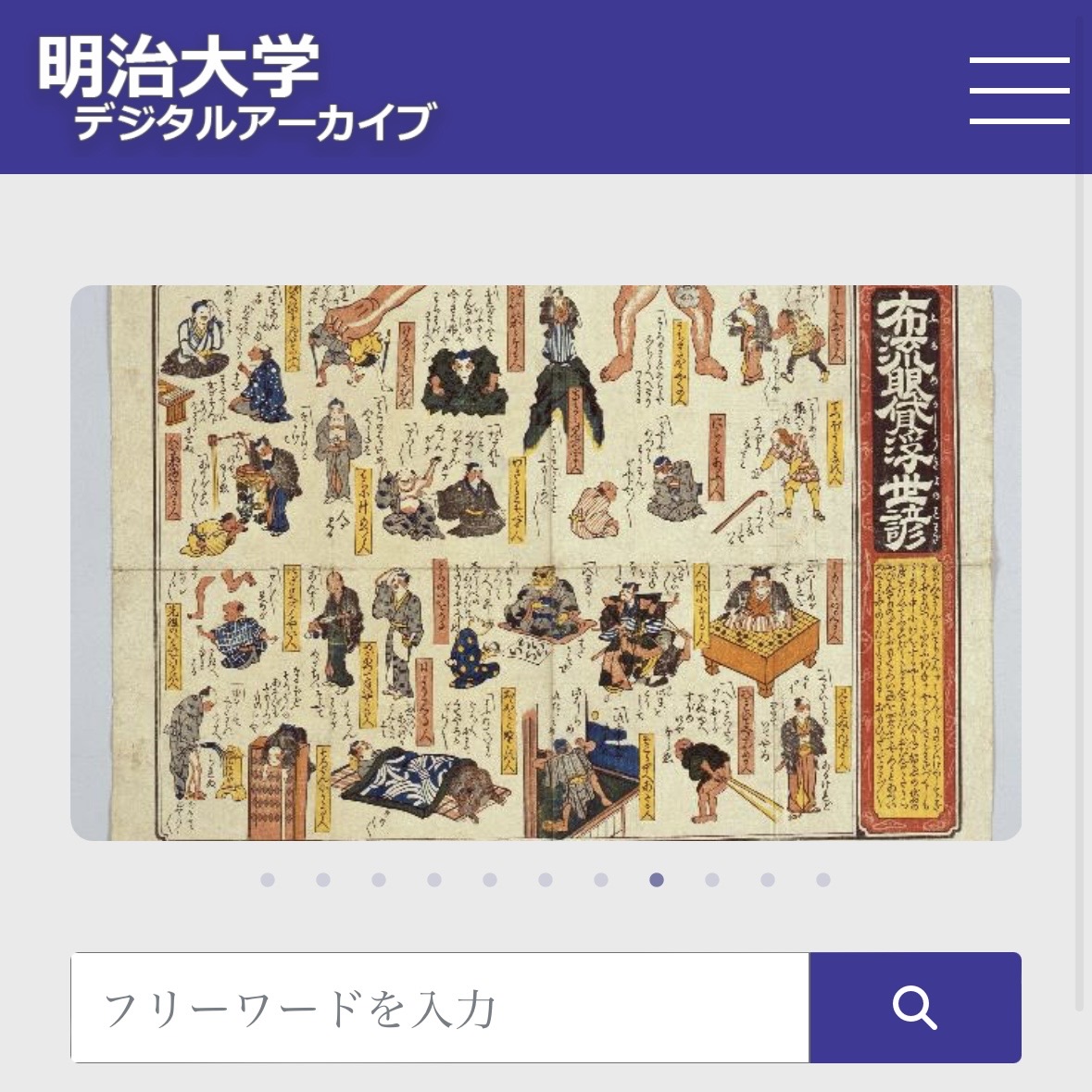明治大学博物館 公式Facebook
刑事部門
刑事博物館の設立
戦後の刑事博物館
戦前は常設の展示施設はなく、所蔵品は駿河台キャンパス・記念館5階の一室に収納され、行事の時などに臨時に公開をしていたようです。戦後、大学の創立70周年記念の際に、所蔵品を図書館閲覧室に列品して展示会を開催したことを契機に再建されることになり、1953年度から法学部の島田正郎教授(当時)が、その運営を指揮しました。再建にあたり、島田教授は、法学部の鍋田一助教授(当時)、文学部の木村礎助教授(当時)の協力を得て、これまでとは異なる方向で、館の運営に当たろうと考えました。刑罰具などの刑事法学習の実物資料を収集することは困難であったため、刑罰器具の収集から離れて、明治立法史関係文書と日本近世法律文書を収集対象とすることにしたのです。明治立法史関係文書に着目したのは、明治大学の関係者で日本近代法の立法事業に参画した人が少なくなかったためであり、近世法律文書とは、法律を生み出す社会そのものを広く見据えたもので、主に近世村方文書が対象でした。後に、そこには「本学法学部をもって、明治期立法史研究の中枢たらしめ、本学文学部をもって、本邦近世村落史研究の中心たらしめ」るとのビジョンがあったと回顧しています(『明治大学刑事博物館年報24』より)。新しい資料収集方針のもと、刑事博物館は、全国有数の質と量を有する資料保存機関に成長し、その充実した収蔵資料からは多くの優れた法制史、日本史研究が生み出されていきました。
施設の移転—いくつかの場所で—
戦後の刑事博物館は、1954年4月に2号館4階で活動を再開し、6月からは展示公開も始めます。その後、1966年に小川町校舎3階に移転。大学会館建設に伴って1981年に1号館1階に仮移転し、1985年に大学会館3、4階に落ち着きました。常設の展示のほか、1989年からは企画展も開催し、学生・院生・研究者の資料の閲覧利用に応えるとともに、展示という形での公開も進めました。以上のような長い歴史を受け継ぎつつ、2004年に刑事博物館は新博物館の刑事部門となり、アカデミーコモンで新たな一歩を踏み出しました。