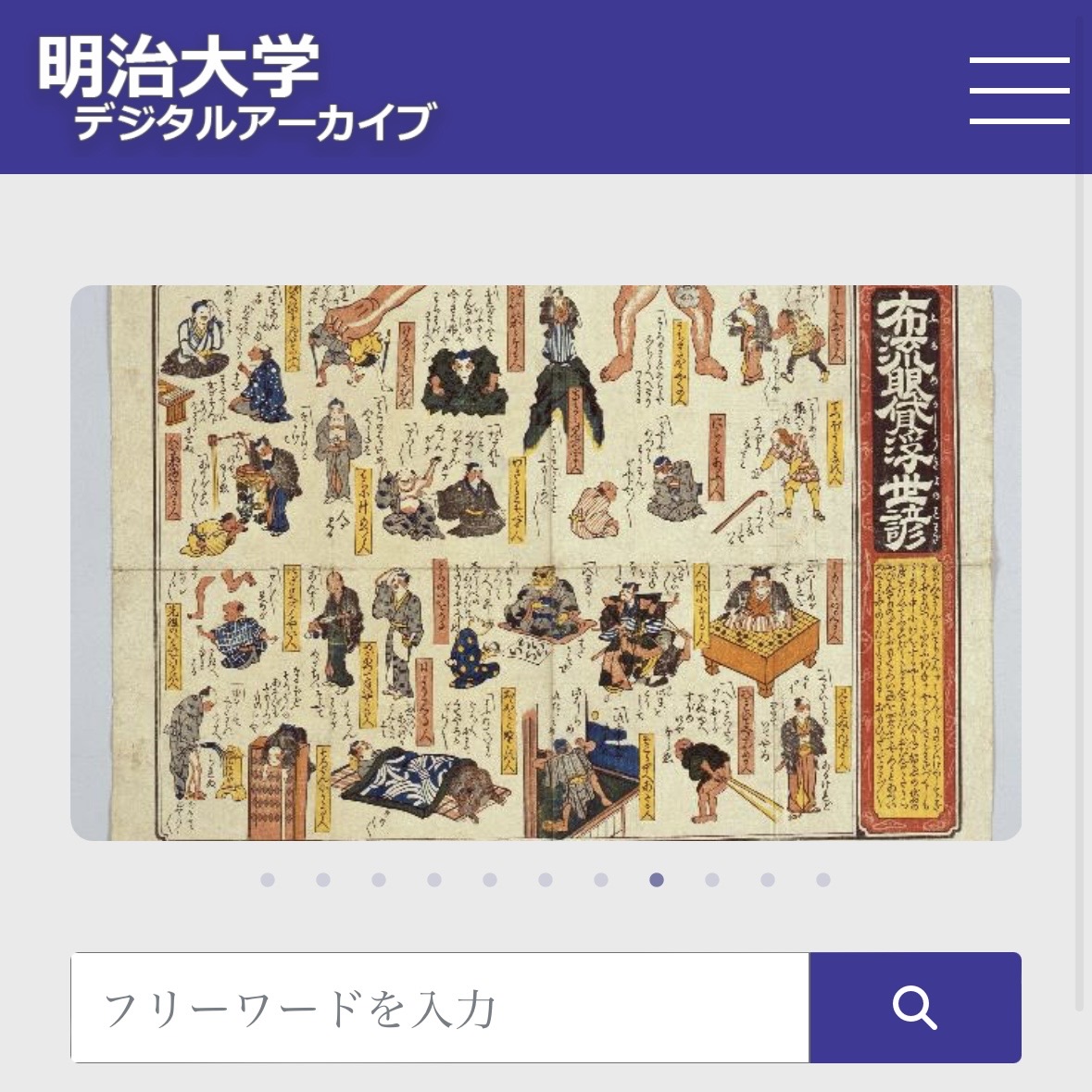明治大学博物館 公式Facebook
開催期間:2025年05月29日~2025年07月16日
明治大学 博物館事務室
| 主催 | 明治大学博物館 |
|---|---|
| 共催 | 明治大学文学部史学地理学科考古学専攻 |
| 会期 | 2025年5月29日(木)~7月16日(水) |
| 会場 | 明治大学博物館 特別展示室 |
| 開館時間 |
平日 10:00~17:00(最終入場16:30)
土曜 10:00~16:00(最終入場15:30)
休館 日曜・祝日
|
| 料金 | 無料 |
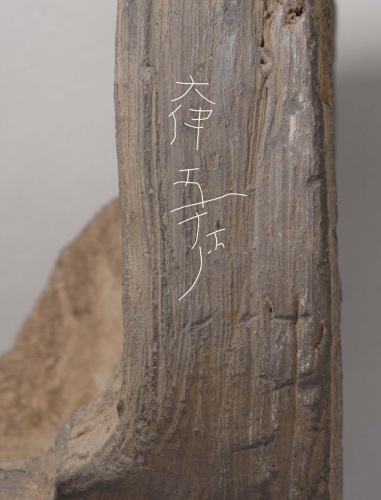 神奈川県千代廃寺の「五十戸」銘文字瓦(文字部分を加工しています)
神奈川県千代廃寺の「五十戸」銘文字瓦(文字部分を加工しています)
 長野県信濃国分寺の軒丸瓦
長野県信濃国分寺の軒丸瓦
 大坂城の金箔軒丸瓦
大坂城の金箔軒丸瓦
 江戸時代の鬼瓦
江戸時代の鬼瓦
明治大学博物館
<ご案内>
当館では、以下の事項に係る問い合わせについては、ご回答いたしません。予めご承知おきください。
・鑑定並びに同定及び市場価格に関する問い合わせ。
・史料の判読、解読、注釈及び翻訳に関する問い合わせ。
・ある事項(事柄・事件・人物)についての調査及び関連する資料の所蔵調査に関すること等、調査・研究の代行にあたる問い合わせ。
・網羅的な文献目録の作成にあたる問い合わせ。
・研究者の紹介及び仲介に関する問い合わせ。
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 アカデミーコモン地階
eメール:museum-info★mics.meiji.ac.jp(★を@に置き換えてご利用ください)
TEL:03-3296-4448 FAX:03-3296-4365
※土曜日の午後、日曜日・祝祭日・大学の定める休日は事務室が閉室となります。