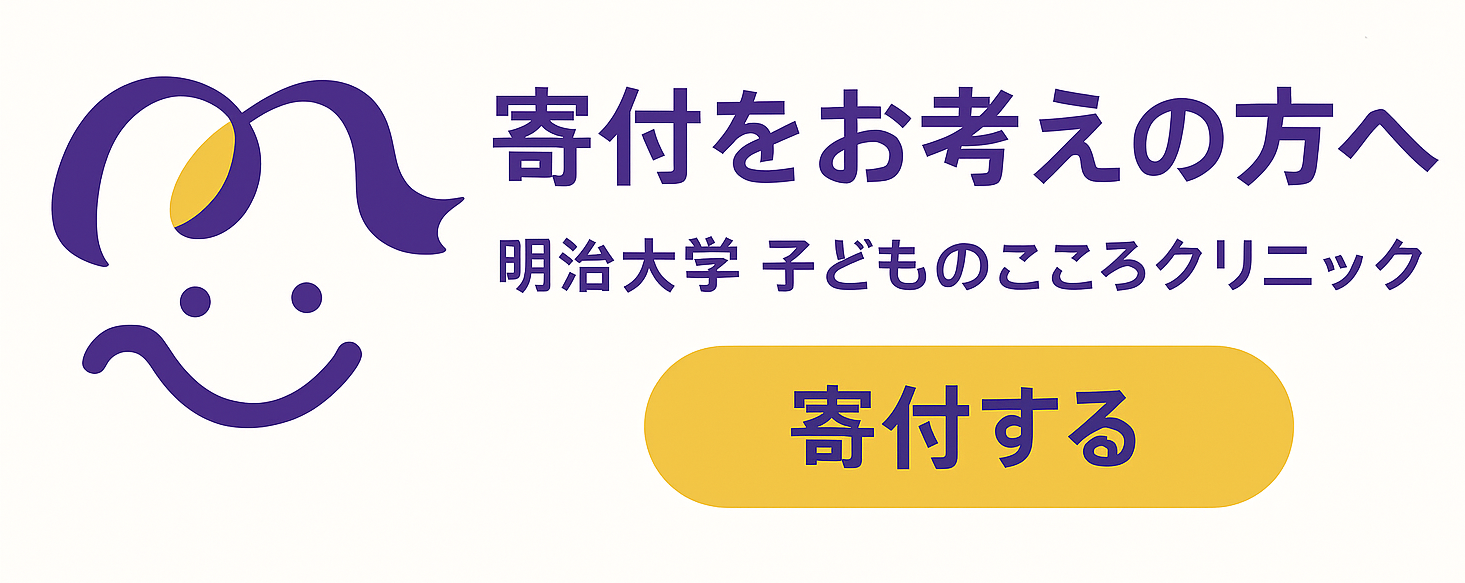「境界知能」について書いていたとき、学校の先生たちはどう思うかちょっと気になったので、長年にわたり小学校の教員をやっていた友人に書いたものを読んでもらいました。
彼女は、私の小学校の同級生で、定年退職してもう何年にもなるのですが、現在もボランティアで子どもに勉強を教えています。幼なじみに近い存在ですが、私はミユキ先生と呼んで、なにかと頼りにしているのです。
もらった返事から、ちょっと抜粋してみましょう。
■「境界知能」の児童にまで手の回らない理由
たしかに「境界知能」らしき児童は教室に4人か5人はいて、その子たちに手をかけてあげたいのだけど、学習がもっとたいへんな子が1人か2人はいる。さらに、じっとしていない子、知能はとても高そうだけど問題行動の多い子もいる。
なので、一斉指導の中では両端のレベルをなんとかするのが精一杯。境界知能?の子は少人数教室や学習補助員がいるときに面倒をみてもらっているというのが現状です。
できれば、2年生から3年生までになんとかできるといいのだけれど、その学年の担任には初任者や臨時採用の教員を当てるケースが多くて、ベテランは学年に一人いるかいないかの状態。だから、ヤマトくんのご指摘通り、境界知能の子が置いていかれるのは、教師の腕もあるけど学校側の運営上の問題なんですよね…。
自分の書いたことがピント外れでなくて安心しましたが、教室の現状はやはり深刻なようですね。先生たちも大変です。
■できる子以上、天才少年少女含む?
「境界知能」はIQ(知能指数)でいうと70から85ぐらい、知的障害と平均の間の領域を指す言葉です。正規分布でいうと左端から2番目の領域です(図を参照)。では、反対側の右端に名前はあるのでしょうか?
このところ、「ギフテッド(gifted)」という言葉を見聞きすることが増えました。IQ130以上で、学問や芸術領域などに並外れた才能を発揮する、あるいは潜在的に持っている人のことをいうそうです。
俗に言う「天才」? でも、天才の場合は、必ずしもIQは問われませんから違うかもしれない。まあ、「できる子以上、天才少年少女含む」みたいなニュアンスでしょうか。
ギフテッドと境界知能の問題は、知能指数で線を引けば平均領域をはさんで右と左、反対側にありますが、共通点がいくつかあります。
両者とも近年の「発達障害ブーム」にともなって浮上してきたこと、知能検査を受ける子どもの数が増えたせいで発見したり分類したりしやすくなったこと、ともに教育現場で問題化していたが支援の狭間に置かれてきたことなどです。
ギフテッドといわれる子どもの中には、ミユキ先生が言っていた「知能はとても高いけど問題行動の多い子」も、きっと含まれているでしょう。いや、彼らはまさにその「問題行動」によって存在に気づかれるのです。
ミユキ先生はさらに言います。「若い先生方を困らせているのは、実はこっち系の子たちが多いんですよ。授業やクラスのマナーを持っていかれてしまうんです」
いったいどんな子どもたちなのでしょう?
■教師泣かせの子どもたち
小学校に入学する前から、漢字をたくさん知っている、かけ算や割り算ができる。パソコンもいじれる。恐竜の名前をたくさん覚えていたり、国旗を見せれば国の名前を言えたりで、周りからは子ども博士みたいに言われている。頭の回転が早く口達者、好奇心も旺盛。
こういう子どもっていますよね。大人からすると話していて面白いし、子どもらしさもあって可愛い。
ところが難もあって、たとえば、とても頑固で親の言うことをきかない。興味のあることには夢中になるが、やりたくないことは頑としてやらない。叱ればかんしゃくを起こしてギャン泣き。集団の中でも我を通そうとして、自分が一番でないと怒る。ときには、おともだち相手に引っかいたり咬みついたり。
こういう威勢のよい子とはまた別に、なにかと敏感で恐がりな子もいます。新しい場所や子どもが大勢いるところに連れて行くと尻込みをする。無理に仲間に入れようとすると、これまた大泣き。食べ物や着る物にも好き嫌いが多くて、偏食があったり、お気に入りの服しか着なかったり。
これらの難点は、保育園や幼稚園ではなんとかなっていたとしても、小学校にあがるとそうもいかなくなります。学校というところは、時間ごとに毎日やることが決まっているし、大勢の生徒と一緒にひとつの教室で長いこと椅子に座って授業を受けなければいけない。つまり、保育園や幼稚園に比べ、拘束される時間が増え自由度がぐっと下がるわけです。
知能の高い子は、理解が早いので授業に退屈しています。すでに知っていることも多い。漢字の書き取りだの算数の計算だの、同じ内容を繰り返しやらされる課題は苦痛です。
授業が始まると、教師の先回りをして発言したり、勝手に自前の知識を披露したりする。退屈なものだから、席を立ってウロウロしたり、ほかの生徒にちょっかいを出したりもする。
こんな子たちの行動は、たしかに教師泣かせです。生徒に「授業やクラスのマナーを持っていかれてしまう」先生たちの苦労も想像できます。しかし、こうした現象を特別な生徒の起こす「問題行動」と捉えるだけでは、「問題」を解決できないでしょう。
いっぽう、敏感で恐がりな子たちは、生徒が大勢いて騒がしい教室が苦手です。教師が大きな声で注意を与えるのを聞くと、自分が叱られているように感じてしまう。教室でゲロを吐く子を見たりしたら、わが身にも同じことが…と恐くなって授業に出られなくなってしまう。
こういう子たちは、「授業もマナーも持って行く」心配はありませんが、早々に不登校になる可能性はあるので、また別の配慮が必要です。
■子どもたちは「問題提起行動」で何を問う?
ここまで説明してきたように、知能は高いのに学校生活に適応するのは難しい子がいます。これを知能が高いゆえにと考えるか、別に社会性や行動制御などに遅れがあるせいと考えるか、意見のわかれるところです。
私は、ギフテッド問題は、HSC問題に似たところがあると感じています。HSCは“Highly Sensitive Child”の略語、「とても繊細な子」を意味する言葉です。
この概念を提唱した米国の心理学者エレイン・N・アーロンの意見は、次のようなものでした。些細なことにこだわる、引っ込み思案、臆病(おくびょう)などといった性格レベルの話で片づけられてきたが、じつは感覚刺激に過敏な体質の持ち主なのであるから、相応の配慮のもとにしつけや教育が行われなければいけない。
これはこれでいいのですが、私が気になったのは、彼女がHSCは正常の範囲内であって発達障害とは異なるものと主張した点で。私たち精神科医からすると、HSCの特徴は発達障害によくみられる「知覚過敏」の症状を切り出したもののようにも受け取れるし、両者の間に明確な線を引くことはできません。
ギフテッドの定義もまた曖昧なものですが、これを支持する人たちも、ギフテッドは発達障害ではないと盛んに主張しています。しかし、知的障害は発達障害の一部であり、境界知能をその延長と考えるならば、ギフテッドだって同根といえないでしょうか。
この子はIQが高いから、ひといちばい繊細な子だから集団に馴染めないのだ、発達障害と一緒にするなというのは、私に言わせれば「贔屓(ひいき)の引き倒し」です。妙な持ち上げ方は子どものためになりませんし、発達障害の間に線を引こうとするのは、発達障害の当事者にスティグマをもたらしかねません。
そもそも発達障害とは、知能、社会性、行動制御など社会で生きていくための力が、その子の年齢に期待されるレベルまで育っていない状態のこと。知能は高くても、子どもばかりの大きな集団の中で生活するための知恵や柔軟性が身についていなければ、学校生活で苦労するのは無理もない話なのです。
もちろん、その集団のあり方やそこで要求される「マナー」については、一人ひとりの子どもに目配りをしながら見直していく必要があります。発達障害の近縁に現れた子どもたちは、その「問題提起行動」によって「なんとかしてよ、いつまでグズグズしているの!」と大人たちに問題を突きつけているようにも思えます。