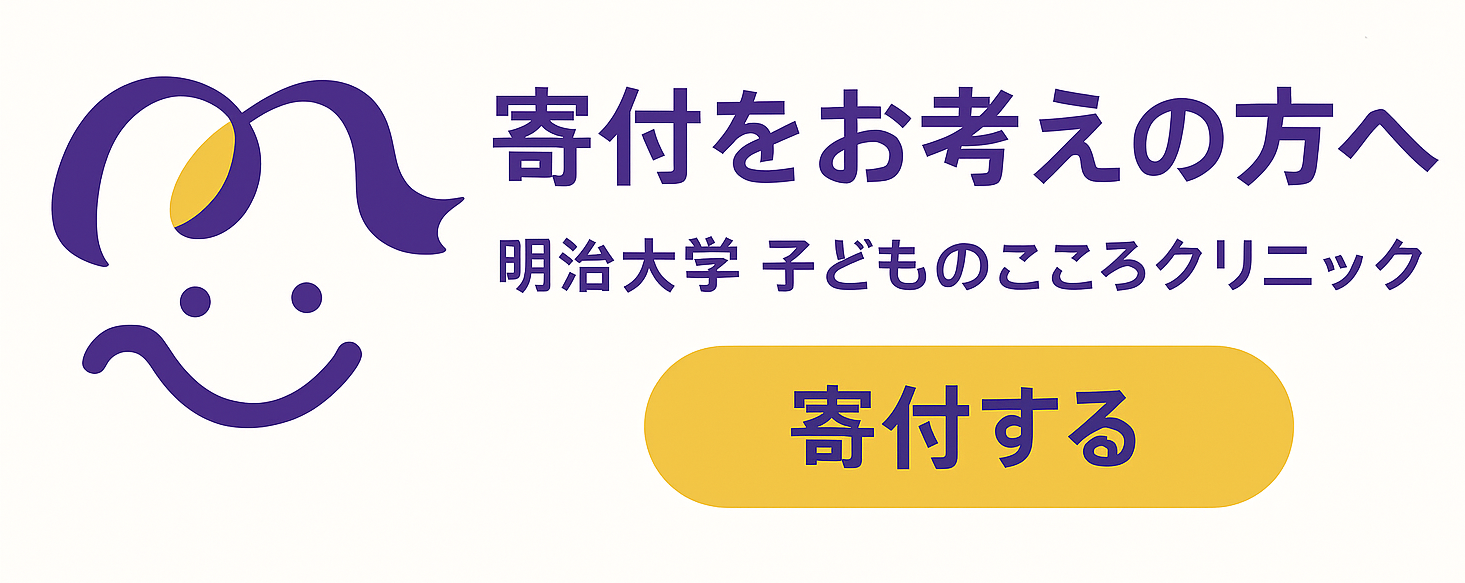「明治大学子どものこころクリニック」は、学内組織としては「明治大学心理臨床センター」の附属診療所といった位置づけになります。センターの方では、公認心理師の資格を持つ教員や相談員が心理相談(カウンセリングほか各種の心理治療)を行っています。
初代センター長の弘中正美教授(2014年退官)が専門にされていたこともあり、ここでは子どものプレイセラピーが盛んです。立派なプレイルームがあり、大学院生たちもここで臨床の経験を積みます。
プレイセラピー(play therapy)は、日本語では「遊戯療法」と訳されますが、子どもの療育や心理治療の分野では非常にポピュラーです。もっぱら就学前の幼児や小学生年齢の児童を対象に、地域の福祉センターや教育センターなどで行われています。
プレイセラピーだの遊戯療法だのという名前を聞くと、こどもを遊ばせるだけで治療になるの?と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。実際に、通院している子どもの親御さんから、似たような質問をされることもあります。
いや、たしかに子どもは遊ぶんですけど、遊ばせてるだけじゃないんですよ。セラピーというからには、方法もあれば理屈もあるんです。
■プレイセラピーの方法と効用
プレイセラピーの対象になるのは、精神発達に遅れが心配される子や情緒が不安定であつかいが難しい子などです。言葉を話さなかったり、集団に馴染めなかったり、頻繁に泣いたりかんしゃくを起こしたり、暴れたり、その他いろいろ。
そもそも、なにが不満なのか、不安なのか、子どもは話してくれません。自分の気持ちを言葉にできないから、大人があれこれ聞いても何を考えているのかわからない。
まあ、大人だって気持ちを言葉にするのは難しいこともありますが、子どもよりは上手に言葉を使って考えたり話したりできます。だから、カウンセリングが効果を生むわけです。
子どもの場合、大人の言葉に代わるのが遊びです。子どもがどんな玩具を選びどういう遊び方をするか、そこに子どもの感情が投影されます。遊びの中に象徴的に表現されるそれを、セラピスト(多くは心理師)は読み取ります。
プレイセラピーはおもに精神分析学の分野で発展してきたのでこういう考え方になるのですが、セラピストは子どもと遊びながら、子どもを観察し解釈を重ねていくのです。
セラピーの頻度は週に1回とか月に1回とかケースによりますが、毎回同じ遊びを続ける子や回によって遊びを変える子など、子どもによっていろいろです。
なにをやって遊ぶか決めるのは子どもです。とはいえ、自分では決められない子もいます。そういう子には、セラピストの方から、これやってみる?と誘うこともあります。
また、プレイセラピー自体に抵抗し、座り込んで漫画を読んでいるだけなんて子もいます。セラピスト泣かせですが、回を重ねるうちに遊べるようになることもあるので、ここは根くらべです。
プレイルームでは、子どもやセラピストが怪我するような危ないことをしない限り、どう遊ぼうが自由です。ただし、終わりの時間は守る、プレイルームの備品やプレイの時間に作ったものは家に持ち帰らないなどルールはあります。
このような大きな枠のなかで、セラピストは子どもが思い切り遊べるように配慮しながらともに遊び、二人の間に信頼関係を築いていきます。
セラピーは数ヶ月から数年単位で続くのが一般的です。子どもが遊んでいる時間を使って(だいたい1回30分から60分の間)、別の心理師が親の相談を担当します。親の話を通して家庭や学校での子どもの様子を知り、日常生活とプレイルームで見られる姿とすりあわせる作業も必要です。
いかがでしょう。プレイセラピーの進め方やセラピストの仕事ぶりをざっとご紹介しただけでも、ただ遊んでいるだけじゃないことがおわかりいただけたと思うのですが。
私自身はプレイセラピーをやりませんが、なにより良いと思うのは、これが子どもの自然の力を生かした方法であることです。侵襲性も少なく安全なところもよい。薬は脳に効きますが、子どもをおとなしくさせるだけ。遊びは心に効いて、子どもを育てます。
■プレイセラピーと「リアリティ」
弘中正美先生は、「遊びについて」という文章の中で「子どもが遊びに興じるとき、そこには強烈なリアリティが生じる」と書いておられます(弘中正美・編著『心理臨床における遊び~その意味と活用』、遠見書房、2016年)。どういうことでしょうか。
私は先生から直々に次のようなご講義を受けました。
たとえば、ここがプレイルームだとして、子どもとかくれんぼしようということになったとする。常識からしたら、こんなところで隠れたってすぐに見つかってしまう。大人なら、かくれんぼなんて成立しないよと思う。
ところが、実際に始めてみると、子どもはどこか身を潜める場所を見つけ出し、そこで体を半分震わせながらじっとしている。そして、こちらがなかなか見つけられないふりをしてみせると、クスクス笑い声をあげたりわざとボールを転がしたりする。
そんなことをして最後に「ここだ!」と見つけると、子どもはワーッとものすごく興奮した状態で出てきて、「もう一回やろう!」なんて言う。
これはもう実際に大人が考えるレベルを越えて、子どもはすっかり本気になっている。見つけられるのが半分嬉しい、半分怖い、そんな感情をむき出しにしてかくれんぼに夢中になっているのだ。
これこそ子どもが遊びの中で見せる「リアリティ」である。プレイセラピーというのは、この種のリアリティによって成立している。
と、弘中先生は、こんなふうにおっしゃっていました。私の理解したところによると、ここでいう「リアリティ」とは生き生きとした生の瞬間、あるいは、そのとき子どもが見せる生のエネルギーのことではないか。まさに、遊びせんとや生まれてきた子どものナマの姿が、そこに見て取れるというわけです。
だとしたら、次のような言い換えも可能かもしれません。すなわち、プレイセラピーとは、子どもが遊びの中で見せるリアリティをよりどころにして、その子本来の生きる力を引き出し、あるいは伸ばししながら、困難を乗り越えていけるよう支援することである。