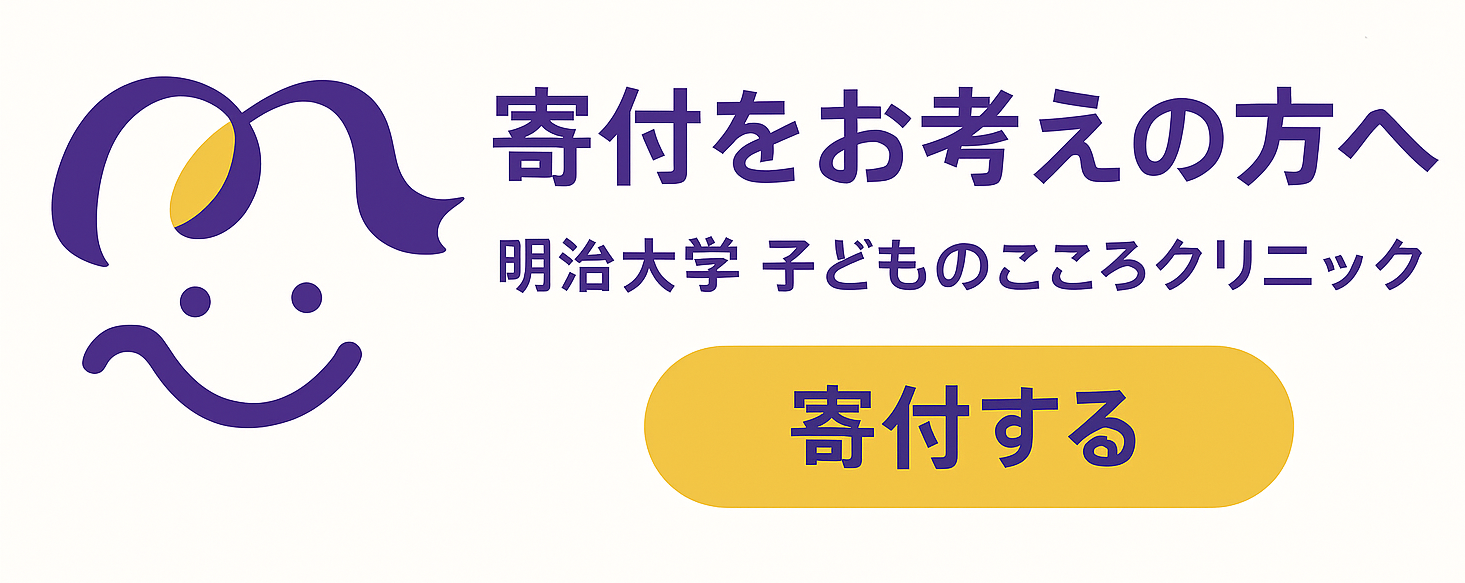明治大学心理臨床センター
心の悩みに関するご相談をお受けします
Go Forward
令和8年1月15日 当院は、おかげさまで開院5周年を迎えました
■ほめ方、叱り方をどうするか 親にとって悩ましい問題
「子どもはほめて育てよ」というのは先人の教えですが、これに対し、「ほめてばかりでいいのか」「叱ったらダメなのか」といった疑問や反論がよく聞かれます。
しかし、ほめることと叱ることは矛盾しません。子どもにはしつけが必要ですから、いけないことや危ないことをしたときには叱ってでもやめさせなければいけません。
ただ、子どもは大人たちの肯定的なまなざしの中にあってこそ、まっすぐに育つのであって、そういう意味では、ほめられる機会の多い子は幸せでしょう。反対に、しょっちゅう叱られている子どもは、むくれたり、すねたり、ひねくれたりで、今時の言い方をすれば、「自己肯定感の低い子」になってしまうかもしれない。
今さら言われなくても…という話でしょうが、とはいえ、子どもがいろいろなら親もいろいろ。ほめたくてもほめ方がよくわからない、いくら言ってもきかないので、ついきつく叱ってしまう、かわいい子どもを叱りたくない、でもこのままでは……と悩む親御さんも少なくないのでは。
ペアトレは、子どもの「行動」に注目し、好ましい行動を増やし、好ましくない行動や危ない行動を減らすためのテクニックを学ぶプログラム。基本は、好ましい行動が見られたら「ほめる」、好ましくない行動は叱る代わりに「無視する」。具体的にはどんなことをするのか、このあと順に見ていきましょう。
■気づきや感謝も「ほめる」につながる効果あり
親が子どもに望む好ましい行動とは、いずれは自主性や社会性の獲得につながる行動といってもいいでしょう。そのごく初期段階として、歯磨きが一人でできる、おうちのお手伝いをする、きょうだい仲良くする——なんて目標がある。だから、それができたときに、よくできたね、エライね、いい子だねとほめるわけです。
よくできたときにほめるのはもちろんですが、できていることに気づいたら一声かけてやるのも大事。「おはよう、あ、歯磨きしてる!エライ、エライ」。また、手伝いをしたときや役に立ったときなどには、感謝の言葉を忘れずに。「ちょっと、そこのお塩とって。うん、ありがとう」
こうした親の気づきや感謝の言葉があると、子どもは親に関心を向けてもらえた、喜んでもらえたと感じますから、そのときの行動は、ほめられたのと同等の価値を与えられたことになります。その積み重ねによって、好ましい行動は定着し増えていくのです。
■重要なのはタイミング、具体的な言葉、余計なコメントは加えない……
ペアトレでは、ほめるときのポイントをいくつか挙げています。
たとえば、タイミングを逃さず即座にほめる、何ができて良かったかを具体的に言葉で伝える、ほめた言葉に批判や余計なコメントを足さない、子どもの性格や年齢にあったほめ方をするなどです。
ペアトレはアメリカ生まれのせいか、「子どもの近くに寄って、目を見て、表情豊かに明るい声で」なんてアドバイスもある。これが自然にできる人はいいんですが、「そんなのわざとらしくて、ちょっと……」と抵抗を感じる人もいるでしょう。子どもの性格を考えたら、大げさにほめられるのが恥ずかしい子だっているに違いありません。
コミュニケーション全般にいえることですが、自分に似合わないやり方では伝えたいことも伝わらないし、受け取る方にも抵抗が生まれます。子どもには肯定的注目が大事、という基本を押さえてあれば、あとは無理せず自己流で、という姿勢で良いと思います。
■「叱る」より効果的な方法は「無視」
ほめ方に増して難しいのは効果的な叱り方です。
叱るだけなら簡単。でも、好ましくない行動をやめさせる効果的な叱り方というのはあるのでしょうか。
昭和の時代なら、聞き分けのない子にはゲンコツを食らわすか、晩飯を食わせないか、押し入れに放り込むかすればよかったんでしょうが、いまはどれもNG!児童虐待!ですからね。いや、実際のところ、こんなことをしたって、子どもは自尊心が傷つくわ、親に恨みを持つわで良いことはない。
ペアトレでは叱り方については教えてくれません。好ましくない行動をやめさせるには、叱る代わりに「無視」を使います。
無視?見て見ぬふり? そんなことでやめさせられるの?と思いますよね。でも、これにはちゃんとした理屈があるのです。
「強化子(reinforcer)」については、すでに説明しましたが、これは人間のある行動の頻度を高める刺激のこと。そして、子どもの行動を変える効果的な強化子は、なにより大人の注目である、という話でしたね。
この注目には、肯定的なものも否定的なものもあって、どちらも子どもの行動を強化する働きがあります。「ほめる」は前者、「叱る」は後者、ほめればほめられた行動が増えるし、叱れば叱られた行動が続いてしまう。
だから、子どもの好ましくない行動をやめさせるには、否定的な注目を取り去ること、すなわち「無視」が有効な方法である。これが行動分析学の教えるところです。
ここで「無視」の対象になるのは、あくまで子どもの好ましくない「行動」であって、子ども「本人」ではありません。それに、無視しっぱなしではいけません。その後の子どもの行動にも着目し、良い変化が現れたらすぐにほめる。つまり、これは「無視」、「待つ」、「ほめる」が3点セットになったテクニックなのです。
■「無視作戦」を実行に移す
実行にあたっては、どの行動を無視するか、ターゲットにする行動をあらかじめ見定めておきます。そして、その行動が出たら、すぐに無視作戦開始!
まず、視線だけでなく体ごと子どもの方を向かないようにして無関心を装いましょう。子どもはギャアギャア言うでしょうが、ここは感情を顔に出さないこと。感情を抑えるためには、なにか他のことに注意を向けると良いかもしれません。
子どもは親に無視されると、かえって困ったことをしたり、「無視すんな!」と怒ったりするでしょう。でも、「無視」によって困った行動が一時的に増えるのは想定内。ここは我慢が肝心です。気持ちを平静に、穏やかにキープしましょう。ため息をついたり、舌打ちしたり、は厳禁!です。
どうですか?難しそう? 自分であげておいてなんですが、この絵、スーパーマーケットでガムをねだる子の例、これは結構キビシイですよね。「無視」のターゲットにする行動としては上級者向きだったかもしれません。アメリカの事情はよく知りませんが、日本には「世間様の目」というものがありますから、ワンワン泣く子をかたわらに、平然と野菜なんか選んでいられませんよ。
こういうときは店から引きずり出してかまわないと思いますが、店の外に出てから長々と説教しない、家に帰ったらおやつを食べさせる……など気遣いが必要でしょう。そして、次に挑戦するときは、家の中で実行できそうな行動を選ぶことをお勧めします。