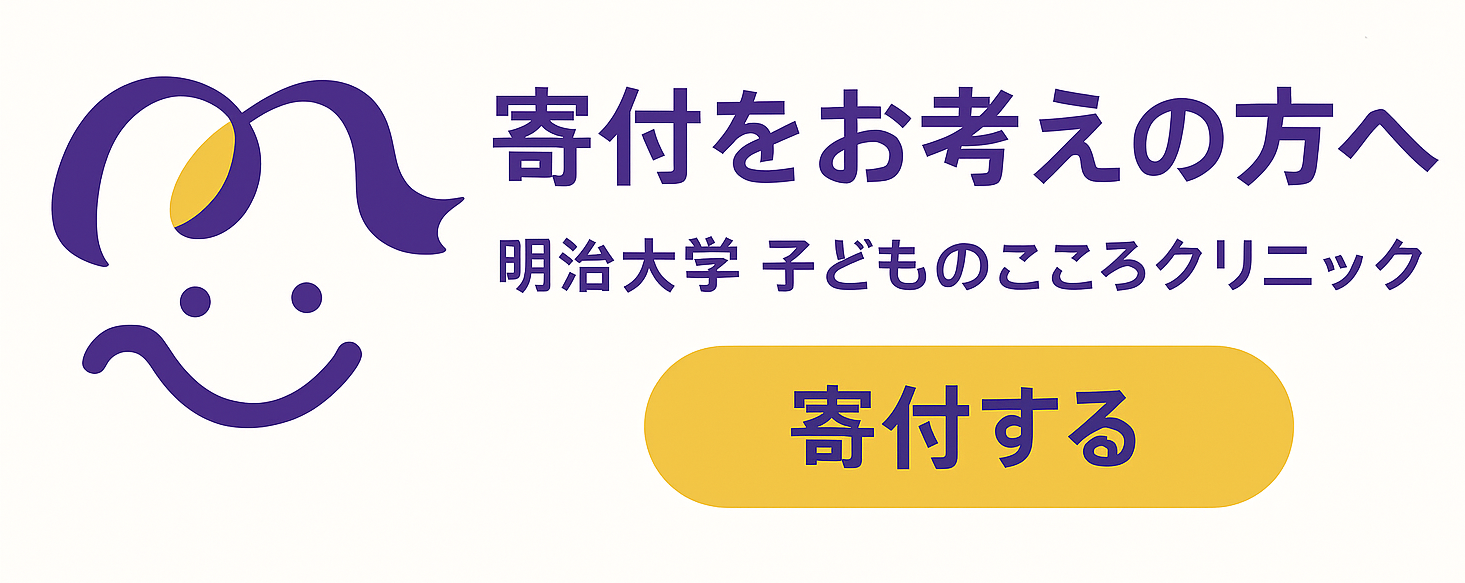明治大学心理臨床センター
心の悩みに関するご相談をお受けします
Go Forward
令和8年1月15日 当院は、おかげさまで開院5周年を迎えました
■ペアトレは現代版「しつけ方教室」?
ペアレント・トレーニング(以下ペアトレ)は、1960年代に米国で誕生し発展を遂げた心理教育的アプローチです。日本では、1990年代から発達障害が増加したことも手伝って、療育機関や医療機関などで盛んに行われるようになりました。
私たちのクリニックでも、公認心理師が中心になって年に2シーズン、1シーズン8回のプログラムを行っています。参加メンバーは、通院する子どもたちの親御さんから希望者を募ります。シーズンごとの入れ替え制で、だいたい各回あたり4、5人がいらしています。
プログラムは、心理師による講義とメンバー同士の経験の分かち合いからなり、メンバーには毎回宿題も出ます。講義のテーマは、子どもの困った行動や危ない行動を減らし、好ましい行動を増やすにはどうしたらよいかです。そして、そのコツをお教えいたしましょう!というわけですから、ペアトレというのは言ってみれば「上手なしつけ方教室」みたいなもの。
いや、こんな乱暴なまとめ方をすると心理師の皆さんに叱られてしまうかもしれません。でも、ユーザー側のニーズからすれば、あながち間違いではないと思います。
核家族化や共同体の解体が進んだこんにちでは、しつけの文化は上の世代から下へと伝わりにくくなりました。それに、時代も変わって、昔あたりまえだったやり方も、今では児童虐待と紙一重、なんてこともなくはない。
そんな世の中、子育てに悩む親たちが増えるのも無理はありません。ペアトレは、そんな時代のニーズに応える方法のひとつと言ってもよいでしょう。
■親子の間に生じがちな「悪循環」を断つ
医療機関で行われるペアトレは、だいたいが注意欠如多動症(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)などの発達障害を持つ子どもの親を対象にしています。しかし、障害の有る無しに関わらず、親子の日常的なやり取りの中で起こりがちな悪循環を断ち、親子関係を健全化するのにも役立ちます。
この「悪循環」とはどういうことをいうのでしょう。
たとえば、子どもがゲームに夢中になって、いつまでたっても風呂に入らないとします。親は叱ってゲームをやめさせようとする。ところが、子どもが言うことをきかない。
そこで、親はより強く叱ったりゲーム機を取り上げたりして言うことを聞かせようとします。すると、子どもはますます反発してかんしゃくを起こす。
こんな親子のやりとりが次第にエスカレートして、家は子どもの泣き叫ぶ声や親の怒鳴り声が飛び交う修羅場に…なんて言ったら言い過ぎですが、これがパターン化しているとしたら「悪循環」と言えませんか。
こうしたことは、子どもが発達障害であってもなくても起きて不思議はありません。目の前のことに気を取られ、やらなきゃいけないことがどんどん後回しになる。好きなことに夢中になるとやめられなくなる。反対に、やりたくないとなったら断固やらない。親が口を出せばかんしゃく玉を破裂させる。そんな子どもはいくらもいるでしょう。
ただ、発達障害を持つ子やその近縁の子は、とくにそんな傾向が強いといえます。育てる親にしたら、なかなか手強い相手です。そういう、いわばしつけに手のかかる難しい子に対しては、どんなやり方が有効なのか。
まず、考えておくべきは、ターゲットは子どもの「行動」であって、性格や特性ではないということです。「その曲がった根性をたたき直してやる!」というのは、昭和の時代の野蛮で間違った考え方。でも、「何度言ったらわかるの!」「おまえはどうしていつもそうなんだ!」なんていうのも、どっちかって言うとその類いですね。つい言っちゃってませんか?
ペアトレでは、上に述べたように、子どもの困った行動、危ない行動を減らし、好ましい行動を増やすことを目標に、それぞれの行動にあった対応のテクニックが学べます。大事なのは、やめさせたい困った行動より先に、増やしたい好ましい行動に注目すること。ここが肝心です。
慌てて言っておきますが、じゃあ、ゲームはやらせ放題、風呂は入りたいときに入らせたらいいの?って話ではありませんよ。そっちはそっちで並行してやっていかないといけません。畑をしっかり耕しながら雑草も刈り取りましょうと… いや、これはちょっとたとえが違うか。
■「肯定的な注目」が子どもの困った行動を減らす
子どもでも大人でも、人間は注目されることを求めています。心理学の教えるところでは、他者からの注目は非常に強力な「強化子(reinforcer)」として働くといいます。
強化子は、行動分析学や学習理論など心理学の領域で使われる用語で、行動の頻度を高める環境からの刺激を指します。ある行動の頻度を上げたければ、そのあとに強化子を提示するのが効果的です。
話が理屈っぽくなって恐縮ですが、ペアトレのプログラムはこの理屈に基づいて作られているんですね。子どもは大人以上に周囲からの注目を必要としていますから、子どもにしてほしい行動を増やし、してほしくない行動を減らすためには、まわりの大人たちがその子にどのような注目を向けるか、すなわちどんな強化子を与えたら良いかが鍵になります。
子どもの中には、肯定的注目が得られないとなると、トラブルを引き起こしてでも注目を得ようとする子がいます。否定的な注目も注目に変わりありません。ですから、親を怒らせるようなことばかりする子や叱ってもふざけてばかりいる子は、じつはなじみのやり方で手っ取り早く注目を得ようとしているとも考えられるのです。
この場合、子どもはわざと悪い子になっているわけではないので罪はないはずですが、大人が好ましくない行動にばかり注目すると、かえってそれが増える結果につながりかねません。反対に、好ましい行動の方に肯定的な注目を向け、ほめることを繰り返していくと、その行動がどんどん増えていき、相対的に好ましくない行動や危険な行動が減ってきます。
注目されたら子どもは嬉しい、ほめられたらなお嬉しい、自分でできるようになったらもっと嬉しい。そういう好循環を作っていけたら、子どもは自信を持てるようになるし、指示されたことにも協力するようになる。これがペアトレの教えです。