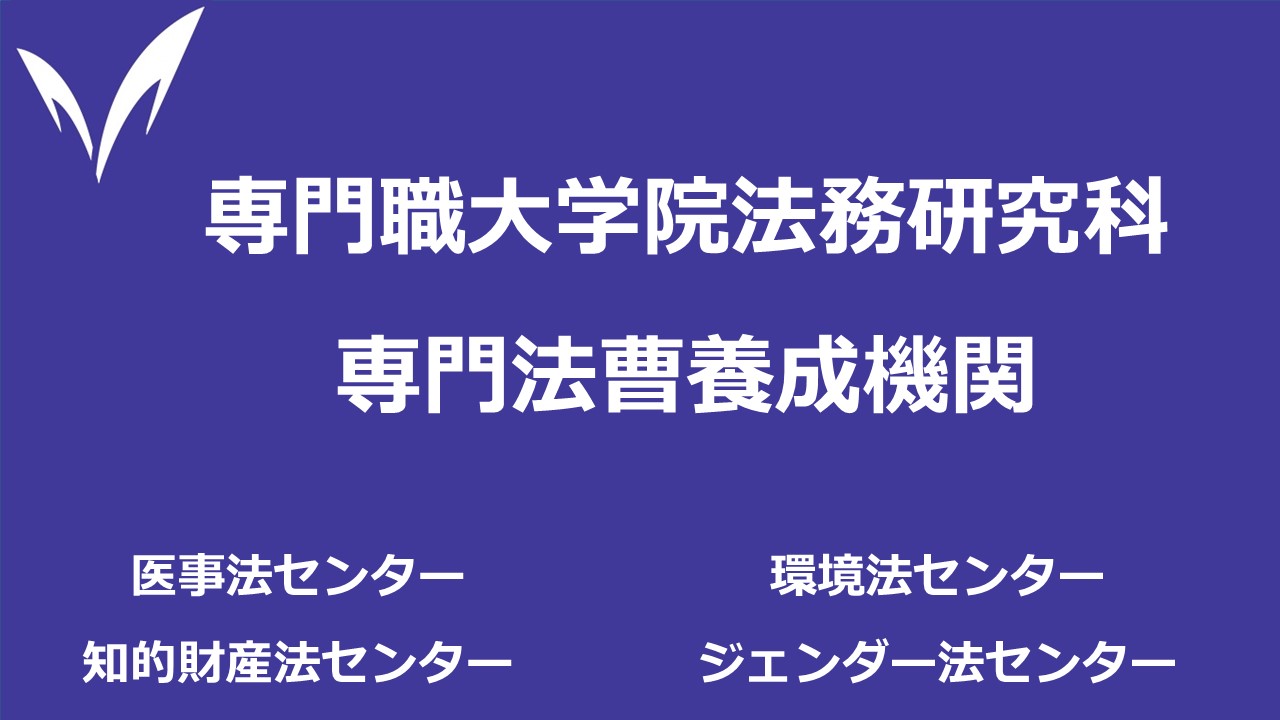2026年02月03日
以下の各履修イメージを参考にして、各自の履修計画に基づき単位を修得してください。
なお、パターンごとに履修すると望ましい科目を列挙していますが、各自の興味やイメージする進路にあわせて主体的に科目を選択してください。
※ 各科目の開講状況及び配当学年は、年度によって変更になることがあります。
パターン1 社会における人間の権利擁護に向き合う法曹を目指す人
女性や社会的マイノリティの人権、雇用、家族(婚姻・離婚等)、消費者保護など、社会と人間の問題に真摯に向きあう法曹が求められています。この分野で活躍するために、展開・先端科目群の「ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ」では、憲法の平等原理、違憲審査基準論や、家族法、労働法(男女雇用機会均等法など)、 刑法、DV防止法、ストーカー規制法等の関連部分まで、科目横断的にジェンダーの視点で再検討し、LGBTQの権利なども含めて、様々な差別や格差が存在する現代社会の法律問題について研究します。また、「労働法」「消費者法」「医事・生命倫理と法Ⅰ・Ⅱ」等を履修して社会的弱者の問題に向きあう科目について学びます。
1年次:「ジェンダーと法Ⅰ」、「法情報調査」、「司法制度論」
2・3年次:「ジェンダーと法Ⅱ」、「少年法」、「法社会学」、「労働法」、「憲法展開演習」、「民法展開演習」、 「商法展開演習」、「刑法展開演習」、「刑事訴訟法展開演習」、「模擬裁判(民事)」、「ローヤリング」、「医事・生命倫理と法Ⅰ・Ⅱ」、「消費者法」、「国際法」、「国際人権法」
1年次:「ジェンダーと法Ⅰ」、「法情報調査」、「司法制度論」
2・3年次:「ジェンダーと法Ⅱ」、「少年法」、「法社会学」、「労働法」、「憲法展開演習」、「民法展開演習」、 「商法展開演習」、「刑法展開演習」、「刑事訴訟法展開演習」、「模擬裁判(民事)」、「ローヤリング」、「医事・生命倫理と法Ⅰ・Ⅱ」、「消費者法」、「国際法」、「国際人権法」
(野川忍先生)
パターン2 医事法に強い法曹を目指す人
医療──それは私たちの日々の生活に無くてはならない営みです。その医療をめぐってさまざまな社会的な問題が生じます。典型例が医療事故や薬害です。医療事故や薬害により被害を受けた人が生じた場合、その方々の被害を回復させるための法的な支援、あるいは責任追及を受けた医療関係者への法的な支援が必要となります。それだけではありません。感染症に罹患したことによって生じるさまざまな人権侵害、心ない患者やその家族から医療関係者に対してしばしばなされる暴力やハラスメント、医療関係者の過労死なども現在の医療現場では深刻な問題となっています。医事法に強い法曹を目指す方は、以上のような問題について公法・私法を問わず多角的に検討できる視点を身につけることが必要となります。
さらにこの領域で活躍する法曹には、医療関係者への法学教育、行政府や立法府に対する政策提言の役割なども求められることがしばしばあります。そこで、生殖補助医療・終末期医療・救急医療・再生医療など政策と行政が密接に関わってくる事例を通じて、政策と制度と法との関係や、法の限界について学び考えることも重要なポイントになります。
ご存知の通り、医事法は試験科目ではありません。それゆえ“履修してもムダ”と感じるかもしれません。しかし、相当程度の生存可能性・期待権・不作為不法行為などの不法行為法領域で近年注目を集めている議論は、いずれも医療事故訴訟の場で最初に展開されたものです。また合格するために必要不可欠なスキルのひとつである裁判例(特に事実関係)を読み解く能力は、医療事故訴訟のような難しい判決文に接すればこそレベルアップも可能となります。“履修してもムダ”ではありません。無駄と感じるか、あるいは無駄にしてしまうかは、すべて貴方次第です。
1 年 次:基本3科目+「司法制度論」、「法と公共政策」、「法情報調査」
2・3年次:「医事・生命倫理と法Ⅰ・Ⅱ」、「憲法展開演習」、「行政法展開演習」、「民法展開演習」、「刑法展開演習」、「民事訴訟法展開演習」、「刑事訴訟法展開演習」、「法曹実務演習1」
さらにこの領域で活躍する法曹には、医療関係者への法学教育、行政府や立法府に対する政策提言の役割なども求められることがしばしばあります。そこで、生殖補助医療・終末期医療・救急医療・再生医療など政策と行政が密接に関わってくる事例を通じて、政策と制度と法との関係や、法の限界について学び考えることも重要なポイントになります。
ご存知の通り、医事法は試験科目ではありません。それゆえ“履修してもムダ”と感じるかもしれません。しかし、相当程度の生存可能性・期待権・不作為不法行為などの不法行為法領域で近年注目を集めている議論は、いずれも医療事故訴訟の場で最初に展開されたものです。また合格するために必要不可欠なスキルのひとつである裁判例(特に事実関係)を読み解く能力は、医療事故訴訟のような難しい判決文に接すればこそレベルアップも可能となります。“履修してもムダ”ではありません。無駄と感じるか、あるいは無駄にしてしまうかは、すべて貴方次第です。
1 年 次:基本3科目+「司法制度論」、「法と公共政策」、「法情報調査」
2・3年次:「医事・生命倫理と法Ⅰ・Ⅱ」、「憲法展開演習」、「行政法展開演習」、「民法展開演習」、「刑法展開演習」、「民事訴訟法展開演習」、「刑事訴訟法展開演習」、「法曹実務演習1」
(小西知世先生)
以下8つのパターンは、展開・先端科目群の司法試験選択科目を履修するにあたり、入学後に履修することが望ましい科目を列挙してあります。
また、担当教員からのアドバイスやメッセージが寄せられています。
パターン3 倒産法
法律実務家、とりわけ弁護士は、倒産という社会現象に様々な形でかかわります。管財人や監督委員として倒産手続に直接かかわらなくても、一方では、取引先が倒産して債権回収が困難となった人々、他方では、収入や資産が乏しくなって債務の弁済が困難となり倒産手続の利用を考慮している人々から、相談を受けることがしばしばあります。さらに、企業買収などの事業再編スキーム(M&A)を検討するにあたっても、倒産法の知識が必須です。
倒産法を勉強しようとする場合、その中心的科目は講義としての「倒産法」(4単位)と「倒産法総合演習」(2単位)です。倒産法は、民事法の集大成といわれるように、民法、商法、民事訴訟法、民事執行・保全法の知識が前提となります。したがって、倒産法の講義及び演習の履修は、2年次秋学期または3年次にすることをお勧めします。ただし、講義については、意欲ある方の2年次春学期の履修を拒むものではありません。
この点で、選択科目としての負担が軽いとはいえません。しかし、倒産法を学べば、逆に、民事法分野全般にわたって理解を深めることができます。とくに、民法の担保権の意義・機能については、倒産法を学ぶことで、はじめて深く理解することができます。なお、法律だけでなく、内外の経済や社会の動きにも関心をもつよう、心がけてください。
2・3年次:「倒産法」、「倒産法総合演習」、「民事執行・保全法」、「金融商品取引法」、「消費者法」等
倒産法を勉強しようとする場合、その中心的科目は講義としての「倒産法」(4単位)と「倒産法総合演習」(2単位)です。倒産法は、民事法の集大成といわれるように、民法、商法、民事訴訟法、民事執行・保全法の知識が前提となります。したがって、倒産法の講義及び演習の履修は、2年次秋学期または3年次にすることをお勧めします。ただし、講義については、意欲ある方の2年次春学期の履修を拒むものではありません。
この点で、選択科目としての負担が軽いとはいえません。しかし、倒産法を学べば、逆に、民事法分野全般にわたって理解を深めることができます。とくに、民法の担保権の意義・機能については、倒産法を学ぶことで、はじめて深く理解することができます。なお、法律だけでなく、内外の経済や社会の動きにも関心をもつよう、心がけてください。
2・3年次:「倒産法」、「倒産法総合演習」、「民事執行・保全法」、「金融商品取引法」、「消費者法」等
(大橋眞弓先生)
パターン4 租税法
租税法は、租税をめぐる法律関係を扱いますが、それを規律する法律として、国税通則法のような通則的法律のほか、所得税法や法人税法のような多数の個別法律からなっています。司法試験の出題範囲は、国税通則法、所得税法及び法人税法となっています。そして、所得税法や法人税法は、取引行為や財産を課税の対象とするために、民法、会社法のような民事関係の基本的法律を確実に理解しておく必要があります。また、租税の課税・徴収の手続や課税をめぐる争いの解決には行政救済法の知識が不可欠です。その意味において、まさに複合的な「展開・先端科目」です。
企業も個人も租税のことを離れて意思決定をすることはできないようになってきました。たとえば、財産の譲渡契約の締結に当たって、譲渡利益に対する課税がどうなるのか、離婚の際の財産分与や慰謝料に関してどのような租税上の扱いになるか、企業利益に対してはどの程度の租税が課されるのかなどについて、十分な知識をもっていなければなりません。それゆえ、通常の民事の法曹として生きていくのにも、租税法の基本的知識が不可欠なのです。
そこで、「租税法Ⅰ」、「租税法Ⅱ」、「租税法総合演習」は当然のこととして、それ以外にも、民商法科目や行政法関係科目はしっかりと勉強をしておいてください。
2・3年次:「租税法Ⅰ・Ⅱ」、「租税法総合演習」、民商法科目、行政法関係科目
企業も個人も租税のことを離れて意思決定をすることはできないようになってきました。たとえば、財産の譲渡契約の締結に当たって、譲渡利益に対する課税がどうなるのか、離婚の際の財産分与や慰謝料に関してどのような租税上の扱いになるか、企業利益に対してはどの程度の租税が課されるのかなどについて、十分な知識をもっていなければなりません。それゆえ、通常の民事の法曹として生きていくのにも、租税法の基本的知識が不可欠なのです。
そこで、「租税法Ⅰ」、「租税法Ⅱ」、「租税法総合演習」は当然のこととして、それ以外にも、民商法科目や行政法関係科目はしっかりと勉強をしておいてください。
2・3年次:「租税法Ⅰ・Ⅱ」、「租税法総合演習」、民商法科目、行政法関係科目
(岩﨑政明先生)
パターン5 経済法
【経済法・独占禁止法分野に強い法曹を目指す人】
経済法の中心は独占禁止法です。この法律は、条文数は少ないですが、具体的事案の検討を通じて条文に係る要件・効果を理解する必要性が高いので、常に新しい審決・判決・公正取引委員会が公表しているガイドラインに注意を払う必要があります。経済法は、学際領域の問題が幅広く関わってきますので、ビジネスに関連する幅広い知識に精通するほど、実務上の強みとなります。例えば、企業結合規制に関しては、M&Aに関する商事法の知識の習得が勧められます。近時は、デジタル経済の問題が独禁法の執行の主要分野となっていますので、知的財産法・個人情報保護法の知識が強みとなります。消費者利益の観点からは、消費者法についての知識が強みとなります。独禁法は、カルテルを中心に、欧米アジアでの訴追が頻繁に行われており、国際的執行についての知識、外国法の知識が実務に役立ちます。さらに、独禁法の執行は、公取委による行政手続のほか、私人により民事手続きを通じて行われ、時には、刑事手続による執行も行われますので、行政法、民事法、刑事訴訟法についての知識を固めることも重要です。展開演習では、これらの学際分野・比較法分野を意識した指導が行われます。「企業実務と法Ⅰ」は、M&Aに関連する知識の習得に役立ちます。
1 年 次:「法情報調査」
2・3年次:「経済法」、「独占禁止手続法」、「経済法総合演習」、「経済法演習」、「展開・先端系総合指導(経済法)」、「金融商品取引法」、「企業実務と法Ⅰ」
経済法の中心は独占禁止法です。この法律は、条文数は少ないですが、具体的事案の検討を通じて条文に係る要件・効果を理解する必要性が高いので、常に新しい審決・判決・公正取引委員会が公表しているガイドラインに注意を払う必要があります。経済法は、学際領域の問題が幅広く関わってきますので、ビジネスに関連する幅広い知識に精通するほど、実務上の強みとなります。例えば、企業結合規制に関しては、M&Aに関する商事法の知識の習得が勧められます。近時は、デジタル経済の問題が独禁法の執行の主要分野となっていますので、知的財産法・個人情報保護法の知識が強みとなります。消費者利益の観点からは、消費者法についての知識が強みとなります。独禁法は、カルテルを中心に、欧米アジアでの訴追が頻繁に行われており、国際的執行についての知識、外国法の知識が実務に役立ちます。さらに、独禁法の執行は、公取委による行政手続のほか、私人により民事手続きを通じて行われ、時には、刑事手続による執行も行われますので、行政法、民事法、刑事訴訟法についての知識を固めることも重要です。展開演習では、これらの学際分野・比較法分野を意識した指導が行われます。「企業実務と法Ⅰ」は、M&Aに関連する知識の習得に役立ちます。
1 年 次:「法情報調査」
2・3年次:「経済法」、「独占禁止手続法」、「経済法総合演習」、「経済法演習」、「展開・先端系総合指導(経済法)」、「金融商品取引法」、「企業実務と法Ⅰ」
(越知保見先生)
パターン6 知的財産法
「知的財産と法」を中心に、展開・先端科目群の中から「経済法」「独占禁止手続法」等を選択します。「知的財産と法Ⅰ」では、特許法を中心に、知的財産法の概論を講義するとともに、知的財産法と先端技術(インターネット、ライフサイエンス等)との関係や、知的財産に関する国際ルールのあり方等についても考察します。また、「知的財産と法Ⅱ」では、著作権法を中心に、実例に基づき、著作権法における保護の詳細について分析します。知的財産法は、公法的側面と私法的側面を併せ持つとともに、実体法的側面と手続法的側面も併せ持つものですから、民法、民事訴訟法等の基本科目で学んだ「知識」を活用する「知恵」が必要です。また、知的財産の客体が技術的なものから文化的なものまで幅広いため、いろいろなことに「知的好奇心」を持つことも大切です。
知的財産法の体系を理解するとともに、知的財産に関する紛争防止(管理)のために、「知恵」を絞り、「知的好奇心」を高めるように日々努力するようにしてください。
1 年 次:「法情報調査」、「立法と政治」
2・3年次:「知的財産と法Ⅰ・Ⅱ」、「知的財産法総合演習」、「展開・先端系総合指導(知的財産法)」、「法曹実務演習1・2」、「法社会学」、「法と公共政策」、「経済法」、「独占禁止手続法」
知的財産法の体系を理解するとともに、知的財産に関する紛争防止(管理)のために、「知恵」を絞り、「知的好奇心」を高めるように日々努力するようにしてください。
1 年 次:「法情報調査」、「立法と政治」
2・3年次:「知的財産と法Ⅰ・Ⅱ」、「知的財産法総合演習」、「展開・先端系総合指導(知的財産法)」、「法曹実務演習1・2」、「法社会学」、「法と公共政策」、「経済法」、「独占禁止手続法」
(淺見節子先生 熊谷健一先生)
パターン7 労働法
【企業法務の一環である労働法に強い法曹を目指す人】
労働法は、憲法を頂点とする実定法体系の重要な一分野であり、また民法、民事訴訟法、行政法等の基本法を土台として展開する先端的な専門法分野に属します。特に21世紀になってからは、労働法の分野に属する法制度が大変重要な地位を占め、またいっそう見逃せない機能を果たすようになっており、その十分な理解は、法曹を目指す人には不可欠の素養であると言えます。2018年に開始されたいわゆる「働き方改革」も、36本もの実定法の改正を伴う法制度の大改革であり、今後も労働法の重要性がますます大きくなることが予想されます。労働法を学ばずして、現代社会に的確に対応することは不可能であると言っても過言ではありません。
以上のような観点から、まずは民法を中心として基本科目の素養を身につけることが、労働法の理解のためには不可欠となります。労働法を受講する場合は、2年生までにこれら基本科目の素養を身につけたうえで、3年生になってから参加することをお奨めします。
また、労働法は企業組織再編などに不可欠の法務分野として会社法制と深い関わりを有しており、企業実務に関する法的素養があることは、労働法の理解に非常に役立ちます。他方で労働法は、いわゆる「社会法」の中心的領域を形成していますので、「ジェンダーと法」、「消費者法」などの履修が非常に役立ちます。社会法分野については、このうち「ジェンダーと法」を含む二つ程度は履修しておくよう薦めます。
1 年 次:「法と公共政策」
2・3年次:「労働法」、「労働法総合演習」、「展開・先端系総合指導(労働法)」、「企業実務と法Ⅰ・Ⅱ」、「ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ」、「法社会学」、「消費者法」
労働法は、憲法を頂点とする実定法体系の重要な一分野であり、また民法、民事訴訟法、行政法等の基本法を土台として展開する先端的な専門法分野に属します。特に21世紀になってからは、労働法の分野に属する法制度が大変重要な地位を占め、またいっそう見逃せない機能を果たすようになっており、その十分な理解は、法曹を目指す人には不可欠の素養であると言えます。2018年に開始されたいわゆる「働き方改革」も、36本もの実定法の改正を伴う法制度の大改革であり、今後も労働法の重要性がますます大きくなることが予想されます。労働法を学ばずして、現代社会に的確に対応することは不可能であると言っても過言ではありません。
以上のような観点から、まずは民法を中心として基本科目の素養を身につけることが、労働法の理解のためには不可欠となります。労働法を受講する場合は、2年生までにこれら基本科目の素養を身につけたうえで、3年生になってから参加することをお奨めします。
また、労働法は企業組織再編などに不可欠の法務分野として会社法制と深い関わりを有しており、企業実務に関する法的素養があることは、労働法の理解に非常に役立ちます。他方で労働法は、いわゆる「社会法」の中心的領域を形成していますので、「ジェンダーと法」、「消費者法」などの履修が非常に役立ちます。社会法分野については、このうち「ジェンダーと法」を含む二つ程度は履修しておくよう薦めます。
1 年 次:「法と公共政策」
2・3年次:「労働法」、「労働法総合演習」、「展開・先端系総合指導(労働法)」、「企業実務と法Ⅰ・Ⅱ」、「ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ」、「法社会学」、「消費者法」
(野川忍先生)
パターン8 環境法
【環境法に強い法曹を目指す人】
急速に体系化・国際化する環境法分野で活躍するために、基礎法学・隣接科目群から「法と公共政策」などを適宜選択し、展開・先端科目群から「環境と法Ⅰ・Ⅱ」「環境法総合演習」「展開・先端系総合指導(環境法)」を選択します。「環境と法Ⅰ」では、基本原則と理念、各種手法等の環境法の基本的な考え方と個別法の重要論点について学び、「環境と法Ⅱ」では、個別法を踏まえた訴訟上の問題点について、典型判例に基づきながら学びます。
環境法は、公法(とくに行政法)と私法(とくに民法の不法行為法)が交錯する分野であり、それらの融合を目指す先端領域の学問分野です。そのため、法解釈論の深化のみならず、立法を視野に入れた法政策論の定立に係る研究や思考方法が求められます。「環境法総合演習」では、判例評釈等を通して、そのような視座を養い、必要な技能を磨きます。また、「展開・先端系総合指導(環境法)」では、最新の判例を素材としながら、自然科学の知見や評価を織り交ぜながら、環境法あるいは環境政策の学際性を体感する訓練を行います。
環境法は選択科目の中でも、通常の法解釈学とは異なる学習方法を求められているのではないかと、不安を感じる学生も少なくないと思われます。しかし、司法試験に求められる出題の法令等には10の個別法という一定の縛りがあり、直近の改正法令を中心に出題されるなど出題範囲も限定される傾向があるので、司法試験科目としての環境法の学習においては、広汎な学習や知識は必要とされていません。ただし、法科大学院で将来の環境法曹を養成するという立場から、環境法の現状とその限界、立法政策上の課題、など、その問題解決志向性は常に求められていると考えます。
他方で、環境法は伝統的な法学分野とは異なり、条文によって具体化される法律効果は現代世代だけでなく将来世代をも射程範囲に入れます。そのためには、経済学や社会学などの他の社会科学分野に加えて、自然科学分野との地道な共同作業が不可欠です。そこで、教える側は、教材を工夫し、実行可能な範囲内で環境問題の現場において学生達を教育することが環境法曹の育成に不可欠であると感じています。将来の環境法曹を目指す学生諸君も、この点を踏まえて視野を広く、意欲的に学習に取り組まれることを願っています。
1 年 次:「法と公共政策」、「立法と政治」
2・3年次:「環境と法Ⅰ・Ⅱ」、「環境法総合演習」、「展開・先端系総合指導(環境法)」
急速に体系化・国際化する環境法分野で活躍するために、基礎法学・隣接科目群から「法と公共政策」などを適宜選択し、展開・先端科目群から「環境と法Ⅰ・Ⅱ」「環境法総合演習」「展開・先端系総合指導(環境法)」を選択します。「環境と法Ⅰ」では、基本原則と理念、各種手法等の環境法の基本的な考え方と個別法の重要論点について学び、「環境と法Ⅱ」では、個別法を踏まえた訴訟上の問題点について、典型判例に基づきながら学びます。
環境法は、公法(とくに行政法)と私法(とくに民法の不法行為法)が交錯する分野であり、それらの融合を目指す先端領域の学問分野です。そのため、法解釈論の深化のみならず、立法を視野に入れた法政策論の定立に係る研究や思考方法が求められます。「環境法総合演習」では、判例評釈等を通して、そのような視座を養い、必要な技能を磨きます。また、「展開・先端系総合指導(環境法)」では、最新の判例を素材としながら、自然科学の知見や評価を織り交ぜながら、環境法あるいは環境政策の学際性を体感する訓練を行います。
環境法は選択科目の中でも、通常の法解釈学とは異なる学習方法を求められているのではないかと、不安を感じる学生も少なくないと思われます。しかし、司法試験に求められる出題の法令等には10の個別法という一定の縛りがあり、直近の改正法令を中心に出題されるなど出題範囲も限定される傾向があるので、司法試験科目としての環境法の学習においては、広汎な学習や知識は必要とされていません。ただし、法科大学院で将来の環境法曹を養成するという立場から、環境法の現状とその限界、立法政策上の課題、など、その問題解決志向性は常に求められていると考えます。
他方で、環境法は伝統的な法学分野とは異なり、条文によって具体化される法律効果は現代世代だけでなく将来世代をも射程範囲に入れます。そのためには、経済学や社会学などの他の社会科学分野に加えて、自然科学分野との地道な共同作業が不可欠です。そこで、教える側は、教材を工夫し、実行可能な範囲内で環境問題の現場において学生達を教育することが環境法曹の育成に不可欠であると感じています。将来の環境法曹を目指す学生諸君も、この点を踏まえて視野を広く、意欲的に学習に取り組まれることを願っています。
1 年 次:「法と公共政策」、「立法と政治」
2・3年次:「環境と法Ⅰ・Ⅱ」、「環境法総合演習」、「展開・先端系総合指導(環境法)」
(奥田進一先生)
パターン9 国際公法
【国際関係法に強い法曹を目指す人】
国際法は、基本的には国家間の権利義務関係を規律する法分野であり、従来は国内裁判所で直接に適用されることはそれほど多くはありませんでした。しかし近年、特に経済や人権、環境の分野を中心として多数の国際条約が締結され、国内法の規律や運用に大きな影響を与えるようになっています。こうした現象を正確に理解するためには、その基礎をなす国際法の基本概念とその仕組みをきちんと押さえておくことが必要です。グローバル化が進む今日、法曹には、こうした分野への鋭い感覚と知識が必要となります。
その意味で、司法試験で国際公法を選択するのでなくても、勉強しておいた方が将来の仕事の範囲が広がるでしょう。国内法を勉強していると頭が固くなりがちだという人がいますが、国際法の勉強はそれをもみほぐします。国によって運用のあり方も制度も異なり、最高裁判所によって担保されるような唯一の正解というものがないからです。もちろん国際法も法ですから、国内法をしっかり勉強しておくことが前提です。国内法と比較しながら何がどう違うかを常に意識して勉強することが重要です。
「国際法」の授業では、国際法の基本的な概念をしっかり身につけるよう学習しますが、その中では海洋法や国際紛争解決の仕組み、安全保障の問題など、急速に変化しつつあるテーマをも扱います。また「国際公法総合演習」では、日本の裁判所の判例を実際に読みながら、国際法の日本の司法への影響を確認し、日本の法制度の中での国際法と国内法の関係を中心に、国際法の適用の実際を具体的に検討します。司法試験の選択科目として国際公法を選択しようとする場合には、国際経済法および国際人権法の分野も対象になりますが、この演習ではこれらの分野も一定程度カバーする予定です。
1 年 次:「法情報調査」、「法と公共政策」
2・3年次:「国際法」、「国際公法総合演習」、「比較法制度論」
国際法は、基本的には国家間の権利義務関係を規律する法分野であり、従来は国内裁判所で直接に適用されることはそれほど多くはありませんでした。しかし近年、特に経済や人権、環境の分野を中心として多数の国際条約が締結され、国内法の規律や運用に大きな影響を与えるようになっています。こうした現象を正確に理解するためには、その基礎をなす国際法の基本概念とその仕組みをきちんと押さえておくことが必要です。グローバル化が進む今日、法曹には、こうした分野への鋭い感覚と知識が必要となります。
その意味で、司法試験で国際公法を選択するのでなくても、勉強しておいた方が将来の仕事の範囲が広がるでしょう。国内法を勉強していると頭が固くなりがちだという人がいますが、国際法の勉強はそれをもみほぐします。国によって運用のあり方も制度も異なり、最高裁判所によって担保されるような唯一の正解というものがないからです。もちろん国際法も法ですから、国内法をしっかり勉強しておくことが前提です。国内法と比較しながら何がどう違うかを常に意識して勉強することが重要です。
「国際法」の授業では、国際法の基本的な概念をしっかり身につけるよう学習しますが、その中では海洋法や国際紛争解決の仕組み、安全保障の問題など、急速に変化しつつあるテーマをも扱います。また「国際公法総合演習」では、日本の裁判所の判例を実際に読みながら、国際法の日本の司法への影響を確認し、日本の法制度の中での国際法と国内法の関係を中心に、国際法の適用の実際を具体的に検討します。司法試験の選択科目として国際公法を選択しようとする場合には、国際経済法および国際人権法の分野も対象になりますが、この演習ではこれらの分野も一定程度カバーする予定です。
1 年 次:「法情報調査」、「法と公共政策」
2・3年次:「国際法」、「国際公法総合演習」、「比較法制度論」
(伊藤一頼先生)
パターン10 国際私法
【企業や個人の国際的な活動、生活に伴って生ずる様々な法的問題に興味があり、これらの問題に関連する法律実務に携わりたい人】
国際私法は、企業や個人が外国との法的な関わりを持つときに、どこの法律に準拠して問題を処理解決したらよいのかを様々な法的要素に着目してその法律の適用を実践する法律です。我が国では、変化する国際的な契約関係や、渉外的(国際的)な法律問題や動向に対応するために制定、施行された「法の適用に関する通則法」、国際的な事件に関する裁判管轄を規律するために平成24年4月1日に施行された民事訴訟法および平成31年4月1日に施行された人事訴訟法等の改正内容や国際取引に関する条約ならびに渉外的な判例を学ぶことになります。ただ国際的といっても外国法の知識や外国語が堪能でなければならないということはなく、あくまでも基礎は国内法なので、民法(特に家族法)や民事訴訟法(国際民事訴訟手続)など実体法や手続法の知識の習得が大前提で、これらの基礎的な素養と知識は1年次や2年次の必修科目で学び、2年次からの国際私法の講義で準拠法および国際民事手続法の基本的な考えを学び、国際私法総合演習で実践的な問題解決能力を身につけ、試験に臨むのが良いと思います。履修が望ましい科目としては、下記が挙げられます。
1 年 次:「法情報調査」
2・3年次:「国際私法」、「国際私法総合演習」、「企業実務と法Ⅱ」
3 年 次:「民事法文書作成」
国際私法は、企業や個人が外国との法的な関わりを持つときに、どこの法律に準拠して問題を処理解決したらよいのかを様々な法的要素に着目してその法律の適用を実践する法律です。我が国では、変化する国際的な契約関係や、渉外的(国際的)な法律問題や動向に対応するために制定、施行された「法の適用に関する通則法」、国際的な事件に関する裁判管轄を規律するために平成24年4月1日に施行された民事訴訟法および平成31年4月1日に施行された人事訴訟法等の改正内容や国際取引に関する条約ならびに渉外的な判例を学ぶことになります。ただ国際的といっても外国法の知識や外国語が堪能でなければならないということはなく、あくまでも基礎は国内法なので、民法(特に家族法)や民事訴訟法(国際民事訴訟手続)など実体法や手続法の知識の習得が大前提で、これらの基礎的な素養と知識は1年次や2年次の必修科目で学び、2年次からの国際私法の講義で準拠法および国際民事手続法の基本的な考えを学び、国際私法総合演習で実践的な問題解決能力を身につけ、試験に臨むのが良いと思います。履修が望ましい科目としては、下記が挙げられます。
1 年 次:「法情報調査」
2・3年次:「国際私法」、「国際私法総合演習」、「企業実務と法Ⅱ」
3 年 次:「民事法文書作成」
(内田明先生)
- お問い合わせ先
-
明治大学専門職大学院事務室(法務研究科)
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1
アカデミーコモン10階
電話 03-3296-4318~9
窓口取扱時間
平日 9:00~18:00、土曜日 9:00~12:30
※窓口取扱時間は、変更する場合があります。 -