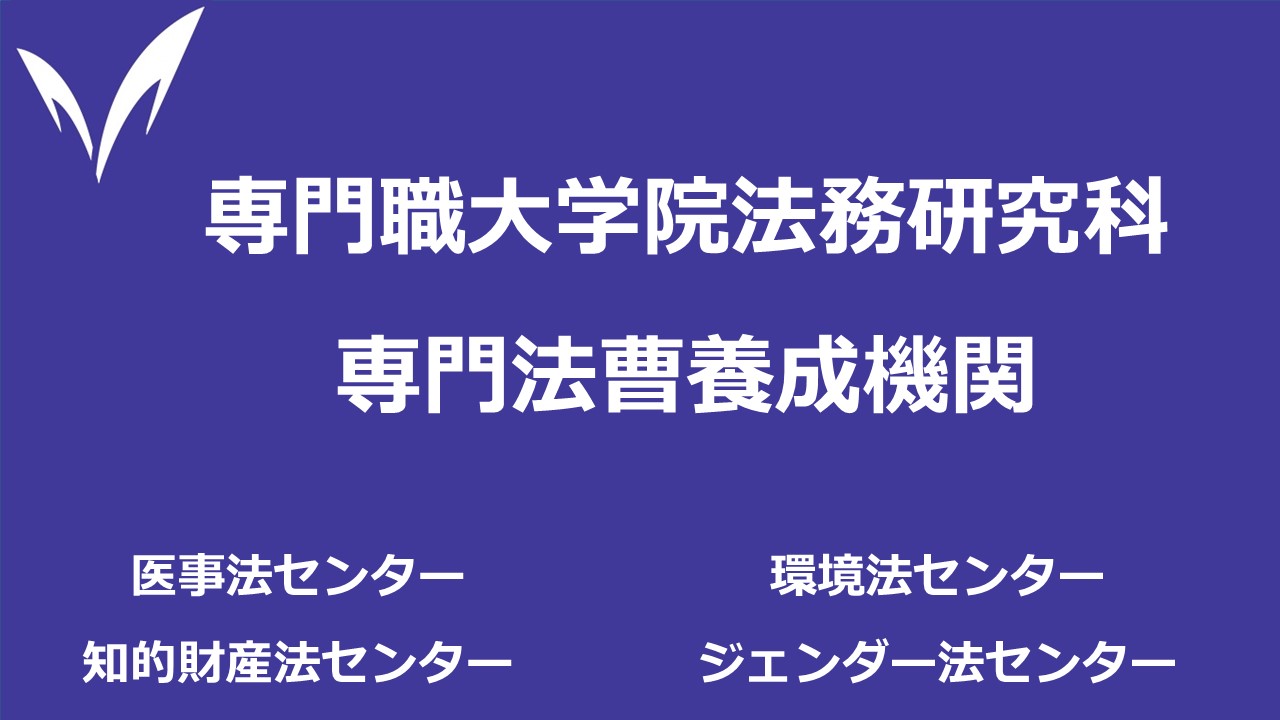2026年02月03日
下田 真人 法学未修者コース修了
2004年4月に、明治大学法科大学院の未修コース第1期生として入学し、2008年9月に新司法試験に合格後、第62期司法修習生として、山口県で実務修習。
【明治大学法科大学院ではどのような勉強をしてきたのか】
私は、商学部を卒業した後、民間企業に勤務し、退職後、明治大学法科大学院に入学しました。それまで全く法律の勉強をしたこともなく、法律にかかわる仕事をしたこともありませんでしたので、1年時の夏学期は、授業についていくことがとても大変でした。私は、法科大学院に入学する前は、未修コースというのは、法学部以外の出身者で、他分野で活動してきた者が集まるところと思っていたのですが、実際に入学してみると、未修コースでも過半数が法学部出身者や司法試験受験経験者であったため、入学当初から授業のレベルが想定以上に高かったのです。2年生になれば、既修者コースに入学してくる学生とともに勉強することになることからも、このままではいけないと奮起し、1年時は盆も正月も、自習室が開いている日は1日も休まずに大学院に通って勉強しました。今から思い返すと非効率な勉強も多かったと思いますが、この時に歯を食いしばった経験は、今でも自分の支えになっていますし、以後、法学部出身の学生たちと伍してやっていくための基盤にもなりました。
また、私自身の強みは、やはり法律以外の分野の経験があることしかないと考えていましたので、選択科目も真剣に勉強しました。新司法試験科目には無い科目ですから、直接新司法試験に役立つことはありませんが、自らの将来の仕事の幅を広げるための基礎作りとして、意識を高く持って取り組みました。
【修習での学習と法科大学院での学習との整合性について】
実務では、法適用の問題よりも、事実認定の問題が中心となることが大半です。修習においては、法科大学院での学習とは異なり、事実認定の技術を磨くことに、多くの時間を費やすことになります。しかし、それは、法科大学院において、実体法の理解を身につけていることが絶対条件となっています。実体法を理解していなければ、求める法律効果を発生させるための要件がわからず、認定しなければならない事実を抽出することができないからです。
法科大学院では、民法や刑法などといった基本的な実体法について、講義もありますし、演習もあります。これらの内容をしっかりと身につければ、修習にも十分に対応できる力をつけることができると思います。たしかに、実務修習で扱う法律は、民法や刑法といった基本的な実体法だけではありません。特別法なども多々あります。しかし、基本的な実体法の知識や法解釈の理解を深めておけば、特別法を扱う際の基礎になりますから、十分に対応できるようになります。そのような意味で、法科大学院での実体法の授業は、司法修習をする上での、必要不可欠な導入となっているといえるでしょう。
手続法についての知識も、実務修習においては不可欠の要素です。実務はすべて手続法に基づいて、時々刻々と進行していくものですから、手続法を理解していなければ、裁判手続の傍聴等しても、何をしているのかが分からなくなってしまうからです。法科大学院での民事訴訟法や刑事訴訟法といった手続法の講義も、実務修習をするにあたっての必要不可欠な知識を得る機会として、大変貴重なものであると思います。
【明治大学法科大学院ではどのような勉強をしたらよいと思っているか】
前述しましたとおり、司法修習においては、法科大学院における基本法律科目(特に実体法)の知識、理解が大前提とされていますから、それらを身につけるための学習に一つ一つ真剣に取り組んでいくことに尽きると思います。新司法試験は、実務家登用試験でありますが、司法修習を受ける能力があるかどうかを判定する試験でもあります。ですから、新司法試験の合格を考える上でも、司法修習で求められる実体法の基礎知識、理解を身につけることが合格に必要不可欠なことです。実体法を身につけるには、やはりしっかりとした基本書を読み、講義や演習に真剣に参加することと、判例などの多くの事例に触れることが肝要だと思います。事例に多く触れておくことは、新司法試験であれば択一試験などでも大きな力になるとともに、修習においても、生の事件の処理を検討する上で、解決方法の引き出しが増え、大きな武器になります。法律の勉強には、何か特効薬があるわけではなく、毎日の積み重ねが将来の大きな力となるものですから、日々の授業に真剣に取り組んでいくことが、何より大切だと思います。
【最後に】
法科大学院は、司法修習や実務家として必要とされる基本的な法律知識や法解釈能力を身につけるという、司法修習や実務に就くにあたっての貴重な導入の場であるともに、司法修習だけでは育成できない多様な法曹を養成するための場であるとも思います。たしかに、法曹であれば誰でも身につけていなければならない基本的な法律知識や法解釈能力を落としてはいけません。しかし、そのような画一的な学習のみにとどまるのではなく、総合大学という学際的な環境を十分に活用して、多様化した社会の中で活躍できる素地を身につける、最後のチャンスが法科大学院であるとも感じています。学生の皆さんには、法科大学院で勉強すべきことをあまり限定的に考えずに、将来の夢や知的好奇心に素直に従って、幅広く、エネルギッシュに、様々なことを勉強していただければと思っています。
【明治大学法科大学院ではどのような勉強をしてきたのか】
私は、商学部を卒業した後、民間企業に勤務し、退職後、明治大学法科大学院に入学しました。それまで全く法律の勉強をしたこともなく、法律にかかわる仕事をしたこともありませんでしたので、1年時の夏学期は、授業についていくことがとても大変でした。私は、法科大学院に入学する前は、未修コースというのは、法学部以外の出身者で、他分野で活動してきた者が集まるところと思っていたのですが、実際に入学してみると、未修コースでも過半数が法学部出身者や司法試験受験経験者であったため、入学当初から授業のレベルが想定以上に高かったのです。2年生になれば、既修者コースに入学してくる学生とともに勉強することになることからも、このままではいけないと奮起し、1年時は盆も正月も、自習室が開いている日は1日も休まずに大学院に通って勉強しました。今から思い返すと非効率な勉強も多かったと思いますが、この時に歯を食いしばった経験は、今でも自分の支えになっていますし、以後、法学部出身の学生たちと伍してやっていくための基盤にもなりました。
また、私自身の強みは、やはり法律以外の分野の経験があることしかないと考えていましたので、選択科目も真剣に勉強しました。新司法試験科目には無い科目ですから、直接新司法試験に役立つことはありませんが、自らの将来の仕事の幅を広げるための基礎作りとして、意識を高く持って取り組みました。
【修習での学習と法科大学院での学習との整合性について】
実務では、法適用の問題よりも、事実認定の問題が中心となることが大半です。修習においては、法科大学院での学習とは異なり、事実認定の技術を磨くことに、多くの時間を費やすことになります。しかし、それは、法科大学院において、実体法の理解を身につけていることが絶対条件となっています。実体法を理解していなければ、求める法律効果を発生させるための要件がわからず、認定しなければならない事実を抽出することができないからです。
法科大学院では、民法や刑法などといった基本的な実体法について、講義もありますし、演習もあります。これらの内容をしっかりと身につければ、修習にも十分に対応できる力をつけることができると思います。たしかに、実務修習で扱う法律は、民法や刑法といった基本的な実体法だけではありません。特別法なども多々あります。しかし、基本的な実体法の知識や法解釈の理解を深めておけば、特別法を扱う際の基礎になりますから、十分に対応できるようになります。そのような意味で、法科大学院での実体法の授業は、司法修習をする上での、必要不可欠な導入となっているといえるでしょう。
手続法についての知識も、実務修習においては不可欠の要素です。実務はすべて手続法に基づいて、時々刻々と進行していくものですから、手続法を理解していなければ、裁判手続の傍聴等しても、何をしているのかが分からなくなってしまうからです。法科大学院での民事訴訟法や刑事訴訟法といった手続法の講義も、実務修習をするにあたっての必要不可欠な知識を得る機会として、大変貴重なものであると思います。
【明治大学法科大学院ではどのような勉強をしたらよいと思っているか】
前述しましたとおり、司法修習においては、法科大学院における基本法律科目(特に実体法)の知識、理解が大前提とされていますから、それらを身につけるための学習に一つ一つ真剣に取り組んでいくことに尽きると思います。新司法試験は、実務家登用試験でありますが、司法修習を受ける能力があるかどうかを判定する試験でもあります。ですから、新司法試験の合格を考える上でも、司法修習で求められる実体法の基礎知識、理解を身につけることが合格に必要不可欠なことです。実体法を身につけるには、やはりしっかりとした基本書を読み、講義や演習に真剣に参加することと、判例などの多くの事例に触れることが肝要だと思います。事例に多く触れておくことは、新司法試験であれば択一試験などでも大きな力になるとともに、修習においても、生の事件の処理を検討する上で、解決方法の引き出しが増え、大きな武器になります。法律の勉強には、何か特効薬があるわけではなく、毎日の積み重ねが将来の大きな力となるものですから、日々の授業に真剣に取り組んでいくことが、何より大切だと思います。
【最後に】
法科大学院は、司法修習や実務家として必要とされる基本的な法律知識や法解釈能力を身につけるという、司法修習や実務に就くにあたっての貴重な導入の場であるともに、司法修習だけでは育成できない多様な法曹を養成するための場であるとも思います。たしかに、法曹であれば誰でも身につけていなければならない基本的な法律知識や法解釈能力を落としてはいけません。しかし、そのような画一的な学習のみにとどまるのではなく、総合大学という学際的な環境を十分に活用して、多様化した社会の中で活躍できる素地を身につける、最後のチャンスが法科大学院であるとも感じています。学生の皆さんには、法科大学院で勉強すべきことをあまり限定的に考えずに、将来の夢や知的好奇心に素直に従って、幅広く、エネルギッシュに、様々なことを勉強していただければと思っています。
高栁 良作 法学既修者コース修了
【自己紹介】
私は、2007年3月明治大学法科大学院を修了(二期既修)し、その年の新司法試験に運よく合格し、同年の11月から司法修習を開始しました(第61期)。
そして、2008年12月に司法修習を修了し、同月横浜弁護士会に登録して、現在は横浜市内にある事務所でイソ弁として稼動しています。
今回、明治大学法科大学院修了生の立場から、法科大学院時代に勉強しておいて良かったこと、および勉強しておくべきだったことなどについて、述べたいと思います。
【法科大学院生活を振り返って】
(1)勉強方法の改善
私は、大学時代に旧司法試験を受けており、六法については一通り勉強していたため、迷わず既修者コースを選択しました。
法科大学院での勉強は、実務家の養成を目的としている以上、判例や条文解釈中心の勉強になります。もちろん、結論だけでなく、その理由、そこに至るまでの判例や学説の流れ、判例であればその射程範囲などです。
私自身、大学時代から、いわゆる「論点主義」に陥らないように注意はしていましたが、上記法科大学院での講義を受けて、気がつかないうちに論点主義に陥っていることに気がつきました。
そのため、自分の勉強方法を一から見直すことができました。
(2)印象深い講義
上記のような講義の中でも、20人くらいの学生と教授によって行われるゼミ形式での講義は特に印象的でした。今までの勉強とは異なり、毎回課題が出され、次回までに調査をして、発表するという経験は、とても刺激的であり、自分の勉強の励みにもなりました。
特に青山善充先生の民事訴訟法ゼミでは、毎回、青山教授との質疑応答に答えられずに自分の知識のなさを改めて実感する、ということの繰り返しでした。ただ、そのゼミのおかげで勉強のモチベーションがあがり、また自分の勉強の方法を見直すことが出来たと思います。
そして、そのゼミ形式の講義に対応するため、学生同士で自主ゼミを組み、その講義の予習・復習も行いました。この自主ゼミで議論することで、自分では理解していたつもりでも実は不十分であった部分が明らかになったり、また、自分では気がつかなかった弱点を発見することができたりするなど、勉強を続けていく上で、とても役に立ちました。この自主ゼミの経験は、実務家になった今でも、役に立っていると思います。
(3)実務家の先生との関係
私は、司法試験を目指しながらも、法科大学院に入学するまでは、実務家の方とお話をする機会というものをほとんど持つことがありませんでした。そのため、「弁護士になりたい」と思っていても、具体的な仕事について、知識を持っていませんでした。
法科大学院に入学してからは、弁護士や検事、そして裁判官の先生方と直接お話しすることができ、また先生方の日常の業務の様子や、実務家としての信念などをうかがうことが出来ました。そのようなお話を聞き、また先生方の姿を見ることで、将来自分がどのような実務家になりたいか、ということが明確になったと思います。
(4)小 括
このように、私は講義を予習復習してきちんと受けること、友人とゼミを組んで、議論をし、また協力し合うこと、そして実務家の先生方となるべく多くの接点を持つように心がけていました。
(5)やっておくべきだったこと
私は、法科大学院時代には「模擬裁判(刑事)」と「法文書作成」の2つの実務系科目を履修していました。当時は、新司法試験の受験に役に立つのかといった不安の中での履修でしたが、実際には、刑事手続の細かな部分や契約書作成時の注意点など、教科書を読んでいるだけでは身につかないような知識を得ることができ、ダイレクトに新司法試験受験の役に立ちました。
そして、弁護士として稼動している現在においても、上記2つの講義で学んだことが、私の核になっていると思います。
そのことから考えれば、上記科目のみならず、他の実務系科目である「模擬裁判(民事)」や「エクスターンシップ」などの科目についても、時間の許す限り、履修しておけばよかったと思っています。
【現法科大学院生の皆さんに向けて】
私が偉そうなことなどいえないのですが、何かの参考になればと思い、法科大学院時代にしておくべきことを最後に述べたいと思います。
まず、講義の履修です。これは当然のことかもしれませんが、すべての講義について、予習・復習をしっかり行ってください。既修コースは2年で司法試験に臨まなければならない以上、時間は貴重です。そのため、講義で学んだことを、すぐに自分の知識とするぐらいのつもりで勉強する必要があると思います。
次に、友人との自主ゼミです。この自主ゼミについては、賛否両論がありますが、自分と同じ、もしくはそれ以上の人達と行う自主ゼミはいい刺激になります。また、上記のように一人で勉強していては気がつかない点を発見することができます。そのため、弊害がない限り、自主ゼミは組んでください。
最後に、書面の作成です。弁護士だけでなく、検察官も裁判官もその仕事のほとんどは書面の作成に充てられていると思います。また、新司法試験も答案という書面を作成することが要求されています。
そして、その書面というのは、「人に読ませる(読んでもらう)書面」です。私自身まだまだですが、他人に対して、自分の考えを理解してもらうといったことが常に要求されると思います。
そのため、みなさんも書面の作成能力を鍛えることが必須です。ただ、この点は講義を履修するだけでは身につかないものであるため、レポートを積極的に作成して先生に添削してもらったり、あるいは上記の自主ゼミにおいて友人同士で答案を添削したりするなどして、鍛える必要があると思います
自分が弁護士になって実感しましたが、この仕事は本当にやりがいのある仕事だと思います。裁判官・検事のみなさんもそうおっしゃいます。法科大学院での勉強は、辛いことも多いと思いますが、それを乗り越えれば、実務家というやりがいのある仕事に就くことができます。それを目指して、皆さん頑張ってください。
私は、2007年3月明治大学法科大学院を修了(二期既修)し、その年の新司法試験に運よく合格し、同年の11月から司法修習を開始しました(第61期)。
そして、2008年12月に司法修習を修了し、同月横浜弁護士会に登録して、現在は横浜市内にある事務所でイソ弁として稼動しています。
今回、明治大学法科大学院修了生の立場から、法科大学院時代に勉強しておいて良かったこと、および勉強しておくべきだったことなどについて、述べたいと思います。
【法科大学院生活を振り返って】
(1)勉強方法の改善
私は、大学時代に旧司法試験を受けており、六法については一通り勉強していたため、迷わず既修者コースを選択しました。
法科大学院での勉強は、実務家の養成を目的としている以上、判例や条文解釈中心の勉強になります。もちろん、結論だけでなく、その理由、そこに至るまでの判例や学説の流れ、判例であればその射程範囲などです。
私自身、大学時代から、いわゆる「論点主義」に陥らないように注意はしていましたが、上記法科大学院での講義を受けて、気がつかないうちに論点主義に陥っていることに気がつきました。
そのため、自分の勉強方法を一から見直すことができました。
(2)印象深い講義
上記のような講義の中でも、20人くらいの学生と教授によって行われるゼミ形式での講義は特に印象的でした。今までの勉強とは異なり、毎回課題が出され、次回までに調査をして、発表するという経験は、とても刺激的であり、自分の勉強の励みにもなりました。
特に青山善充先生の民事訴訟法ゼミでは、毎回、青山教授との質疑応答に答えられずに自分の知識のなさを改めて実感する、ということの繰り返しでした。ただ、そのゼミのおかげで勉強のモチベーションがあがり、また自分の勉強の方法を見直すことが出来たと思います。
そして、そのゼミ形式の講義に対応するため、学生同士で自主ゼミを組み、その講義の予習・復習も行いました。この自主ゼミで議論することで、自分では理解していたつもりでも実は不十分であった部分が明らかになったり、また、自分では気がつかなかった弱点を発見することができたりするなど、勉強を続けていく上で、とても役に立ちました。この自主ゼミの経験は、実務家になった今でも、役に立っていると思います。
(3)実務家の先生との関係
私は、司法試験を目指しながらも、法科大学院に入学するまでは、実務家の方とお話をする機会というものをほとんど持つことがありませんでした。そのため、「弁護士になりたい」と思っていても、具体的な仕事について、知識を持っていませんでした。
法科大学院に入学してからは、弁護士や検事、そして裁判官の先生方と直接お話しすることができ、また先生方の日常の業務の様子や、実務家としての信念などをうかがうことが出来ました。そのようなお話を聞き、また先生方の姿を見ることで、将来自分がどのような実務家になりたいか、ということが明確になったと思います。
(4)小 括
このように、私は講義を予習復習してきちんと受けること、友人とゼミを組んで、議論をし、また協力し合うこと、そして実務家の先生方となるべく多くの接点を持つように心がけていました。
(5)やっておくべきだったこと
私は、法科大学院時代には「模擬裁判(刑事)」と「法文書作成」の2つの実務系科目を履修していました。当時は、新司法試験の受験に役に立つのかといった不安の中での履修でしたが、実際には、刑事手続の細かな部分や契約書作成時の注意点など、教科書を読んでいるだけでは身につかないような知識を得ることができ、ダイレクトに新司法試験受験の役に立ちました。
そして、弁護士として稼動している現在においても、上記2つの講義で学んだことが、私の核になっていると思います。
そのことから考えれば、上記科目のみならず、他の実務系科目である「模擬裁判(民事)」や「エクスターンシップ」などの科目についても、時間の許す限り、履修しておけばよかったと思っています。
【現法科大学院生の皆さんに向けて】
私が偉そうなことなどいえないのですが、何かの参考になればと思い、法科大学院時代にしておくべきことを最後に述べたいと思います。
まず、講義の履修です。これは当然のことかもしれませんが、すべての講義について、予習・復習をしっかり行ってください。既修コースは2年で司法試験に臨まなければならない以上、時間は貴重です。そのため、講義で学んだことを、すぐに自分の知識とするぐらいのつもりで勉強する必要があると思います。
次に、友人との自主ゼミです。この自主ゼミについては、賛否両論がありますが、自分と同じ、もしくはそれ以上の人達と行う自主ゼミはいい刺激になります。また、上記のように一人で勉強していては気がつかない点を発見することができます。そのため、弊害がない限り、自主ゼミは組んでください。
最後に、書面の作成です。弁護士だけでなく、検察官も裁判官もその仕事のほとんどは書面の作成に充てられていると思います。また、新司法試験も答案という書面を作成することが要求されています。
そして、その書面というのは、「人に読ませる(読んでもらう)書面」です。私自身まだまだですが、他人に対して、自分の考えを理解してもらうといったことが常に要求されると思います。
そのため、みなさんも書面の作成能力を鍛えることが必須です。ただ、この点は講義を履修するだけでは身につかないものであるため、レポートを積極的に作成して先生に添削してもらったり、あるいは上記の自主ゼミにおいて友人同士で答案を添削したりするなどして、鍛える必要があると思います
自分が弁護士になって実感しましたが、この仕事は本当にやりがいのある仕事だと思います。裁判官・検事のみなさんもそうおっしゃいます。法科大学院での勉強は、辛いことも多いと思いますが、それを乗り越えれば、実務家というやりがいのある仕事に就くことができます。それを目指して、皆さん頑張ってください。
張江 亜季 法学既修者コース修了
「明治大学法科大学院での2年間」
私は、2007年3月に明治大学法科大学院を修了後、2007年11月に司法修習所に入所し(第61期)、2008年12月18日、東京都内の法律事務所に入所しました。
【明治大学法科大学院での出会い】
(1)実務家の方々と身近に接することができたこと
イ) 私は、法科大学院に入学する前、旧司法試験を受験していましたが、実務家の方々から直接お話を伺えるという機会はほとんどありませんでした。
しかし、明治大学法科大学院既修コース1年目の民法演習クラスを、実務家の先生に担当していただき、入学直後から、リアルタイムで弁護士をなさっている先生の授業を体感することができ、大きな刺激を受けました。
それまでは、すでに理論的に構築された判例や学説の流れを憶えるという勉強をしていたのですが、自分の導きたい結論のために、自分の持っている条文や判例の知識を最大限に生かし、生の事例に当てはめ、自ら理論を構築していくという考え方に衝撃を受けました。
私は、この時、実務家というのは、ある意味職人なんだということを強く意識しました。それと同時に、使える道具を持っていることの重要性にも気付かされました。
明治大学法科大学院で実務家の先生方と接したことにより、それまで自分が漫然と蓄えていた法律や条文の知識を、使える道具へとブラッシュアップしいくことの大切さに気付けたと思っています。憶えた法律や条文の知識を実際に使えるようにならなければ、生の事実にぶつかった時、それを解決していくことは決してできないということを入学直後に意識することができたことにより、その後の勉強方針をしっかりと持てたと思います。
弁護士となった現在でも、自分の持っている道具を使える道具へとブラッシュアップする努力を怠ることのないよう、常に心がけています。
ロ) また、明治大学法科大学院では、先端科目において、各分野の第一線でご活躍なさっている先生方の講義を聴くことができました。
自分が興味を持てる分野に出会い、その分野の第一線で活躍する弁護士を目の当たりにすることによって、自分が目指す弁護士像が明確になり、新司法試験合格へのモチベーションを常に高く保つことができました。
新司法試験の受験科目ではない先端科目であっても、法的思考方法や法的解決力、法律家として必要なマインドを直接聞くことができたので、新司法試験受験の時もこのような講義が大いに役立ちました。
(2)同じ志の仲間と出会えたこと
私は、明治大学出身であったことから、慣れ親しんだ母校である明治大学法科大学院に入学したのですが、もう一つ、明治大学法科大学院を選んだ大きな理由があります。それは、入学案内に書かれていた「熱い心と冷静な頭をもった法律家を育成したい」という言葉に惹かれたことです。
私は、法科大学院を受験する際、せっかく法科大学院に入学するのなら、どのような法律家を育成することを理念としているのかを明確にしている大学院を受験しようと思っていました。他人のために役に立つことがしたいと考えていた私は、熱い心がなければ頑張れない、でも冷静に物事を判断できなければ何も解決することはできないという考えに共感しました。
明治大学法科大学院に入学後、このような「熱い心と冷静な頭脳をもった法律家」を目指す、沢山の仲間達と出会い、支えられながら、新司法試験を乗り切ることができました。私にとって、明治大学法科大学院で出会った仲間達は、現在でも、とても大切な仲間であり、良きライバルです。明確な理念がある明治大学法科大学院であったからこそ、このような素敵な仲間達に出会えたと思っています。
【明治大学法科大学院での勉強】
司法修習期間が1年という短期間になった現在、ロースクール時代にどのようなことを学んだのかはとても重要です。
特に、司法修習で大きな重点を占める民事の要件事実について、明治大学法科大学院で、裁判官と実務家の先生方にしっかりと基礎から教えていただいていたことが、とても役に立ちました。
また、少人数の演習クラスは、様々な論点についてクラスメイトと議論を交わし、自分の考えを整理して、相手にわかり易く伝えることの訓練の場となり、とても有意義な時間だったと思います。
【まとめ】
私にとって、明治大学法科大学院で過ごした2年間は、とても密度の濃い、充実したものでした。もうすぐ修了という時期に、もう少しここで過ごしたかったなと思ったほど快適なものでもありました。
これは、明治大学法科大学院の先生方が、「熱い心と冷静な頭脳」を持って、私達学生に親身に接してくださったからだと思っています。
今後、明治大学法科大学院で学ばれる後輩の皆さんには、是非、多くの先生方に自分の「熱い心」をぶつけて欲しいと思います。きっと、自分の目標にプラスとなるアドバイスを頂けると思います。
私も、「熱い心と冷静な頭脳をもった法律家」になれるよう、これからも研鑽を積んでいきます。
私は、2007年3月に明治大学法科大学院を修了後、2007年11月に司法修習所に入所し(第61期)、2008年12月18日、東京都内の法律事務所に入所しました。
【明治大学法科大学院での出会い】
(1)実務家の方々と身近に接することができたこと
イ) 私は、法科大学院に入学する前、旧司法試験を受験していましたが、実務家の方々から直接お話を伺えるという機会はほとんどありませんでした。
しかし、明治大学法科大学院既修コース1年目の民法演習クラスを、実務家の先生に担当していただき、入学直後から、リアルタイムで弁護士をなさっている先生の授業を体感することができ、大きな刺激を受けました。
それまでは、すでに理論的に構築された判例や学説の流れを憶えるという勉強をしていたのですが、自分の導きたい結論のために、自分の持っている条文や判例の知識を最大限に生かし、生の事例に当てはめ、自ら理論を構築していくという考え方に衝撃を受けました。
私は、この時、実務家というのは、ある意味職人なんだということを強く意識しました。それと同時に、使える道具を持っていることの重要性にも気付かされました。
明治大学法科大学院で実務家の先生方と接したことにより、それまで自分が漫然と蓄えていた法律や条文の知識を、使える道具へとブラッシュアップしいくことの大切さに気付けたと思っています。憶えた法律や条文の知識を実際に使えるようにならなければ、生の事実にぶつかった時、それを解決していくことは決してできないということを入学直後に意識することができたことにより、その後の勉強方針をしっかりと持てたと思います。
弁護士となった現在でも、自分の持っている道具を使える道具へとブラッシュアップする努力を怠ることのないよう、常に心がけています。
ロ) また、明治大学法科大学院では、先端科目において、各分野の第一線でご活躍なさっている先生方の講義を聴くことができました。
自分が興味を持てる分野に出会い、その分野の第一線で活躍する弁護士を目の当たりにすることによって、自分が目指す弁護士像が明確になり、新司法試験合格へのモチベーションを常に高く保つことができました。
新司法試験の受験科目ではない先端科目であっても、法的思考方法や法的解決力、法律家として必要なマインドを直接聞くことができたので、新司法試験受験の時もこのような講義が大いに役立ちました。
(2)同じ志の仲間と出会えたこと
私は、明治大学出身であったことから、慣れ親しんだ母校である明治大学法科大学院に入学したのですが、もう一つ、明治大学法科大学院を選んだ大きな理由があります。それは、入学案内に書かれていた「熱い心と冷静な頭をもった法律家を育成したい」という言葉に惹かれたことです。
私は、法科大学院を受験する際、せっかく法科大学院に入学するのなら、どのような法律家を育成することを理念としているのかを明確にしている大学院を受験しようと思っていました。他人のために役に立つことがしたいと考えていた私は、熱い心がなければ頑張れない、でも冷静に物事を判断できなければ何も解決することはできないという考えに共感しました。
明治大学法科大学院に入学後、このような「熱い心と冷静な頭脳をもった法律家」を目指す、沢山の仲間達と出会い、支えられながら、新司法試験を乗り切ることができました。私にとって、明治大学法科大学院で出会った仲間達は、現在でも、とても大切な仲間であり、良きライバルです。明確な理念がある明治大学法科大学院であったからこそ、このような素敵な仲間達に出会えたと思っています。
【明治大学法科大学院での勉強】
司法修習期間が1年という短期間になった現在、ロースクール時代にどのようなことを学んだのかはとても重要です。
特に、司法修習で大きな重点を占める民事の要件事実について、明治大学法科大学院で、裁判官と実務家の先生方にしっかりと基礎から教えていただいていたことが、とても役に立ちました。
また、少人数の演習クラスは、様々な論点についてクラスメイトと議論を交わし、自分の考えを整理して、相手にわかり易く伝えることの訓練の場となり、とても有意義な時間だったと思います。
【まとめ】
私にとって、明治大学法科大学院で過ごした2年間は、とても密度の濃い、充実したものでした。もうすぐ修了という時期に、もう少しここで過ごしたかったなと思ったほど快適なものでもありました。
これは、明治大学法科大学院の先生方が、「熱い心と冷静な頭脳」を持って、私達学生に親身に接してくださったからだと思っています。
今後、明治大学法科大学院で学ばれる後輩の皆さんには、是非、多くの先生方に自分の「熱い心」をぶつけて欲しいと思います。きっと、自分の目標にプラスとなるアドバイスを頂けると思います。
私も、「熱い心と冷静な頭脳をもった法律家」になれるよう、これからも研鑽を積んでいきます。
- お問い合わせ先
-
明治大学専門職大学院事務室(法務研究科)
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1
アカデミーコモン10階
電話 03-3296-4318~9
窓口取扱時間
平日 9:00~18:00 ,土曜日 9:00~12:30
※窓口取扱時間は,変更する場合があります。 -