2026年02月03日
国際日本学実践科目の履修生がVolue合同会社を訪問しました
2025年01月25日
明治大学
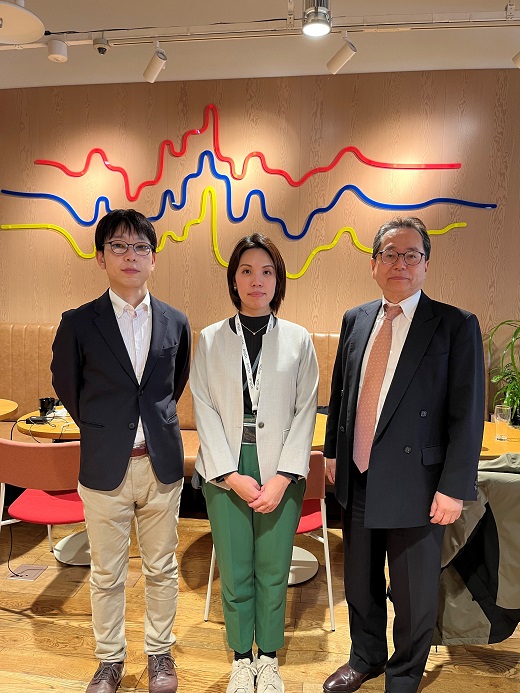
2024年度秋学期の「国際日本学実践科目D」で実施している企業訪問の最後は、さる1月21日に実施、東京丸ノ内北口にあるフレキシブルオフィスのWeWorkに日本の拠点を設けるVolue合同会社に出向いて、同社の松本健一会長、田中功カントリーマネージャー、及び関口百合子ディールデスク・マネジャーからお話を伺いました。
Volueはノルウェー王国のオスロに本拠を置き、欧州全域においてエネルギー関連のソリューションを提供する企業です。エネルギー関連のデータ提供や予測、エネルギー生産や売買の最適化と自動化等に適したソフトウェアの開発と提供などを行う先進企業で、日本においても事業拡大を行うべく2022年に東京に拠点を設けました。
その会長である松本さんは、1980年に三井物産入社、20年以上勤務し、石油、ガス、化学、発電プラントの建設やファイナンスなどを手がけ、その後、米英の外資系企業の経営にも携わりアジアと日本における事業拡大に貢献されてきた方です。また田中さんは、電力会社にウラン燃料を供給する商社のお仕事に携わり、中国語も堪能なプロフェッショナルです。関口さんはシンガポール生まれで、日本の公教育を受けたのち豪州で高等教育を受け、再びシンガポールに戻って日本企業のアジアでの事業拡大に取り組むなどの経験をお持ちの方です。
当日は、同社が欧州を中心に数十年に亘り電力事業者や電力の大口需要家に、データサイエンスとデジタル技術を活用して提供してきた可視化、予測・分析・最適化サービスの内容と、再エネの増大に伴い精度を上げるために近年行っている人工知能の活用やプロセス自動化の取り組みについてお話を伺いましたが、脱炭素に舵を切っている欧州に比べると日本は再生可能エネルギーの開発も電力の効率的な利用も遅れており、それを効果的に進めるためのソリューションを提供する同社の役割を理解することができました。
松本さん、田中さん、関口さんはいずれも、日本の企業と外資系の企業の両方で勤務する経験をお持ちであることから、両者の違いや働く上での心構えなどを伺いました。
田中さんは、「外資系の企業ではジョブ型採用が基本となるが、仕事の効率を重視し、残業をしてまで仕事をすることにネガティブなイメージがある。管理業務がシンプルで、担当するコア業務に集中できる。上下関係がフラットでトップとも自由な意見交換ができる雰囲気がある。一方、日本企業はいろいろな部署で、じっくり育ててくれるというメリットはある」というお話をしていただきました。
関口さんは、「仕事のプロセスにおいて創意工夫をこらし進めていくことに喜びを感じる。外資でも日本の企業でも、学ぶ姿勢さえあれば教えてくれる職場の環境はあろうが、やはり一緒に働く人々との相性や関係は大切である。自分のやれることをステップバイステップでやっていくことに尽きるのではないか」というお話をしていただきました。
松本さんからは、「外資の特徴は、M&Aなど経営のアクションが早く、その結果、自分の仕事が突然、なくなるということもあり得る。外資でトップを務め続けるには、常に新しいテーマを見つけ出し、組織のマネージメントとセールスの実績という両面で成果を出していかなければならない。私自身、新しい仕事に取り組むに当たっては仮説抽出と分析・検証の計画作りが重要で、その過程においてMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)(漏れなく、ダブりなくの俯瞰思考)を重視している。どのような会社で働くにしても、スキルセットとマインドセットを日々磨くことが求められる」と教えていただきました。
就職活動を控えている履修生には、とても有益はお話が伺えました。
Volueはノルウェー王国のオスロに本拠を置き、欧州全域においてエネルギー関連のソリューションを提供する企業です。エネルギー関連のデータ提供や予測、エネルギー生産や売買の最適化と自動化等に適したソフトウェアの開発と提供などを行う先進企業で、日本においても事業拡大を行うべく2022年に東京に拠点を設けました。
その会長である松本さんは、1980年に三井物産入社、20年以上勤務し、石油、ガス、化学、発電プラントの建設やファイナンスなどを手がけ、その後、米英の外資系企業の経営にも携わりアジアと日本における事業拡大に貢献されてきた方です。また田中さんは、電力会社にウラン燃料を供給する商社のお仕事に携わり、中国語も堪能なプロフェッショナルです。関口さんはシンガポール生まれで、日本の公教育を受けたのち豪州で高等教育を受け、再びシンガポールに戻って日本企業のアジアでの事業拡大に取り組むなどの経験をお持ちの方です。
当日は、同社が欧州を中心に数十年に亘り電力事業者や電力の大口需要家に、データサイエンスとデジタル技術を活用して提供してきた可視化、予測・分析・最適化サービスの内容と、再エネの増大に伴い精度を上げるために近年行っている人工知能の活用やプロセス自動化の取り組みについてお話を伺いましたが、脱炭素に舵を切っている欧州に比べると日本は再生可能エネルギーの開発も電力の効率的な利用も遅れており、それを効果的に進めるためのソリューションを提供する同社の役割を理解することができました。
松本さん、田中さん、関口さんはいずれも、日本の企業と外資系の企業の両方で勤務する経験をお持ちであることから、両者の違いや働く上での心構えなどを伺いました。
田中さんは、「外資系の企業ではジョブ型採用が基本となるが、仕事の効率を重視し、残業をしてまで仕事をすることにネガティブなイメージがある。管理業務がシンプルで、担当するコア業務に集中できる。上下関係がフラットでトップとも自由な意見交換ができる雰囲気がある。一方、日本企業はいろいろな部署で、じっくり育ててくれるというメリットはある」というお話をしていただきました。
関口さんは、「仕事のプロセスにおいて創意工夫をこらし進めていくことに喜びを感じる。外資でも日本の企業でも、学ぶ姿勢さえあれば教えてくれる職場の環境はあろうが、やはり一緒に働く人々との相性や関係は大切である。自分のやれることをステップバイステップでやっていくことに尽きるのではないか」というお話をしていただきました。
松本さんからは、「外資の特徴は、M&Aなど経営のアクションが早く、その結果、自分の仕事が突然、なくなるということもあり得る。外資でトップを務め続けるには、常に新しいテーマを見つけ出し、組織のマネージメントとセールスの実績という両面で成果を出していかなければならない。私自身、新しい仕事に取り組むに当たっては仮説抽出と分析・検証の計画作りが重要で、その過程においてMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)(漏れなく、ダブりなくの俯瞰思考)を重視している。どのような会社で働くにしても、スキルセットとマインドセットを日々磨くことが求められる」と教えていただきました。
就職活動を控えている履修生には、とても有益はお話が伺えました。
(兼任講師:井上洋)









