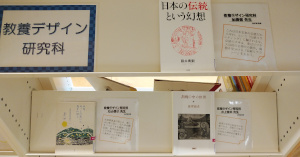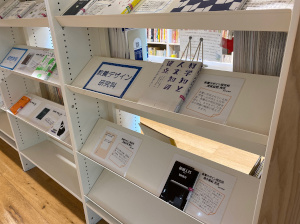2026年02月03日
教養デザインの本棚
和泉図書館の教員おすすめ本コーナーの教養デザイン研究科の展示スペースに、研究科の教員が、将来は大学院に進もうかと考えている学部生のみなさん、また、大学院で研究を始める院生のみなさんにお薦めする本を紹介、展示しています。
和泉図書館にお立ち寄りの際はぜひお手に取ってご覧ください。
和泉図書館にお立ち寄りの際はぜひお手に取ってご覧ください。
2025年度
エリノア・オストロム『コモンズのガバナンスー人びとの協働と制度の進化—』(原田禎夫・齋藤暖夫・嶋田大作訳、晃洋書房、2022年)
推薦者:西川和孝(准教授 教養デザイン研究科 思想コース)
世界的な人口増加と急速な経済発展にともなって、地球上の限られた資源をめぐる争いが各地で発生している。本書は、地域社会の住民たちが共有資源「コモンズ」をどのように管理・運営しているのかを、世界各地の事例に基づいて分析し、長期的に持続可能な共同管理を実現するための8つの設計原理を導き出した名著である。まさに、資源ガバナンスのあり方を考えるうえで極めて有用な道しるべとなる一冊である。
武井彩佳『歴史修正主義 ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで』(中公新書、2021年)
推薦者:佐藤公紀(専任講師 教養デザイン研究科 文化コース)
政治的な意図によって歴史的事実が歪められることを「歴史修正主義」と言います。「オルタナティブ・ファクト(もう一つの事実)」や「フェイクニュース」といった言葉がSNS上で飛び交う現代は、まさに「歴史修正主義」が全盛を迎えた時代であると言えるでしょう。
政治的な意図によって歴史的事実が歪められることを「歴史修正主義」と言います。「オルタナティブ・ファクト(もう一つの事実)」や「フェイクニュース」といった言葉がSNS上で飛び交う現代は、まさに「歴史修正主義」が全盛を迎えた時代であると言えるでしょう。
本書は、このような状況に対し、欧米における19世紀末から現代に至る系譜を歴史研究の視点から批判的に検討し、これからの歴史認識を築くための手がかりを提示します。現代の歴史認識の危機に正面から取り組み、「歴史的事実とは何か」を改めて問い直す本書は、まさに必読の一冊です。
2024年度
中野佳祐『カタツムリの知恵と脱成長.貧しさと豊かさについての変奏曲』(コモンズ、2017年)
推薦者:釜崎太(教授 教養デザイン研究科 思想コース)
地域貢献や地域密着など、「地域」という言葉をよく耳にします。しかしその「地域」とは具体的に何を指し、「地域が豊かになる」とはどのようなことを意味しているのでしょうか。本書に描かれている地域の原風景は、私たちの通念に再考を迫ります。
地域貢献や地域密着など、「地域」という言葉をよく耳にします。しかしその「地域」とは具体的に何を指し、「地域が豊かになる」とはどのようなことを意味しているのでしょうか。本書に描かれている地域の原風景は、私たちの通念に再考を迫ります。
E.H.カー『歴史とは何か 新版』(近藤和彦訳、岩波書店、2022年)
推薦者:佐藤公紀(専任講師 教養デザイン研究科 文化コース)
「歴史とは、現在と過去のあいだの終わりのない対話である」という言葉で知られる歴史学の名著の新訳版です。原著の刊行からすでに六十余年を経ているにもかかわらず、むしろ歴史修正主義が勢いを増し、歴史学への信頼が動揺しつつある今だからこそ、歴史の本質を軽妙な語り口で鮮やかに浮かび上がらせた本書を読むことの意義が高まっています。
「歴史とは、現在と過去のあいだの終わりのない対話である」という言葉で知られる歴史学の名著の新訳版です。原著の刊行からすでに六十余年を経ているにもかかわらず、むしろ歴史修正主義が勢いを増し、歴史学への信頼が動揺しつつある今だからこそ、歴史の本質を軽妙な語り口で鮮やかに浮かび上がらせた本書を読むことの意義が高まっています。
伊知地英信『外来種は悪じゃないーミドリガメのための弁明ー』(草思社、2023年)
推薦者:森永由紀(教授 教養デザイン研究科 平和・環境コース)
生態系を脅かす要因として外来種が問題視されている。著者が公園で生き物説明会などをすると、生き物の名前を聞く前に「これは外来生物ですか?」と質問する子供がいるという。外来種を新たに放たないのは当然としても、池のかいぼりなどで”そこにいる”外来種をむげに駆除することには疑問を抱く私にとって、本書は既に私たちと共にある外来種との付き合い方について、まことに腑に落ちる考えを提示してくれる。人の周囲にある自然を守る理由も方法も、誰もが納得するものはあるようでないことに気付かされる。
生態系を脅かす要因として外来種が問題視されている。著者が公園で生き物説明会などをすると、生き物の名前を聞く前に「これは外来生物ですか?」と質問する子供がいるという。外来種を新たに放たないのは当然としても、池のかいぼりなどで”そこにいる”外来種をむげに駆除することには疑問を抱く私にとって、本書は既に私たちと共にある外来種との付き合い方について、まことに腑に落ちる考えを提示してくれる。人の周囲にある自然を守る理由も方法も、誰もが納得するものはあるようでないことに気付かされる。
2023年度 春学期
宮宇地一彦『デザイン脳を開く—建築の発想法』(彰国社、2004年)
推薦者:瀧口美香(准教授 教養デザイン研究科 思想コース)
自由に発想し、創造することの楽しさを知ることができる一冊。言語、身体、五感を駆使して発想するための手引き。建築を具体例として、"発想のメカニズム" を解き明かす。
自由に発想し、創造することの楽しさを知ることができる一冊。言語、身体、五感を駆使して発想するための手引き。建築を具体例として、"発想のメカニズム" を解き明かす。
梅原猛『隠された十字架 法隆寺論 改版(新潮文庫)』(新潮社、2003年)
推薦者:神田正行(准教授 教養デザイン研究科 文化コース)
「法隆寺は聖徳太子の怨霊を鎮めるために建てられた」という、センセーショナルな主張の書籍で、山岸凉子氏が名作『日出処の天子』を執筆するきっかけにもなったといいます。中学生の時に、社会科の先生から勧められて読み、古代史にハマるきっかけになりました。今読み返してみると、論証に強引なところが目立つので、これから手に取る皆さんには、批判的・懐疑的に読んでほしいと思います。
「法隆寺は聖徳太子の怨霊を鎮めるために建てられた」という、センセーショナルな主張の書籍で、山岸凉子氏が名作『日出処の天子』を執筆するきっかけにもなったといいます。中学生の時に、社会科の先生から勧められて読み、古代史にハマるきっかけになりました。今読み返してみると、論証に強引なところが目立つので、これから手に取る皆さんには、批判的・懐疑的に読んでほしいと思います。
ポール・A・オフィット著、関谷冬華訳『禍いの科学』(日経ナショナルジオグラフィック社、2020年)
推薦者:勝田忠広(教授 教養デザイン研究科 平和・環境コース)
無垢な科学的発見が、空気に流された社会によって多くの人命を奪う結果になってしまった7つの事例。流行語に落ちてしまった「エビデンスの必要性」を再考するために。
無垢な科学的発見が、空気に流された社会によって多くの人命を奪う結果になってしまった7つの事例。流行語に落ちてしまった「エビデンスの必要性」を再考するために。
2022年度 秋学期
益田勝実『火山列島の思想』(講談社学術文庫、2015年)
推薦者:伊藤剣(准教授 教養デザイン研究科 思想コース)
著者の想像力と筆力が、神話を生み出した古代人の思想を鮮やかに蘇らせる。優れた学術的文章は読み物としても堪能できることを示す好例。
著者の想像力と筆力が、神話を生み出した古代人の思想を鮮やかに蘇らせる。優れた学術的文章は読み物としても堪能できることを示す好例。
ケルテース・イムレ(岩崎悦子訳)『運命ではなく』(国書刊行会、2003年)
推薦者:広沢絵里子(教授 教養デザイン研究科 文化コース)
強制収容所に移送されたユダヤ人少年の目線から、ユーモアあふれる文体で残酷な戦争と「その後」がずっと地続きであることを描く自伝的小説。歴史への感性が磨かれる作品。
ロナルド・スティール著『現代史の目撃者 : リップマンとアメリカの世紀』(上・下)浅野輔訳 (ティビーエス・ブリタニカ, 1982年)
推薦者:鳥居高(教授 教養デザイン研究科 平和・環境コース)
1920年代以降、アメリカのジャーナリストとして活躍したリップマン。主著である『世論』(岩波文庫邦訳あり)は情報化社会の今もなお、有益な示唆に富んでいる。本書は単に彼の伝記だけでなく、政治学と心理学の融合。政治権力とジャーナリズムの緊張関係、1910年以降のアメリカ文化史、とその内容は多岐にわたり、最後に、アメリカ大統領にさえ影響力を行使得た、人物の「老い」までを描き、政治、文化、人間の生きざまさえも考えさせてくれる。既に刊行されて40年近い日々を経過したが、今日もなお、輝きを失わない。
1920年代以降、アメリカのジャーナリストとして活躍したリップマン。主著である『世論』(岩波文庫邦訳あり)は情報化社会の今もなお、有益な示唆に富んでいる。本書は単に彼の伝記だけでなく、政治学と心理学の融合。政治権力とジャーナリズムの緊張関係、1910年以降のアメリカ文化史、とその内容は多岐にわたり、最後に、アメリカ大統領にさえ影響力を行使得た、人物の「老い」までを描き、政治、文化、人間の生きざまさえも考えさせてくれる。既に刊行されて40年近い日々を経過したが、今日もなお、輝きを失わない。
2021年度 秋学期
澁澤龍彦『胡桃の中の世界』(青土社、1974年)
推薦者:井上善幸(教授 教養デザイン研究科 思想コース)
澁澤の思考の結晶学が本
書である。想像力を幾何
のデザインへと組みかえ
る知性の博物誌的饗宴を
堪能されんことを。
澁澤の思考の結晶学が本
書である。想像力を幾何
のデザインへと組みかえ
る知性の博物誌的饗宴を
堪能されんことを。
藤井青銅『「日本の伝統」という幻想』(柏書房、2018年)
推薦者:加藤徹(教授 教養デザイン研究科 文化コース)
これは日本古来の伝統だから守れ、という「伝統マウンティング」に騙されるな。伝統の大半は、実はビジネス目的の近現代の創作。偽物を見分ける「伝統リテラシー」をもとう。
これは日本古来の伝統だから守れ、という「伝統マウンティング」に騙されるな。伝統の大半は、実はビジネス目的の近現代の創作。偽物を見分ける「伝統リテラシー」をもとう。
2021年度 春学期
マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソン、斎藤幸平 『未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か?』(集英社新書、2019年8月)
推薦者:岩野卓司(教授 教養デザイン研究科 思想コース)
資本主義の危機、環境破壊、AIの危険な支配という未来を、我々はどう克服したらいいのだろうか。
資本主義の危機、環境破壊、AIの危険な支配という未来を、我々はどう克服したらいいのだろうか。
福田恆存 『演劇入門 -増補版』(中公文庫、2020年8月)
推薦者:畑中基紀(教授 教養デザイン研究科 文化コース)
生きるとは〈ことば〉を使うこと。〈ことば〉が秘めたパワーに気づくことで、きっと、あなたの人生が変わる。
このパワーを最大限に引き出すのが演劇だ。
本書を読んでシモキタに行き、役者の身体から発せられる〈ことば〉のエネルギーに触れよう。
生きるとは〈ことば〉を使うこと。〈ことば〉が秘めたパワーに気づくことで、きっと、あなたの人生が変わる。
このパワーを最大限に引き出すのが演劇だ。
本書を読んでシモキタに行き、役者の身体から発せられる〈ことば〉のエネルギーに触れよう。