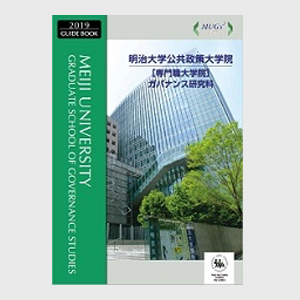進学説明会・オープンキャンバス
明治大学ガバナンス研究科の魅力を直接体験できるイベント
Master of Public Policy, MPP
公共政策のプロフェッショナルを育成するガバナンス研究科
新型コロナウィルス感染症は現在(2020年10月下旬)でも収束の兆しは見えない。日本国内の新規感染者数は9月上旬からほぼ横ばい状態である。世界的に見ても最も感染者数の多い米国や9月に急増したインド等で増加ペースが鈍化しつつある一方、東南アジアの複数の国で増加傾向にある他、ヨーロッパでも再拡大の様相を呈している。こうした中、経済への打撃を減らすため、各国では一時期の「緊急事態宣言」や「都市封鎖」といった強硬手段をとらず、感染拡大を避けつつも経済・社会活動を行う「新しい日常」の導入が進んでいる。来年には有効なワクチンや治療薬が開発されると期待されるが、どこまで有効かは未知数である。人間の活動による生態系の変化や生物多様性の減少、そして加速するグローバル化が今回のパンデミックを生んだことは確かであり、今後も別の新型感染症が流行する可能性は常に存在する。こうした点から、感染症拡大防止を常に念頭におく生活が今後も続いていくことが予想されるだろう。それでは、この「新しい日常」において、私たちの社会はどう変わっていくのだろうか。本稿ではこの点を「人と人の繋がり方」、特に「コミュニケーションのあり方」に焦点をあてて考えてみたい。
感染拡大防止のために当初から言われ、今でも重視されているのが「3密(密閉・密集・密接)を避ける」こと、或いは「フィジカル・ディスタンシング(身体的距離を置くこと)[*1] 」である。これによって人と人の出会い方に大きな制限がかけられることになった。具体的には、(1) 会えない、(2) 集まれない、(3) 遠くに行けない、の3「ない」である。まず「会えない」は対面で密接に会話することによる感染リスクを減らすため、普段一緒に暮らす人以外とは、基本的に長時間(マスクなしで)近接して会話することができない、ということ。これで親しい仲間であっても、或いは仕事で必要であっても、対面して自由に一定時間以上会話することが難しくなった。次の「集まれない」は「会えない」の拡大版だが、ある程度の人数が一つの場所(特に屋内)に集まり、話し合ったり何か一緒に作業をすることを避ける、という考えである。これにより様々な会合や共同作業、さらには種々のイベントや公演等が行われなくなった。そして最後の「遠くに行けない」は人の移動によって感染が広がることを防ぐために、緊急事態宣言中は県境を越えての移動自粛が求められ、今でも国境を越えた人の移動が大きく制限されていることである。これによって観光を含む様々な経済活動に影響が出ているが、それに加えて「普段あまり会えない人同士が繋がる」「異なる文化背景を持った人たちが出会う」ような場を持つことが難しくなった。
このように人と人の出会い方、集まり方に大きな制限が掛けられた一方、脚光を浴びたのが、テレビ会議システム等を使ったオンラインでのコミュニケーションである。筆者も最初は戸惑いとともに恐る恐るZoomによるミーティングや授業を始めたが、今では多くの仕事や活動の場で「リモート会議」や「オンラインイベント」が普通になっている。さらに最近では対面での話し合いや授業の場にオンラインでも参加できる「ハイブリッド型」の導入も様々な現場で取り組まれているようである。
こうして「オンライン」でのコミュニケーションが「新しい日常」を構成するようになったが、もちろんデジタル・ディバイド (情報格差)には留意する必要があり、オンライン環境を使えない人たちへの配慮が求められる。また一方で、人と人が対面で出会ったり集まったりすることの重要性も再確認されつつあるが、上記「3ない」の状況ではこれまで通りのコミュニケーションをとるのはなかなか難しいことも確かである。「新しい日常」において、よりよいコミュニケーションとはどうあるべきなのだろうか?このことを考えるにあたって、まず「コミュニケーションとは何か」を整理してみたい。
[*1] 当初は「ソーシャルディスタンス(社会的距離)」と言われていたが、WHO(世界保健機関)は「人と人の繋がりは保ってほしい」という意味で「物理的距離」という言い方を使っている。(東京新聞4月25日https://www.tokyo-np.co.jp/article/17045)
「導管メタファー」という考え方がある(中原・長岡、2009)。これはある人(Aさん)から別の人(Bさん)へ、導管を通したように、何らかの情報がそのまま伝えられる、というコミュニケーションのイメージである。中原・長岡によれば、こうしたイメージはビジネスの現場でも、そして近代的な学校教育の場でも一般的にであるという。情報や知識を「AからBへ」いかに効率的に伝えるか、がコミュニケーションのカギである、という考え方だ。
しかし果たして、「Aさんの考えやメッセージがBさんにそのまま伝わる」ことは本当に可能なのだろうか。まずAさんは、自分の経験なり考えを「言葉」にして伝えることになるが、Aさんの経験や考えはその「言葉」に100%表現されているのだろうか?そしてAさんの言葉を受け取ったBさんは、その「言葉」からAさんの考えや経験をそっくりそのまま理解することができるのだろうか?
ここでのポイントは、私たちのコミュニケーションの多くの部分は「言葉」によってなされる、ということだ。そして言葉というのは、たとえ同じ単語や文章であっても、人によって、或いは時によって、それが各人に「意味するもの」は異なってくる、という特徴がある。だからAさんは自分の経験や考えをある「単語や文章」にして表現したとしても、それがAさんが本当に伝えたかったことをうまく表しているかどうか誰も分からないし、その「単語や文章」を聞いたBさんが、どう考え、何を感じたのか、についても他人にはよく分からない。つまり、コミュニケーションは「導管のメタファー」のようにはいかない、ということだ。
ではどうしたらいいのか。ここで大事になってくるのが、「双方向のやり取り」である。Aさんが何かを語る。それに対してBさんが反応する。その反応をうけて、Aさんがまた語りなおす。そういう継続した双方向のやり取りを通じて、Aさんが語りたかったことをBさんは自分なりに理解できるかもしれないし、Aさん自身もBさんの反応を通じて新しい考えを見つけるかもしれない。このプロセスを、中原・長岡は社会構成主義の観点にたって、「対話」と名付けている[*2]。変化の激しい現代社会においては、多様な人たちが出会い、話し合い、何かを生み出していくプロセスが重要であり、その視点からも「対話」こそがコミュニケーションの中心である、と言えるだろう[*3]。では対話とは何だろうか?
[*2] 社会構成主義についての入門書はガーゲン(2018)が分かりやすい
[*3] このことについては暉峻(2017)を参照
物理学者でありながら経営論やリーダーシップ論に大きな影響を与えたと言われるデヴィッド・ボームはその著書『ダイアローグ』で対話について、「話し手のどちらも、自分がすでに知っているアイデアや情報を共有しようとはしない。むしろ、二人の人間が何かを協力して作ると言ったほうがいいだろう。つまり、新たなものを一緒に創造すること」としている(ボーム、2007年)。英語の「Dialogue」はギリシャ語の「Dialogos」から来ていて、「Logos」は言葉、「Dia」は「~を通して」という意味だが、ボームはここから、対話という言葉は「グループ全体に一種の意味の流れが生じ、そこから何か新たな理解が現れてくる可能性を伝えている」と解釈している。
こうした「新たな理解が現れる」対話の特性を最大限に表していると思えるのが、「オープンダイアローグ」である。これはもともとフィンランドの一地方で急性期の統合失調症患者への治療方法として開発されたもので、患者とその家族や親戚、医師や看護師、心理士等、本人に関わる人たちが集まり、全員による「開かれた対話」を継続的に行うことによって、殆ど薬物を使わずに抜群の治療成績が証明されている(斎藤2015)。オープンダイアローグを支える考え方は「ダイアローグの思想」と呼ばれており、その理論的な柱の一つがロシアの思想家ミハイル・バフチンによる対話の考え方である。社会的現実はポリフォニー的(多声的)で、話し手と聞き手の間に作り上げられるものであり、対話は共有された新しい現実をつくりだす(セイックラ/アーンキル2016、第5章)。オープンダイアローグでは、開かれた対話を通じて、患者が自らの体験を言葉にし、周りの人たちが応答する。そのやり取りを重ねることで「新しい現実」が生み出され、患者を取り巻く関係性も変化してき、結果として患者の症状が改善していく、と考えられる。
さて、この話は果たして統合失調症の患者さんだけに当てはまるものだろうか?ある人が、何かを発言するとき、それはその人自身の中で、ゼロから湧き出したものだろうか?いや、そうではない筈だ。それまでにその人がどこかで誰かとの関係の中で考えたこと、感じたことの結果として、「考え」や「感情」が言葉になり、それを発すると、今度はそれを受けた誰かが何らかの反応をし、二人の間で現実が生まれる、と言えるのではないか[*4]。こう考えると、「現実」は過去から現在、そして未来に至るまで人と人の関係を通して常に作られ続けていることになる。だから、新たな意味を創造する「開かれた対話」がなければ、新しい現実、つまり社会の望ましい変化は生まれないことになる。
[*4] このことを社会構成主義の第一人者ケネス・J・ガーゲンは最新の著作のなかで「境界画定的存在から関係規定的存在へ」と位置付けている(ガーゲン、2020)。
それでは、一方的な情報の伝達や意味が固定された会話ではなく、「新たなものを一緒に創造する」ような対話はどのようにして生まれるのだろうか。筆者は長年関わっているNPO[*5]を通じて、いわゆる途上国において協働による課題解決を促進するコミュニティ・ファシリテーターの育成研修や、地域づくりの現場同士を(国境を越えて)繋ぎ、学びあう活動を行ってきた。そこでは「対話」を可能にする場をどのようにして生み出せるかを試行錯誤しており、その経験から、対話を成立させるための条件として次の4点が重要であると考えている。
[*5] 一般社団法人あいあいネット(http://www.i-i-net.org/)
上記の4点のなかで、オンラインによるコミュニケーションでもほぼ確実に成立すると考えられるのは①安全・安心な場と②双方向性の2点だろう。特にリモートの場合は自分の馴染んだ場所(家等)で繋ぐことが可能なので、「安心・安全」は実現しやすいと考えられる。ただ、②の「相手がしっかり聴いてくれている」というのをオンラインの小さな画面上で確認するのは難しい面がある。相手の言ったことに大きな身振りで反応しつつ、しっかり応答する、という基本を守ることが必要だろう。
一方、③「沈黙と相づち」については、今使われているアプリケーション(Zoom等)では、沈黙は画面がフリーズしたと思われかねず、相手の言葉に重ねて発声する相づちを打つと相手の音声が途切れてしまい、自然なやり取りになりにくい。ただ、この点はアプリやハード面の改良で何とかなる可能性もあるだろう。しかし④の「空間の共有と身体性」を、オンラインによるリモート環境で実現するのは難しそうだ。この点を別の形でどう乗り越えるか。既にさまざまな組織や活動の場で、オンラインを通じた対話の場作りの試みが始まっている。こうした実践を通じて、「ウィズコロナの時代」における「開かれた対話」はどう作られていくのか、フォローしていきたいと考えている。