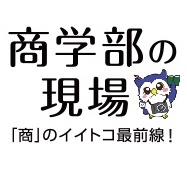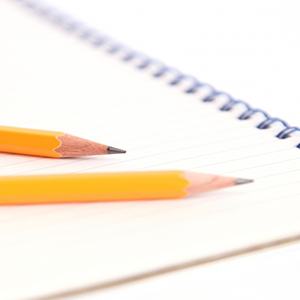2026年02月03日
1.実施日
2019年12月6日(金)10:50~12:30
2.実施場所
駿河台キャンパス リバティータワー 1116教室
3.科目名
環境科学B
4.テーマ
科学と外交政策から読み解く日本の捕鯨問題
5.ゲストスピーカー
石井 敦 (東北大学 東北アジア研究センター 准教授)
6.実施内容
日本は国際捕鯨取締条約から昨年末に脱退し、今年の7月から31年ぶりに商業捕鯨を再開した。しかし、国内の鯨肉の需要は減り商業捕鯨の採算がとれる目途も立たない中で国際社会からの批判を受けながら脱退したことについて、東北大学東北アジア研究センターの石井敦准教授にお話しいただいた。石井先生は、国際捕鯨委員会(IWC)には7回オブザーバーとして参加され、捕鯨外交について2冊の書籍のほか、数々の論文を執筆されている。
石井先生は最初に社会科学における方法論の重要性を述べられた。反実仮想を用いて日本の捕鯨外交を批判的に読み解くという手法について説明された上、捕鯨に関しては国内で虚偽情報があふれているとして、次の例が挙げられ、検証された。1.クジラを守る理由は可愛いからだという欧米の価値観の押し付けがある 2.捕鯨は「日本の文化」である、3.増えすぎたクジラが漁獲高の減少の要因であるという食害論、ほか。
商業捕鯨再開にあたり「鯨類に対する異なる意見や立場が共存する可能性すらないことが、誠に残念ながら明らかになった」という談話が政府から発表された一方で、IWCでの反捕鯨の論点がクジラは資源の弾力性が極めて小さく保護が難しいことや、一瞬で捕殺することが不可能なために苦痛を与える点などにあることが紹介された。
国際捕鯨委員会から脱退した上で捕鯨を実施することの最も重要な問題は、捕鯨を国際機関を通じて実施するという国連海洋法条約65条に違反していることだという。IWCに留まりながらの商業捕鯨の再開が可能であるにも関わらず脱退をして捕鯨を実施することが不安定で、需要が拡大するかは不透明であることが指摘された。
森永 由紀 (科目担当教員)