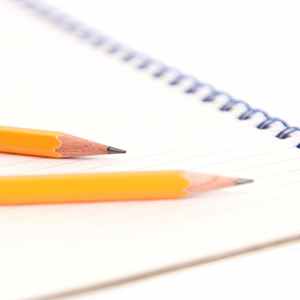学部別入学試験
出題のねらい
Go Forward
2024年10月02日
明治大学 情報コミュニケーション学部
川島ゼミナールでは2024年8月2日~8日に新潟県佐渡市・羽茂地区・小木地区で地域課題の研修を行いました。この研修は佐渡市独自の「大学と域学が連携した地域づくり応援事業補助金」を受けて行われたものであり、佐渡観光交流機構、佐渡市農林水産振興部、羽茂支所、JA佐渡、羽茂農業振興公社、さどやニッポン、北雪酒造、果樹農家など多くの地元の方の支援を受けて実施することができました。
プログラムは羽茂支所での羽茂の名産・おけさ柿の販売振興、新規就農者や移住者支援などについて意見交換会を実施し、農林産業・観光産業などの視察・研修を実施しました。また就農者宅への訪問では、学生との質疑応答を通じて都会からの転職から就農までの経緯について興味深いライフ・ヒストリーを伺うことが出来ました。
◯古民家再生への一歩
今回の活動では、佐渡市羽茂大橋地区にあるゼミ生の曾祖父母の古民家を学生の宿泊施設として利用しました。そもそも、滞在する先からの整理と整備から始めたわけです。全国的な課題となっている空き家問題へのアプローチとして、滞在中には古民家の掃除と片付けを手伝い、学生全員が空き家問題の課題である「維持すること」の大変さを実感しました。以下はゼミ生のコメントです。
「築100年の古民家に張り巡らされた蜘蛛の巣や、巻きついた植物を綺麗に掃除したり、2階に残された桐タンスをひとつずつ片付けていったりしました。都市部に暮らしているとなかなかできない経験になりました。人がすまないことで家が朽ちていってしまうということや、空き家を維持することの大変さ、難しさを身をもって感じました。」
今日、佐渡島は少子高齢化が進み、多くの民家やホテルまでもが空き家となってしまっている現状があります。また、所有者はいても、実際にそこには住んでいない家屋も数多く存在します。このような空き家問題に対して、私たちは何ができるのか、今回滞在した古民家のさらなる活用法なども含めて考えていきたいと思います。
【古民家屋内の古い家具の搬出から始める】
【庭にあふれる整理品の数々】
【佐渡のスイカで一息!】
【片付いたところで一枚】
【臨時ゼミハウスとなりました】
◯佐渡市羽茂地区の農業と自然
私たちが滞在した羽茂地区は、佐渡市の中でも特に果樹の栽培が盛んで、代表的な果樹として「おけさ柿」や「ル・レクチェ」があります。果樹農家の方からおけさ柿やル・レクチェの栽培方法や栽培スケジュールについて教えていただき、実際におけさ柿の摘果作業をお手伝いをしました。また、果樹の栽培に関わる羽茂農業振興公社やJA佐渡の皆様との意見交流会を通じ、離島ならではの販売・流通の課題を実感しました。現在羽茂地区では、果樹農家の新規担い手の不足が大きな課題となっており、農業振興公社による「果樹ワーホリ」や、農業実習生への研修など、担い手確保に対して様々な取り組みが行われています。
私たち学生目線からも、より持続可能な果樹農家の担い手確保に関する取り組み等を考え提案していきたいと考えています。また、11月初旬に予定している2次派遣の際には、おけさ柿が収穫の時期を迎えるとのことなので、ぜひその様子や味も取材させていただけたらと考えています。
さらに、羽茂地区では野生のトキを観察することができます。実際に川島准教授やゼミ生が羽茂地区の田んぼの上を飛ぶ野生のトキを観察・撮影しました。トキ保護センターによる育成と放鳥の結果、現在、佐渡島内に500羽以上の生息が確認され、羽茂地区はその生息地の一つとなっています。
【羽茂支所にて農業関係者との意見交換会】
【おけさ柿の剪定作業の研修】
【農業指導の方の話を聞く】
【上空を悠々と舞うトキ】
◯南佐渡での観光と課題
先日、ユネスコの世界文化遺産に登録された佐渡金山をはじめ、佐渡には、歴史的な史跡や、海、山などの豊かな自然といった観光資源が豊富です。そんな佐渡の観光が抱える課題などについて、南佐渡観光案内所所長の金子さんと意見交流をしました。佐渡においては、島内を移動する二次交通の不足や、高齢化によるバス・タクシーのドライバー不足が深刻な問題となっており、バスの免許が島外でしか取得できないため、新たなドライバーの確保も難しい状況だということがわかりました。また、佐渡島は東京23区の約1.5倍の大きさがあります。島全体を効率よく回るには、緻密なスケジューリングが必要であるものの、「島の大きさ」についての誤解が多く、無謀とも思える日帰り旅行を考える観光客が少なくないという話も聞きました。さらにコロナ禍以降、海外からの観光客が増加しており、特にアジア以外の国々からの訪問者も目立つようになってきたものの、交通や英語対応など、受け入れ態勢には課題が残ると話されていました。
こうした課題に対し、島の人々の気さくな人柄や、佐渡党内における地域ごとの特色をうまく発信し、より持続可能な観光客誘致、そしてリピーターの創出につなげる取り組みが必要であると感じました。
【佐渡観光交流機構・南支所での研修】
【たらい船の実地研修】
◯佐渡の日本酒
「北雪」は佐渡の代表的な日本酒の一つです。私たちは、佐渡島南東部の赤泊地区に拠点を置く株式会社北雪酒造を訪問しました。北雪酒造は佐渡に5つある酒蔵のうちのひとつで、その中でも特に島外・海外輸出に積極的な酒蔵です。6代目社長の羽豆大さんから、近年の日本酒事情や佐渡での日本酒作りの苦労、北雪酒造のブランディングなどについてのお話を伺い、さらに実際に清酒の抽出で用いられている遠心分離機や超音波スピーカーを取り付けたタンク、音楽を聴かせて熟成を促す地下蔵内部を拝見するなど、貴重な体験をさせていただきました。最後に吟醸酒と大吟醸酒の飲み比べや梅ジュースの試飲もさせていただきました。「北雪」が、地元佐渡の豊かな「食」と世界的に知名度の高い「和食」の両面で大きな役割を担う存在であることを実感しました。
【酒造会社前にて】
【醸造工場内の見学】
【北雪酒造の一品の数々】
一週間の研修を通じて羽茂地区の農産業・醸造業といった地場産業と観光産業、そして、佐渡地域文化の鬼太鼓の担い手の方々による様々な現代化への取り組みのお話、そして、ゼミの主題の一つでもあった首都圏からのロジスティクス・アクセスなど、これ以外にも多くの地域課題を学ぶことが出来ました。現在、来年二月の報告書作成に向けて二次派遣の準備中です。