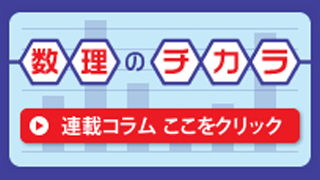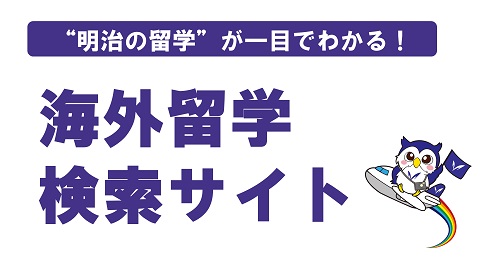ボールペンを使う目的は字を書くことです。しかし我々は文字を書く際にその構造を意識してはいません。私はコンピュータもそうあるべきだと思っています。私の研究の目標は人とモノ、モノとモノの高度なコミュニケーションによって社会を便利にすることであり、言い換えれば、存在を意識せずにコンピュータを使えるようにすることで社会全体をより豊かにすることにあります。
そのための研究の一例に参加型センシングがあります。これは何百人もの人が街でセンサを持ち歩いて情報を集めることで街全体の情報を得ようとする考え方で、その例が右下の写真の研究です。スマホを自転車に取り付けて皆が走ることで、搭載された加速度センサとGPSを利用して急な回避を要した場所や人混みを避けて走った場所などがわかり“自転車交通安全マップ”が半ば自動的に作れます。実は、このようなセンサの計測値から人間や実世界の状況を推定するために、隠れマルコフモデルという数学の確率過程が使われています。技術が進めば、情報から標識設置や補修工事の有無を判断することもできるでしょう。
人間の活動は確率と深く結びついています。モノとモノのネットワークの構築も人間同士の対話のルールが非常に参考になります。私たちの研究は人間を学問的に捉えることが大切です。皆さんにはぜひ教科書の数学を土台として実世界に一歩踏み出してほしいと思います。