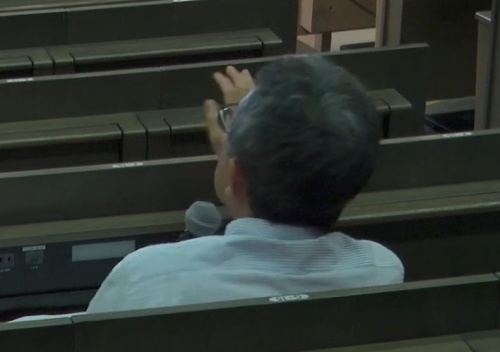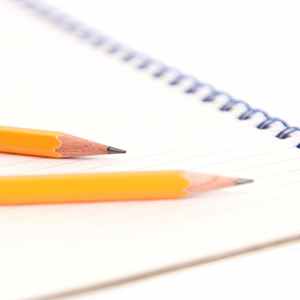2026年02月03日
「ガクの情コミ」学際研究ラボ テーマ「流行」
INDEX
総合討論(コーディネーター 高馬京子 教授)その3
【映像】
総合討論その3
後藤報告をめぐって
① コメント
高馬:3人目の登壇者である後藤先生の報告にコメントをいたします。
「流行は造ることができるか」というテーマでの報告、興味深く伺っていました。
質問としては、メディアの発達・変化によって、先ほどお話のあった、バンドワゴン効果、スノッブ効果、そして今回はあまり触れられませんでしたが、ヴェブレン効果の組み合わせに変化は生じてきているのか、という点があります。
効果に名前が冠されているヴェブレンは『有閑階級の理論』(1889年)の中で、流行を追えるのはエリート層の有閑階級、暇のある階級の人の誇示的消費だと述べています。こんなにお金を持っているのだと見せるための消費ですね。
ただ、メディアが発展して、流行が大衆にもどんどん広がっていく中で、おそらく何かが変わってきていると思います。メディアはかつてはマスメディアだったのが、各種SNSが出てきました。こういったことによって、消費者や作り手との関係も変化していると思います。このあたりについてお伺いしたいと思います。
② 行動経済学と法
今村:後藤先生には、行動経済学と法との関係をお伺いしたいのですね。日本でも行動経済学に関して、本屋さんに行くとたくさん本が置かれていますね。言葉は悪いですが「これで金もうけ」のような感じの本です。行動経済学は金もうけに利用される気がしますし、それによって人々の自由な意思をゆがめながらものを買わせるような、商売のテクニックのようなことを教える悪い輩も出てきている気がするのですよ。
そういったことについて行動経済学は、例えば、景品表示法の優良誤認、あるいは有利誤認に抵触するなどといった、法律のことも考えてきちんと議論しているのか、それとも経済学は経済学ということで分けて、あとは法律家の人が駄目なものは駄目と言ってくださいという割り切りでやっているのか。その辺、ざっくばらんにお教えいただければと思います。
③ 行動経済学の観点からみた、自由と保護
後藤晶(以下後藤): まずは高馬先生のコメントに関してです。デジタルメディアの発展によって、流行が可視化されているという側面もあるように思います。要はツイッターだったりインスタだったりで、皆さん「いいね」とか「映える」、「インスタ映え」とかをいろいろ意識されていると思います。現在はこうして流行が可視化されて、それが必ずしもマスメディア発ではなく、個人発の流行というものがどんどん増えてきました。そういう意味では、流行を造る人がどんどん増えてきたかと思います。
一方で、これは流行だと思わされるようなステマだったり、そういう広告が行われていることが問題となっています。いろいろなSNSが発展して個人が自由に発信できることになった反面の課題として生じている点です。
このことは今村先生の質問にもつながります。つまり行動経済学の観点の中で、法律のことを考えているのかという話です。
もちろん法律についての観点や議論はあります。それこそ消費者をどこまで守るべきかという、そういう権利保護のパターナリスティックな観点があります。それと同時に、どこまでの自由を認めるか、というリバタリアン的な観点からも考えます。消費者の自由を認めますが、一方で消費者が失敗するのも自由です。もちろん致命的な失敗はさせないよう保護する必要はあると考えています。二律背反的な状況になっています。ただ、結構難しい論点であることは間違いありません。まさにいま、景品表示法などをステマ規制との関連で研究をしようという話を受けています。「ステマ」「広告」と明示すれば法律の要件は満たすけれども、ステマをステマだと思えない、もしくはステマに対してステマだと分かっていても、その商品を買ってしまう消費者がいます。ステマをステマと思えない消費者がいる以上は保護ができているとはいえない。これは少々難しい論点ですね。
あと、流行の話にいきますと、校則は流行を「逸脱」とみている、というお話があったかと思います。「逸脱」として、行き過ぎた行為が生じることもあります。先ほどのSNSの話でいけば、いわゆる「バカッター」と呼ばれる犯罪や非行をさらけ出す行為が次々と明るみに出たことがありました。これも規制の話としてつながってくるかもしれません。流行における逸脱については課題もあるかと考えています。
流行をめぐる性規範・ステマの線引き
須田努:今回の流行についての自由と規制がごくうらはらの関係だということがよく分かってきたと思います。特に鈴木先生の報告では、それがとても出てきていました。
今日話題に出なかったことで、少し言いたい点があります。日本の制服の誕生は軍隊の影響があります。日本の近代教育の導入で一番重要なのは、国民の形成にあたって、時間による規制という概念を持ち込むことでした。そのことと軍隊で導入された制服が学校に持ち込まれることは関係していると思います。
もう1つ、流行と規制とを考えていきますと、ものすごく性規範が強いと思うのです。例えば、男性は流行を追うなという環境が、すごく強い。流行を追うのは女性であって、男性はそんなものを追っている場合ではないのだとか。それがまだとても強くて、学校でも見えないような形にしても、それがあるのではないかと思いました。
それから、ステマの話です。私はナイーブな消費者なのかもしれません。ステマの線引きはとても難しいものです。例えばYouTubeで商品の紹介──私の場合で言えばギターの紹介なんですが──を観ていると、良いことしか言わないわけです。映像を観た私は次の日に紹介されたギターを買いに行きます。そこでギターを買ってきて、私はとても幸福になるわけです。そういう問題もあるので、規制をどこまでしてしまうかというのも、少し気になるところです。
高馬: 流行をめぐる男女に関してフランスの例を1点申し上げます。フランスのルイ14世の時代というのは、ファッションを追えるのはエリート層でした。そしてエリート層の男性も女性も大変におしゃれだったわけです。いわゆる庶民は流行を追うものではなかった。ところが、フランス革命で市民が台頭します。そうすると男性はキュロットなどははかない(「サン・キュロット」Sans-culotte)感じになっていき、貴族のような格好をしなくなります。それに対して華美になり、富を見せるのはヴェブレンではないですけれども、女性の役割でした。
そのように、時代の流れの中で、それがどこの時代のものを引き継いで、それがどう定着したのか、ということを歴史的にみてみる必要があるのかな、と思いました。
学際的に「流行」をみる
今村:私は個人の自律的な意思決定というものを近代の社会ではやはり重視するべきと思います。
高馬: 流行とは何か、という答えを出すというより、流行をめぐって学際的に意見交換し、いろいろな課題が出てきて、いろいろな切り口でいろいろな問いを立てることができていく。それがまた結びついて、今まで考えられていなかったような新しい課題も見えてきたのではないかと思います。
それは学校の生徒についても同様です。ただ他方で、パターナリスティックな対応をしなければいけない部分も、まだまだあるような気がします。校則がそれにマッチしているかどうかは、全然違う話だとは思いますが。
自律的な意思決定とは幻想のような気もしてきます。とくに先ほどの行動経済学の知見からみると、人間は合理的な判断がうまくできなくてバイアスというか、認知がうまくいっていないところもありますよね。そこは人間としてもう少し成長すれば、須田先生のように変な買い物をしなくなるといったことがあるのか。「何とか効果」と呼ばれるものも、一歩下がって考え直せば、引っかからないものだとすれば、多分それは是正するべきもののような気もします。そのようなことも考えながら、いろいろな勉強をいたしました。
鈴木:校則は、あくまでも公教育の話です。公権力が私としての個人をどこまで規制できるのかということなのです。ですので、もちろん大人が子どもに対して、もう少しこうしなければいけないというのは当然あるのですけれども、それは私的領域でやってくださいということなのです。保護者の方、あるいは周りの友人や、そういう中で何が好ましいのかがおのずと育っていけばいいということなのです。
学校教育が、全ての子どもに毎日、こうでなければおかしいのだということを押し付けていることは問題があるというだと思います。あくまでも公権力の作動としての校則というものの問題点なんですね。
良いことを言っているのだから良いではないかというのは、それはまた違います。あくまでも、それは個人的な私的な領域でやってください、ということです。ですから先ほどの須田先生のご意見の中にあった性規範の問題であるとか、そういったことも極端なことをいえば各家庭で考えていくことです。もちろん、誤ったジェンダーのようなものがあったならば、それについてはさまざまな社会との関わりの中で変えていかなければいけません。そこに教育ができることもあると思うのですけれども、個人の価値観に関することをある特定の方向へ導いていくようなあり方というのは、かなりリスクがありますし、眉唾で見ていかなければ危ない部分があるのだということを知っておく必要があると思います。
その根っこにある自由意思問題なのですけれども、そう考えると、流行に流される自由というものを認めても良いのではないのかということです。買って満足ということも当然あるわけですし、リテラシーの問題などもありますが、被害に遭った時に初めて、そこの被害に遭わないようにという教育は出てくると思うのです。そこに教育ができることはあるのですが、「だまされちゃ駄目だぞ」と教育が言うと、それは少しお節介という感じもしないではないかと思います。
いろいろな権利の話であるとか、行動経済学を含めて、大変勉強になりました。ありがとうございました。
後藤: 須田先生がギターを買ってハッピーになれば、それはそれでいいのではないですかというのも1つの結論です。もちろん、そういう考え方もありますし、それはきちんと広告を見てものを買うというのは、ある意味今の経済社会として認められる自由な消費行動だと思います。
一方で、もし誤った情報に基づいてその商品を買っているのであれば、それは疑問の余地があるかもしれません。どこまで保護すべきなのかは、非常に難しい問題にもなりますし、行動経済学と法律が関わってくる部分の議論が必要になるのかと思います。どこでラインを引くのかというのは結構難しいと思う次第です。
今回いろいろお話を伺って、また迷子になった気がします。こうやって幅広いお話を伺って悩んで楽しんで生きるのは、情報コミュニケーション学部の良いところかなと思っています。
高馬: 流行とは何か、という答えを出すというより、流行をめぐって学際的に意見交換し、いろいろな課題が出てきて、いろいろな切り口でいろいろな問いを立てることができていく。それがまた結びついて、今まで考えられていなかったような新しい課題も見えてきたのではないかと思います。
皆さまの中でもそれぞれこの続きとして、流行とは何かについても考えていただければと思います。
- お問い合わせ先
-
教務事務部 情報コミュニケーション学部事務室
駿河台キャンパス
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL.03-3296-4262~4
✉ infocom■mics.meiji.ac.jp ※■を@に置き換えてください。
和泉キャンパス
〒168-8555
東京都杉並区永福1-9-1
TEL.03-5300-1627~9