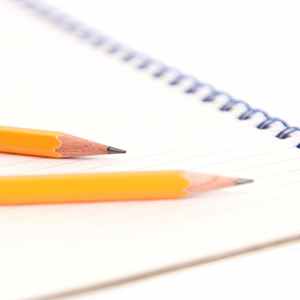2026年02月03日
「ガクの情コミ」学際研究ラボ テーマ「流行」
INDEX
総合討論(コーディネーター 高馬京子 教授)その2
【映像】
総合討論その2
鈴木報告をめぐって
① コメント
高馬:2人目の登壇者である鈴木先生の報告にコメントいたします。
流行と校則というテーマに関して興味深く聞かせていただきました。私の通った高校には制服とか校則がありませんでした。ですが、一方で隣の学校のかわいい制服を結局着ていたな、ということも思い出しました。
先生にフランスの例を少しご紹介いただきました。フランスの制服事情をみると、エリートや富裕層が住む地区のカトリック系の学校や私立学校では採用されていたのだけれども、公立学校ではようやく2018年に初めて制服が導入されたといいます。そこで制服が導入された理由というのは、社会的な差別を見せないために制服を導入したのだ、と報道されています(https://www.afpbb.com/articles/-/3196286)。
校則はないけれども、制服を着たということなのですね。そこで制服が導入された理由というのは、社会的な差別を見せないために制服を導入したのだ、と聞いています。
そこで、日本の校則とか制服のありかたというのは、日本社会独特のことなのか。日本文化としての校則や髪形の制限などの背景について、お考えをいただきたいと思います。
② 私的領域に関与しない公教育
鈴木雅博(以下鈴木): 高馬先生から社会的差別を是正する方策の1つとして、フランスでも制服などを導入する動きがあることなどのご指摘がありました。
基本的な考え方としては、公教育は私的領域には関与しないのが基本的なスタンスだと思うのです。公教育は、公的なある種の権力作用でもあるわけです。市民の育成という部分について教育は行うけれども、宗教であったり服装であったり、そういった部分については基本的には公権力、公教育はノータッチです。
まさに逸脱として、本当に露出が大きい、下着が見えてしまうような服を着てくる場合には、それはいわゆる公序良俗の範囲という形で、やはり一定程度の規制というのはあると思います。しかし服装は基本的には自由な領域として担保されます。
しかし、ご指摘いただいたように、階層の差であるとか、それぞれの環境の差であるとか、思想とか宗教の差というものが、服装によって現れることは、ままあるわけです。そこで結果何をやるのかというと、そういったことは持ち込んではいけない、ということになっています。
たとえば宗教に関しては、イスラム教徒が女性はイスラムの考えに基づいた服装をしてくることとか、スカーフをかぶってくるとか、そういったことについてはライシテ(laïcité 宗教的な中立性)として、禁止しているわけです。これはもちろん、イスラムというマイノリティーにとっての差別ではないのかとフランスでも大変論争になったところではあります。一方でキリスト教徒も大きな十字架のようなネックレスを着けてくること自体禁止されているそうです。
基本的に個人的な領域について学校は関与しません。自由が原則です。しかし、そういったものを学校の中に持ち込むということについては、一定程度の制約や規制が行われます。その差別を持ち込まないように制服を、というのも1つの動きだとは思うのですけれども、恐らくこれは非常にマイナーな、それほど一般化していない動きだとは思います。
③ 日本における制服の家計負担
鈴木:日本の場合、制服を着させることに、経済的な負担を考えていたり、経済的な差別化というものがあらわにならないためなのだというロジックが語られることがあります。ただ、実際制服の価格はどうでしょうか。ご家族に制服を買われたことがある方はご存じと思いますが、制服は大体4~5万円してしまうのです。制服は3年間で着なくなる。高校3年間で終わり、中学校3年間で終わりです。
高馬:着替えも要るし。
鈴木:そう考えると、制服は非常にコスパが悪いです。経済的な平等を謳っていながら、高額なお金がかかる。先ほどのファストファッションの話ではないのですけれども、子どもに5万渡して、これで3年間私服を買いなさいといえば、十分買えると思うのです。なおかつ、それは3年という期間限定ではなくて、もっと長い期間着ることができるはずです。
実は学校が、過度な経済負担を家庭に課している側面が一方にはあるわけです。また、学校の指定制服を取り扱える店が非常に限られていて、なかなか価格競争も起きにくいという現状があります。また、学校の名前が入ったリュックを持たなければいけないとか、上履きはここで買ってくださいとか、体育シューズはここが指定といった形で、学用品が指定製品であることによる、隠れた教育費の高騰に関する研究もあります。
数年前に話題になった、中央区立泰明小学校のアルマーニ製の制服の話もありました。それが10万円近くするという話になっているわけです。ラグジュアリーブランドの制服を着ていることによって晴れがましい気持ちにはなるのでしょうけれども、公立小学校なのにもかかわらず、ある種そういった差異化が悪い意味で働いてしまうのではないか、と論争になりました。
今回流行を押しとどめるために校則があって、制服や頭髪についての規制があるという形でご紹介したのですけれども、実際は制服にも流行があるのです。
具体的には、時期によってスカートが長くなったり、短くなったりとか、その着こなしの仕方といったことですね。何年か前ですけれども制服図鑑のようなものが発刊されて、それを基に女の子が、どこの制服がかわいいかなと見て高校を選ぶようなこともあったわけですので、制服自体が完全に流行から自由になるかといったら、そういったことではないという部分も考えていく必要があると思っています。今回はその点については、踏み込みませんでした。
日本の校則とか制服のありかたというのは、日本社会独特なのかどうか。これはもちろん歴史的経緯があると思うのですが。私は残念ながら、その点はあまり詳しくありません。ただ、基本的に教育制度そのもの、学校制度そのものがヨーロッパのものを持ってくるという考え方ですので、日本にあった寺子屋とかではなく、新たな、まさにパッケージ商品として、椅子に座り机を前にして、黒板を前にして先生が1人で多くの人を対象にしてしゃべるという、教育のパッケージがもたらされる。それを畳の上でやってもよかったのですけれども、そういったことはしなくて、ある種のミニチュアテーマパークのような形で学校というものをつくり出したわけです。
その中のアイテムの1つに制服というものも、最初からというわけではありませんが、徐々に溶け込んでいくわけです。ミニチュアヨーロッパなわけですので、その中にヨーロッパ風の服というものがなじんでいくという素地があったのではないかと思います。
④ 子どもの自由意思と規制
今村: 鈴木先生にお伺いしたいのは、どこまで校則で生徒を規制するか、という点です。
私の報告、あとは後藤先生の報告でも、自由意思について話題が出てきました。一方で校則の適用対象は子どもですよね。子どもに対しての規制は必要と考える人はまだ多いです。つまり、子どもというのは、きちんとしたものの考え方はまだできない。高校生といっても子どもは子ども。小学校なら、なおさら。髪の毛も短く刈らせておいたほうが、変な髪形をしないで良い、といった具合です。
学校には在学関係(児童、生徒と学校 設置者、学校との法関係)などもありますので、校長に広い裁量があるのは、理解できなくはありません。
ならば規制はどこまでなら許されるのか。割と難しいです。地域性の相違もあってもいいのか、高校と小学校・中学校でそれぞれ違いそうです。まだまだ発展過程の人々に対しては、パターナリスティックな観点から抑え付けるという部分があってもいいという意見もあります。先生のご意見として、どこまで彼ら彼女らを抑え付ければいいのかという問題をお伺いしたいと思います。
⑤ 子どもによる自己決定の原則
鈴木:今村先生から頂いた、子どもの制限の範囲に関するお尋ねに関してです。確かに従来は、良いものは大人が決めるというのが基本的な考え方でした。しかし、2022年に子ども基本法という法律もできまして、いいものを大人が決めて子どもに授けるということではなくて、子ども自体が自分たちのことについて自分たちで考えて決めていく。
大人がやっている良いことというのは、本当に良いことかどうか分からないですしね。大人が「この制服、かわいいだろう」といっても、子どもから見たら「何でそんな、ダサい服着なきゃいけないの」ということだってあるわけですから。
大人の良いが子どもの良いにはならない。その良さというものは、大人、子どもという形で、常に上下の流れがあるわけではなく、子ども自身が主体的に決めるということで良いのではないか、ということなのです。
もちろん、子どもに対する特別な配慮が必要なこともあります。それは例えば、子どもに対する特別な保護のための法律があります。飲酒、喫煙、あるいは児童ポルノの問題などです。子どもについては特別な配慮をして保護すべきである。それはもちろん、判断が未熟であったり、だまされてしまうということもありますから。子どもが自分で同意したから良いのかというと、そういうわけにはいかない領域もいくつかはあると思うのです。
しかし、基本的には子どもも大人と同じ権利の保持者である。そういったところをスタート地点に考えて、とりわけ子どもを保護するためには何が必要なのか。そういった観点からいくつかの保護的なことを制度と仕組みとして作っていくことが必要だと思います。「いや、こっちのほうがいい」、「スカートはもうちょっと長いほうがいいと思うぞ」とか、「髪の毛はもうちょっとさっぱりしたほうが中学生らしいぞ」とか、そういったロジックで管理していくとなると、それはまさにパターナリズムや、余計なお節介といった介入になっていってしまうのではないかと思います。
とりわけ高校生については、もう高校3年生、18歳は成人ですから、まさに権利の主体として尊重すべきです。その人たちに、こうでなければいけないというものを、いわゆる大人が押し付けるのは、かなり難しいことではないかと思います。
高馬:このように声が上がってきたということも、時代と思います。かつて男性はみんな丸刈りが当たり前と考えていましたからね。
鈴木:私も当時は丸刈りでした。
高馬:やはりその「当たり前」を疑っていくという姿勢が、どんどん社会に出てきたのかなと思いますね。
鈴木:子どもも、それを良いと思っていました。体罰の問題などはそうですよね。殴られた子どもが「僕は殴られてよかったと思っています」というようなことを言ってしまうわけです。
高馬:私もビンタされて「ありがとうございます」と言った気がします。
鈴木:いまだに、あれで本当に成長できましたと、言ってしまいがちです。同意があればいいのかというと、それはやはり問題がありまして、その難しさというのは非常にあると思います。
- お問い合わせ先
-
教務事務部 情報コミュニケーション学部事務室
駿河台キャンパス
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL.03-3296-4262~4
✉ infocom■mics.meiji.ac.jp ※■を@に置き換えてください。
和泉キャンパス
〒168-8555
東京都杉並区永福1-9-1
TEL.03-5300-1627~9